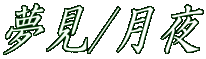
《Little Partner/Little Present》
(巽ヒロヲ・作)
![]()
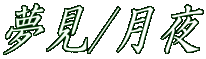
《Little Partner/Little Present》
(巽ヒロヲ・作)
「たっだいま〜」
「……」
いくつもある隠れ家の一つに戻ってきた萌木緑郎を、犬月ランは、精一杯の冷たい沈黙で迎えた。
乱雑に取り散らかった、ワンルームマンションの部屋の中。ランは、足の短いテーブルの前で、クッションの上に胡座をかいて座ってる。
テーブルの上には、ちょこん、と小さな白い箱が置いてあった。
「あ、ランちゃん、まだ起きててくれたんだ?」
「だって、約束したもん」
そう言いながら、ランが、じろっ、とメガネの奥の瞳を緑郎に向けた。
「これ、誕生日のケーキ?」
保冷剤の入った箱から、可愛らしい苺のショートケーキを取り出しながら、緑郎が訊く。
「そう」
「ありがと〜。って、あれ? ランちゃんは?」
「もう食べちゃったよ」
「あっはっはー、だよね〜」
緑郎はそう言いながら、ランと向かい合わせに座った。
ランが、ぷい、とそっぽを向く。
緑郎は、一向にめげた様子もなく、マグカップの中にインスタントコーヒーの粉末を入れ、だばー、と熱湯を注いだ。
「じゃあ、いただきます♪」
両手を合わせてそう言って、緑郎は、細いフォークを手に取った。
そして、嬉しそうに微笑みながら、ぱくぱくとショートケーキを平らげていく。
「おいしーね、このケーキ」
「緑郎が教えてくれたお店で買っただけだもん」
「そっかあ。あそこ、ブルドッグみたいな顔の頑固オヤジがギックリ腰で倒れて、んでもってお婿さんが後を継いだらしいんだけどさ。でも、味は変わってないんだよねー。さすがさすが」
「……」
ランは、横を向いたまま、幸せそうな顔でケーキを口に運び、コーヒーを飲んでいる緑郎を、ちらちらと見た。
が、緑郎が顔を上げ、目が合いそうになると、すぐに視線を逸らす。
「ふう〜、ごちそーさま。んまかった〜♪」
「……」
「あ、ごめん、一口くらいあげればよかったかな?」
「いらない。太るもん」
「そっかにゃあ? ちょっとくらいなら大丈夫だと思うんだけどねー」
いつもの軽い口調で言いながら、緑郎は、二杯目のコーヒーを作ってテーブルに置く。
「あ、ランちゃん、コーヒーは?」
コーヒーの中に砂糖とミルクをたっぷり入れながら、緑郎が訊いた。
「いらない」
「ふーん。確かに、あんまり遅くに飲むと眠れなくなっちゃうもんねー」
「コドモ扱いしないでよッ!」
大声をあげながら、ランは、ばあん、と両手でテーブルを叩いた。
「うわっぢゃぢゃぢゃぢゃぢゃー!」
緑郎が、奇妙な声で叫んでバネ仕掛けのように立ち上がり、ばたばたと足踏みする。
ランが叩いた衝撃で、テーブルの上のマグカップが引っ繰り返ったのだ。
「あ……」
何か言いかけるランをおいて、緑郎が脱衣所に駆け込む。
どうやら、コーヒーを浴びたスラックスを脱いでいるらしい。
ランは、立ち上がり、そっと脱衣場に近付いた。
「だ、だいじょうぶ? 緑郎」
「ん? あー、うんうん、ぜんぜん平気」
脱衣場を覗き込むランに、緑郎は、スラックスを洗濯機に放り込みながら言った。上はワイシャツ、下はトランクスという、どうにもしまらない格好だ。
「……」
一瞬ほっとした顔になったランが、ぎゅっ、と唇を噛む。
「だ、だったら、そんなおおげさな声、出さないでよ」
「あははっ、ごめんごめん」
そう言って、緑郎は、洗面台に向き直り、歯ブラシを取った。
「コーヒーいれ直すのめんどーだから、今日はこれでごちそうさまにするわ。ランちゃん、歯は磨いた?」
「……まだ」
「その白い歯が虫歯になっちゃったら、もったいないよー。甘いモノ食べた後はキチンと磨かないとダメなんだからね」
そう口では言いながら、緑郎は、極めていいかげんに歯を磨き、口をすすぐ。
と、緑郎が前かがみで水を吐き出した時だった。
がんっ!
「あだっ!」
緑郎は、もろに額を鏡にぶつけてしまった。
一瞬、後ろから突き飛ばされたのかと緑郎は思ったが、そうではなかった。
ランが、すごい勢いで背中から抱き着いてきたのだ。
「どうして……?」
「ほえ?」
「どうして怒んないのよっ!」
ランが、緑郎の背中に噛み付くような感じで、言う。
「ど、どーしてって言われても……怒った方がよかった? めっ、とか言って」
「そうじゃない……そういうこと言ってるんじゃないよ……」
ランの声は、泣き声に近い。緑郎は途方に暮れたような顔になった。
「なんで……そんなに……そんなふうに、優しいの……? 緑郎……優しすぎるよ……」
「え、えーっと……オレは、優しすぎだなんて思ってないんだけど?」
背中にランの体温を感じながら、緑郎が言う。
「オレは、ランちゃんにはいつも優しくしてあげたいし、それに、今日、帰るのが遅くなっちゃったのはオレが悪いんだしさ」
「でも、でも……優しすぎると、不安になるんだよ……」
「……どして?」
「だって……子供扱いされてるみたいだし……それに、あたし、まだ本当に子供だし……」
「……」
「今日、あの綺羅さんって人と一緒だったんでしょ?」
「えっ? い、いや、それはそーだったんだけど、やましいことは何もしてないよ」
緑郎が、声を一オクターブ高くして言う。
「うん、信じてるよ……。けど、やっぱり不安だよ」
「それは、えーっと……」
「だって、あの人、緑郎のこと好きなんだよ」
「はい?」
緑郎が、さらに高い声をあげた。
「気付いてないの?」
「い、いや、そりゃあ、綺羅ちゃんとはお友達だし、彼女もそー思ってくれてるだろうなー、ってくらいは自惚れてるけどさあ。でも……」
「あの人、絶対、緑郎のこと好きよ」
「……」
断言するランに、緑郎は口をつぐんだ。
ランは、緑郎の腰に後ろから抱きついたまま、腕をほどこうとしない。
「あたし、やっぱり心配だよ……。あの人、美人だし、胸もおっきいし……時々、しゃべり方とかヘンだけど、そういうとこも、なんか緑郎と気が合いそうだし……」
冬条綺羅本人が聞いたら苦笑いしそうなことを、ランは、真剣そのものの口調で言った。
緑郎が、ランの腕をそっと緩め、その場で振り返った。
そして、向かい合わせの格好でぎゅっとまた抱きついてくるランの髪を、撫でる。
「ランちゃんは、どうすれば安心するの?」
「え、えっと……」
ランは、眼鏡越しの上目使いで、緑郎の顔を見つめた。
ちょっとずれていたランの眼鏡を直してやりながら、緑郎が、その視線を受け止める。
「緑郎が、あたしに一番したいこと、して……」
そのあどけない顔を赤く染めながら、ランは言った。
「一番したいこと?」
「うん……。何をしてもいいし……あたし、何だって、してあげる……」
顔を伏せ、額を緑郎の胸元に押し付けるようにしながら、ランが言う。
「どんなエッチなことでもいいよ。今日は、緑郎の誕生日だし……それに、あたし……」
緑郎が、ランの頬を両手で挟み、再び上を向かせた。
そして、眼鏡に顔が当たらないように注意しながら、ちゅ、と口付けする。
「ほんとに、何してもいいの?」
緑郎が、ランの左の耳に口元を寄せながら、訊いた。
「うん……」
耳朶にかかる息の感触にぶるっと震えながら、ランが答える。
「……だったらさ、ちょっとしてみたいことがあるんだよね」
ランに見えないように悪戯っぽい笑みを浮かべながら、緑郎は、言った。
「や、やだぁ、こんなの……」
「どうして? 何でもしてくれるんじゃなかったの?」
「だって、だってコレ……」
ランは、ショーツ以外の全てを脱ぎ捨てた状態で、ベッドの上で身をよじった。
一方、緑郎は、Tシャツにトランクスといった格好である。
「大丈夫。無理に動かしたりしなければ、跡は残らないから♪」
そう言って、緑郎は、ランの手首を戒める拘束具の、最後の留め金をはめた。
褐色の、幅広の革の枷が、ランの細い手首にしっかりと巻き付いている。
両手首の枷を繋いでいるのは、銀色の鎖だ。
革手錠に両手を後ろ手に拘束され、ランは、怯えたような表情を浮かべている。
「え、えと……ホントに、今夜だけだよ?」
「うん、分かってる」
そう言いながら、緑郎は、ひょい、とランの眼鏡をその可愛らしい顔から外した。
「やだっ……か、返してェ」
「ふーん、眼鏡かけてないランちゃんの顔って、やっぱ新鮮だなあ〜」
「バカぁ! いいから返してよォ。何にも見えないよーっ」
極度の近眼のランが、いっこうに焦点の合わない目を怒らせる。
「いいのいいの。今夜は、眼鏡は必要ないから」
「ど、どういうこと……ああんっ!」
ランが、悲鳴をあげた。
緑郎が、ランの両目を、黒い鉢巻状の布を使って目隠ししたのだ。
「はい、捕らわれのお姫様かんせい〜」
「もーっ! 冗談やめてよっ!」
「冗談なんかじゃないよ。前に言わなかったっけ? オレ、こーいうのちょっと萌えるタチなんだってば」
「だ、だって、これってヘンタイだよ……」
「ごくごくかるーいSMだよ」
そう言いながら、緑郎は、後ろからランのスレンダーな体を抱き締めた。
「ひゃうっ!」
驚いたような声をあげながら、ランが身をよじる。
「やっ! やぁん! こわい……なんだかこわいよォ!」
「今夜は、何でも言うこと聞いてくれるんじゃなかったっけ?」
緑郎が、ランの耳元で言った。
「う……」
「あ、でも、ホントにイヤだったらやめるよ。それに、もしランちゃんがこんなの絶対にイヤって言っても、そんなことでオレはランちゃんのこと、嫌いにならないからね」
「ひ……ひきょうだよォ、そんなこと言うの……」
「で、どうなのかな?」
そう言いながら、緑郎は、腕の中のランの肌を、右手の指先でそっと撫でた。
「あうぅん……」
「もちろん、痛いことは絶対しない。もしランちゃんが辛そうだったら、すぐに中止するよ」
「……」
ランが、押し黙った。
そんなランの肌や髪を、緑郎が、繊細な手つきで、軽く撫で続ける。
「わ、わかったよ……」
指先で耳をくすぐられ、首をすくめるようにしながら、ランは言った。
「でも、でも、本当に痛くしちゃやだよ?」
「うん」
そう言って、緑郎は、ランの小さな乳房にそれぞれ両手を重ねた。
「あっ……」
出会ったころに比べれば、わずかに成長してはいるが、それでもまだごくささやかな乳房を、ふにっ、ふにっ、と柔らかく揉む。
「あ、あぁ、あ……あぅん……」
胸からじわじわと広がっていく快感に、小さく声をあげながら、ランはくねくねと体をうねらせた。
「ろ……緑郎って、胸、好きだよね?」
「え? そ、そっかな?」
「だって、かならず触ってくるし……あうん……て、手つきも、やらしい……」
「いやまあ、確かに好きだけどさ」
「……やっぱり、おっきい方がいいの?」
「え、えーっと……」
「いいよ……いっぱい揉んで……あたしの胸、おっきくして……」
揉めば大きくなる、という迷信を信じているのか、ランがそんなことを言う。
「いや、だからさ、オレは大きさとかじゃなくて、ランちゃんのおっぱいが好きなんだよ」
「んっ、あン……そ、そうなの? あん……あぁン……」
「そう。だから、大好きなランちゃんのおっぱいに、一杯気持ち良くなってほしいんだ」
「あっ、きゃぁん!」
ランが、声をあげる。
緑郎が、すでに勃起し始めたランの桜色の乳首をつまみ、軽くひねったのだ。
「やぁん……不意打ちィ……」
「ね。目隠ししてると、どうされるか分からなくて刺激的でしょ?」
「そ、そんなことないよっ……」
「そっかなあ? 絶対、いつもより敏感になってると思うんだけどにゃ〜」
そんなことを言いながら、緑郎が、ランの乳首をくりくりといじる。
「あっ、あうっ、んっ……はうン……!」
「ほーら、いつもより乳首がぴんぴんになってるよ」
「バっ、バカぁ! 知らないっ!」
ランが、革手錠の鎖を突っ張らせながら、抗議の声をあげる。
「ふっふっふー、抵抗しても無駄だよん」
「きゃうっ……んあっ、んっ……あぁんっ……!」
耳たぶや脇腹、太もも、背中など、すでに緑郎に知られてしまってる性感帯を次々と指先で刺激され、ランは、他愛なく声をあげてしまった。
「あっ……やんやんっ……あぅ……はぅン……はっ、はぁっ、はあぁ……」
甘い喘ぎをあげ続けるランの体から、次第に力が抜けていく。
緑郎は、そんなランのうなじや背中に、ちゅっ、ちゅっ、とキスを繰り返した。
「可愛いよ、ランちゃん……」
「あ、あぁん……はう……ひゃうぅン……」
「ふふふっ……何だか、悪者に捕まってるお姫様がイタズラされてるみたいだよね?」
「やっ……いやぁん、へんなコト言わないでよォ」
「そっかな? こーふんしない?」
「そんなんで、興奮なんかしないもん……あ、あぅ、うぅン……っ!」
緑郎の舌が背筋を這い上るのに合わせ、ランが、ぞくぞくとその体を震わせる。
「ね、想像してごらんよ……悪い泥棒に捕まって、手錠と目隠しをされて、エッチなイタズラされてるー、って感じで……」
耳元で言いながら、緑郎は、ランの柔肌に指を這わせた。
「やっ……やだ……そんなの……あっ、あぁん……はあぁ……っ!」
緑郎の語る“設定”がつぼに嵌まってしまったのか、ランの声が、いっそう熱っぽくなる。
緑郎は、そんなランの様子を見て、口をつぐみ、愛撫に専念し始めた。
「あうっ! や、やぁんっ! そんなに……そんなにしたら……ひあぅっ!」
すでにすっかり勃起し、可憐な乳輪の部分までぷっくりと膨らんでしまった乳首を、緑郎が重点的に攻める。
ランは、戒められた両手を開いたり握ったりしながら、乳房への愛撫にますます激しく喘いだ。
「あうっ……あっ……あああっ……緑郎……緑郎っ……!」
切迫した調子で名前を呼ばれても、緑郎は答えず、ただ、ランの白い背中に舌と唇を這わせるだけだ。
「んっ……ねえっ! 何か言ってよォ……こんなの……こわい……こわいよう……ひあああっ!」
両手を戒められ、視界を塞がれた状態で、ただただ性感を高められて、ランは怯えた声をあげた。
と、緑郎が、唐突に愛撫を中断した。
「え……?」
すっ、と緑郎の体が離れて行く感覚に、ランは左右に頭を巡らせた。
もちろん、目隠しをされている状態では、緑郎がどこに行ったのか分かりようがない。
「や、やだ……どこ? どこいっちゃったのよォ……きゃんっ!」
前方から優しく抱きすくめられ、ランは悲鳴をあげた。
「イ、イジワルっ! どうしてこんな……きゃあっ!」
抗議しかけるランを、緑郎は、無言でベッドに横たえた。
そして、ランの背中に大きな枕を当て、両手に体重がかからないようにしてから、その細い肢体に覆いかぶさる。
この時、ようやく、ランは緑郎が全裸になっているのに気付いた。
剥き出しのペニスが、太ももに当たってる。
それは、幾度も緑郎と体を重ねたランが驚くほどに固く、そして熱かった。
「緑郎……? ひゃうっ!」
ランが、またも悲鳴をあげる。
緑郎が、ランの可愛らしいショーツの中に、右手を差し入れたのだ。
「濡れてるよ、お姫様」
緑郎が、ちょっとかすれたような声で、ランに囁いた。
そして、巧みな指遣いで、ランのいたいけなピンク色の秘裂を、ぷちゅぷちゅと弄ぶ。
「あっ……やあぁっ……だ、だめェ……あああン!」
「すごい……すごく濡れてるよ……パンツ、びしょびしょになってるよ」
「や、やあぁン……そんな……はっ、はああン……ああァ〜ん」
もはや、悲鳴や抗議の声も快楽の波に飲み込まれ、甘い喘ぎにしかならない。
「悪い奴に捕まって、抵抗できなくされて、イタズラされて……なのに、こんなに濡らしちゃうんだ?」
「あんっ……ああぁン……だって、だってェ……」
ランは、さらなる愛撫をねだるように腰を浮かし、くねくねと動かしながら、声をあげた。
自分が、どれほど秘部への直接的な愛撫を切望していたのか、全身を貫く鋭い快感に思い知らされる。
緑郎が、ランのショーツを脱がした。
丸いヒップを浮かし、足を上げて、ランがそれに協力する。
「ひいいいいいンッ!」
びくんっ! とランの体が弓なりに反った。
緑郎が、ランの秘唇に口付けしたのだ。
そのまま、てろっ、てろっ、と舌を動かし、クレヴァスを舐め上げる。
「あ、あああ、あっ、あああうっ! あうっ! あっ!」
まだ莢に収まったままのクリトリスを優しく吸われ、ランは、その幼い体を痙攣させた。
真っ暗な視界に、チカチカと白い光が舞う。
が、緑郎は、ランが絶頂を迎える前に、口唇愛撫を中断させてしまった。
「あぁン……いやァ……も、もっと……もっとしてぇ……」
腰を浮かせて、ランがさらなる愛撫をねだる。
「はしたないお姫様だなあ……」
「だ、だって……はあぁ……ああぅン……」
「はしたなくて、エッチで、可愛いよ」
蜜に濡れたサーモンピンクの秘肉をゆるゆると指で愛撫することで、ランの昂ぶった快感をアイドリング状態に保ちながら、緑郎が言う。
「あ、ああん……切ないよぉ……アソコが切ないの……はっ、あ、あああ、あぅぅン……」
溢れさせた愛液で、シーツと、緑郎の手をぐっしょりと濡らしながら、ランは言った。
「イキたい?」
「うん……イキたい……イキたいの……おねがい、イかせて……」
「だったら、オレのものになってくれる?」
緑郎が、普段とは明らかに異なる口調で、静かに訊いた。
「え……?」
ランが、緑郎の言ったことを咀嚼するように、数瞬だけ考え込む。
「……なる……なるよ……」
ピンク色の舌で唇を舐めてから、ランは、そう言った。
「あたし、緑郎のものになる……ずっとずっと、ランは緑郎のものだよ……」
熱に浮かされたような声で、しかしはっきりと、ランがその言葉を紡ぐ。
「ありがと、ランちゃん」
元の口調に戻ってそう言ってから、緑郎は、ちゅっ、とランの半開きの唇に口付けた。
そして、ランの体を両手で抱え起こす。ランは、されるがままだ。
緑郎は、ベッドの上で足を伸ばし、自らの腰をランにまたがせた。
ランは、両膝をシーツにつくような格好で、熱い愛液の雫をぽたぽたとしたたらせている。
「ランちゃん、自分で入れてみて」
「う、うん……。で、でも、どこにあるのか分かんない……」
「ここだよ」
緑郎が、ランの細いウェストに手を置き、誘導する。
「あぁん♪」
とろとろに潤んだ秘裂の入り口をペニスの先端でまさぐられ、ランが甘い声をあげた。
「あっ……んんっ……入れるよ……入れちゃうんだから……っ」
ランが、両手を拘束された体をよじりながら、蜜に濡れたクレヴァスで緑郎のペニスの位置を探り、狙いを定める。
「んっ、くうううううううゥ……ンっ」
ランの狭隘な膣道が、しっかりと肉茎を咥え込み、奥へ奥へと導き入れる。
「あン……入ってくる……入ってくるよう……」
自らの体の内側の粘膜を雁首で擦りあげられる感触に、ランが白い喉を反らす。
根元近くまで侵入したところで、緑郎の先端が、ランの子宮口に達した。
「ひぁぅ……っ」
重苦しい衝撃を伴った快感に、ランが、ぷるぷると体を震わせた。
そのまま前方に倒れてしまいそうになるランの上体を、緑郎が、膨らみかけの乳房に手を重ねて、支えてやる。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ、はぁっ……」
ランは、敏感な粘膜で、じっくりと緑郎のペニスの感触を味わった。
「ね、緑郎……動いていい?」
「うん、もちろん」
「んっ……ふっ……んんっ……んんン……」
ランが、ゆるゆると、腰を動かし始めた。
その動きに合わせて、いたいけな外観の秘穴を、ぬらぬらと少女のシロップに濡れた肉竿が出入りする。
「ああん……あふっ、あぅン……あっ、ああっ、あっ、ここ、きもちイイ……」
探るように腰を動かしているうちに、自分の最も感じる場所を見つけたランが、声をあげる。
「きもちイイ……ああんっ、あっ、やぁんっ……とまんないよう……っ」
「エッチなお姫様だね、ランちゃんは……」
「だってっ……ああン、だってぇっ……!」
くいん、くいん、とその幼い腰を淫らに動かしながら、ランが頬を真っ赤に染める。
「イヤあ……あっ、ああんっ……すごい……もう、もうダメぇ……腰が、勝手に動いちゃうよう……ひああンッ!」
「いいよ……もっともっと気持ちよくなって……」
「はっ、はあっ、あぅ、んっ、んっ、んんンっ!」
ランが、とがった乳首を緑郎の手の平にこすりつけるようにしながら、腰の動きを速めていく。
きゅぅん、きゅぅん、と括約筋が締まり、緑郎の肉茎を搾り上げた。
摩擦を強めた性感粘膜が、さらに鋭い快楽を紡ぎだす。
「緑郎っ……すごい……すごいよおっ……あっ、ああんっ、き、きもちイイ……きもちイイの……イイっ……!」
「オ、オレも……すごくイイよ……ランちゃんの、エッチにからみついてきて……たまんないよ……」
「やんやんっ、は、はずかしい……っ! でも、でも、アソコがきゅんきゅんするの……ああんッ! あうっ! イイのっ! あうっ、あっ、あああああああっ!」
ランの小さなヒップが、さらなる快楽を求めて躍動し、そのたびに新たな愛液がぴゅるぴゅると溢れてシーツを濡らす。
緑郎は、膣肉の柔らかな締め付けと、靡粘膜同士の激しい摩擦に、確実に追い詰められていた。
拘束し、視覚と自由を奪ったはずの少女に上から攻められ、はぁはぁと喘ぎを漏らしてしまう。
「イキそうなの? ねえっ、緑郎、イキそうなのっ?」
ランが、どこか弾んだ声で訊いてきた。
「イイよ……イって……っ! 緑郎が好きな時に……あたしのアソコでイって……あたしの中でイってっ……!」
ランが、一層腰の動きを激しくした。
ぶちゅ、ぶちゅ、ぶちゅ、ぶちゅ……! という、年端のいかない少女の陰部が奏でるには淫靡過ぎる音が、部屋に響く。
「あくっ……ラ、ランちゃんっ……!」
いつのまにか主導権を奪われていた緑郎が、歯を食いしばるようにして声を漏らす。
「イって……緑郎、はやく……はやくイってェ……!」
自分自身も絶頂が近いのか、ランの声も切羽詰まってきた。
鋭い快感の波がひたひたと脳を浸し、愛しい恋人とつながっている場所が、かーっと熱くなる。
そんな感覚を、ランと緑郎は、ほとんど同時に感じていた。
「あっ……! ラ、ランちゃん……もう、オレ……!」
緑郎が、一足先に快楽に屈服し、絶頂を極めそうになる。
緑郎は、無意識のうちに、手の中の乳房にぎゅっと指を食い込ませた。
「あうううううううううっ!」
いつもなら痛みしか感じないはずの強い刺激が、限界にまで昂まっていた少女の興奮を、ぱあんと弾けさせる。
「イっ! イクっ! イクっ! イっちゃう! イっちゃう! イっちゃう! イっちゃうっ! イっちゃうゥ〜ッ!」
痙攣を伴った強烈な締め付けが、すでに射精の態勢に入っていた緑郎のペニスを、さらに搾り上げる。
「……っ!」
爆発的な快楽に、緑郎は、呼吸すら忘れた。
びゅううううううううううううううううッ! と、激しい勢いで、スペルマがランの膣奥に迸る。
「イクうううううううううううぅーッ!」
緑郎の精液がもたらす衝撃と温度に、ランは、さらなる絶頂に舞い上げられた。
びくん、びくん、びくんっ、と二人の体が、数度、震える。
「あっ……ああああああああっ……あああー……っ」
そして、ランと緑郎は、ほとんど同時に、がっくりと体から力を抜いた。
ランの華奢な体が、緑郎の体に覆いかぶさる。
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ……」
「はーっ……はーっ……はーっ……はーっ……」
二人とも、激しく喘ぎながら、呼吸を整えた。
ぬらぬらと濡れ光る萎えかけのペニスが、ぬるん、と膣圧に押され、外に出る。
そして、愛液と精液の混じり合った体液が、まだ閉じきらない秘裂から、とぷとぷと大量に溢れ出て、シーツに大きな染みを作った。
数分後――
緑郎は、ランの革手錠を外し、目隠しを解いてやった。
そして、まぶしそうに目をパチパチさせるランの顔に、眼鏡をかけてやる。
二人とも、まだ全裸だ。
「……」
ランは、いつもの軽薄そうな表情を浮かべた緑郎の顔と、そして、壁にかかっている時計を見比べた。
さっきまでぴったりと重なっていた長針と短針が、今、わずかにずれている。
午前零時一分。
「――緑郎のヘンタイ!」
ランは、おもむろに枕を両手で持ち、ぼかあん、と緑郎の頭に叩きつけた。
「ちょ、ちょっと待って、ランちゃん!」
「待たないよっ! 緑郎のバカ! スケベ! ヘンタイせーよくしゃっ!」
「どこでそんな言葉覚えたのさ? ……あたたっ!」
ぼっかん、ぼっかん、とランが緑郎の頭を枕で叩き続ける。
「ま、待ってってば! だいたい、ランちゃんだってすっごく感じてたじゃないかあ」
「あ、あれは、緑郎の誕生日だから、サービスしてあげてたんだよっ!」
顔を真っ赤に染めながら、ランは、枕をフルスイングで水平に振り回した。
ぼすうん! と枕が緑郎の顔にまともにぶち当たる。
「はぁ、はぁ、はぁ、はぁ……」
ランが、荒い息をつきながら、枕を手放す。
「も〜、ひっどいなあ」
緑郎は、苦笑いしながら、変形した枕をぽんぽんと叩き、形を整えた。
「分かったよ。もう、ランちゃんにはあーいうことしないからさ。ね?」
「……」
ランが、緑郎を、じっと睨む。
「ん?」
緑郎は、憎らしくなるほどの余裕を見せながら、小首を傾げた。
「……いいよ」
「何が?」
「ろ、緑郎が、どうしてもって頼むなら……たまになら、いいよ……って言ったの!」
「ホント?」
さらに顔を赤くしたランに緑郎がわざとらしく聞き返す。
こくん、とランは、頷いた。
「ありがと、ランちゃん。大好きだよーっ♪」
ぎゅっ、と緑郎が、ランに抱きつく。
「ああん、もう、たまにだからねっ!」
「分かってるってば」
言いながら、緑郎が、ランにキスしようとする。
むー、と一声うなってから、ランが、緑郎のキスに応えた。
二人の唇が、ぴったりと重なる。
そして、二人は、舌を絡め、唾液を交換しながら、いつまでもいつまでも、互いの唇の感触を愉しんだのだった。