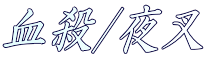
終章
![]()
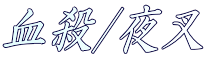
終章
俺は、その場所に帰ってきていた。
変わっていない。
伯母の家の近くの、山の中。
雑木林と雑木林の間にある、丈の高い草の茂る草原。
風景を、秋の夕日が、赤く染めている。
そこを、歩く。
と、目の前に、川の流れが現れた。
子供の頃、俺が溺れかけた、あの川だ。
夕暮れの空の下、どれくらいの深さなのか、よく分からない。
流れが、速い。
その速い水の流れが、俺に、何ともいえないような酩酊感をもたらす。
強い酒に酔い、悪酔いする寸前のような、そんな気持ちだ。
流れから目を逸らし、山を見た。
山は、暗い赤色に染まっている。
山を見ながら、俺は、彼女のことを考えた。
あの時以来、姿を消してしまった、あの小さな吸血鬼のことを――
萌木氏と、綺羅さんの話によると、裏で糸を引いていたのは、あの異端審問官――ジョバンニ・バッティスタ・チボーだという話だった。
ホテルの屋上から墜落しながら、なおも生きていたあの男は、しかし、戦うだけの力をもう残していなかった。
それでも、これまでの経験と知識を生かし、ノインテーターの棺の場所を探り、ハンターたちに知らせていたのだ。
そして、最後の棺の場所に、俺と、ミアと、そして手負いのフォン・ヴァルヴァゾルを呼び寄せた。
罠を張り終え、消耗しきった状態で息を引き取ったチボーは、最後に何を思ったのだろうか。
異端審問官であるチボーにとって、正教会に属する第八機密機関は、少なくとも盟友ではなかったに違いない。
それでも、チボーは、あの洞窟の中の詳細な様子を――複数ある入り口の位置や、地下水脈の存在などを――フォン・ヴァルヴァゾルに教えていた。
そして、この夏の長雨で蓄えられた大量の地下水は、俺と、そしてミアを飲み込み、外の谷川へと押し流したのだった。
俺は、川辺の岩に引っかかっているところを、駆けつけた萌木氏と綺羅さんに発見された。
ミアの姿は、無かった。
目から脳にまでクルスニクの骨の杭を貫き通され、さらに流れる水に晒されたミアが、どうなってしまったのか、分からない。
恐らく、俺とのチャンネルを維持することができず、記憶を失ってしまったのだろう。
そして、俺は、中途半端に“記憶の器”であることを続けている。
ここのところ、しばらく、萌木氏や、綺羅さんや、犬月兄妹に会っていない。
師匠とは、連絡さえ取っていなかった。
頭が――重く、痛い。
ミアの記憶が、俺の脳を緩やかに犯し続けているのだ。
ここ一年、満足に眠ることのできない日々が続いている。
そして、俺は、妙に冴えた目であちこちの昼と夜を歩き続けながら――ずっと、ミアを探しているのだった。
俺は、ゆっくりと、川辺の岩の上に、腰を下ろした。
立っているのが辛い。息が切れる。
これだけ早い川の流れのそばにいれば、なおさらだ。
俺の体は、あの時よりもさらに、変容してしまっている。
半ば以上、吸血鬼になってしまっているのだろう。
吸血鬼になってしまった部分と、未だ人間のままの部分との軋轢が、俺の神経を苛んでいる。
そして、俺にも、間違いなく、夕子と同じクドゥラクの血が流れているのだ。
目が、眩んだ。
ミアから預かった記憶が、俺の脳を内側から圧迫している。
それも、俺の中途半端な“吸血鬼化”に、拍車をかけているのかもしれない。
俺は、ひどく歪んだカタチで、人ならぬモノへと変わりつつあるのだ。
そのことを、意外なほど平静な気持ちで、受け入れる。
そう。そのことは、すでに覚悟の上だ。
吸血鬼たちと戦った時。
初めて人を殺した時。
夕子が目の前で灰になった時。
そして、あの小さな吸血鬼に出会った時。
その時に、俺は、自ら人でないモノになるということを、受け入れたのだ。
だから、もちろん、後悔は無い。
ただ……言いようの無い未練に引きずられるように、この場所に来ている。
ミアと、初めて出会い――あいつが、俺という存在を、初めて陵辱した場所に。
「ああ……」
思わず、声が漏れた。
風が流れる。
雲が流れる。
川が流れる。
時が流れる。
そして――
沈みかけた赤い太陽に照らされて――
「……ミア」
黒い服をまとった、小さな吸血鬼が、川の向こうに、いつの間にか佇んでいるのを、俺は見付けた。
軋む体で、ゆっくりと立ちあがる。
ぐらりと体が揺れた。
どうにか踏みとどまり、目の奥に鈍痛を感じながら、その姿を見る。
ミアは……悲しいほどに無邪気な表情で、小首を傾げ、俺を見ていた。
俺のことも――自分自身のことも――全て忘れ去った、そんな表情。
だが、その姿は、俺の知ってるミアと、少しも変わりが無かった。
「ミア……」
まるで、家から逃げてしまった臆病な仔猫を再び捕まえるような気持ちで、ゆっくり、ゆっくり、ミアに近付く。
川を、渡らなくては。
その事に対する、脅迫的な不快感を、俺は捻じ伏せる。
そう、恐怖など感じない。
そんなもの、ただの幻だ。
俺は、川に入った。
じゃぶ、じゃぶ、と音を立てながら、流れを横切る。
俺の太腿まである川の流れによろけながら、向こう岸のミアを目掛け、歩く。
頭痛が頭蓋骨の内側で渦巻き、呼吸が苦しくなる。動悸は早鐘のようだ。
嘔吐感が迫り上がり、上下感覚が混乱する。
俺は、今、どんな顔をしているんだろう?
ミアが、怯えたような表情で、数歩、後ずさっている。
俺は、ようやく、川を渡りきった。
目の前に……手を伸ばせば届きそうなところに、ミアがいる。
安堵が、俺の脚を萎えさせた。
がくりと、無様に膝をつく。
視界が、急速に暗くなっていった。
「ミア……」
その時、俺は――
もしかしたら、ミアに、笑いかけていたのかもしれない。
しばし、じっと俺を観察していたミアが、にっこりと無垢な笑顔を浮かべ、俺に歩み寄ってきたのだ。
その瞳は赤く染まり、口の端からは、尖った歯がはみ出ている。
ミアは、笑みを浮かべたまま、俺の肩を両手で捕えた。
見かけによらない、強い力。
ああ――昔、こんなことがあった。
そんなことを、ふと、思い出す。
それは、俺が住んでいた部屋でのことか――それとも、同じこの場所でのことか――
ミアが、俺の首筋に、顔を寄せた。
首筋に、ミアの熱い吐息を感じる。
恐らく、今、この小さな吸血鬼は、血に対する原始的な欲求のみによって動いているのだろう。
ミアが――遠慮の無い力で、がぶりと俺の首筋に噛み付いた。
「あ……」
俺は、声を漏らした。
愉悦と苦痛に、体が硬直する。
そんな俺を逃すまいとするかのように、ミアが、俺のことを両手で抱き締めた。
想像していたとおりの快美感と、想像もしていなかった喪失感が、全身を駆け巡る。
ミアが、喪っていた記憶を、俺から吸い上げ、取り戻しているのを、感じた。
そして――
「あ、あ、あ……」
俺は、今、ミアに血を吸われている。
俺の時間を――俺の存在の全てを、ミアに陵辱され、蹂躙され、剥奪されている。
「あぁ……」
死。
俺は、死ぬ。
死んで、ミアと――
……。
目が、覚めた。
目の前に、赤い目にいっぱいの涙を浮かべたミアが、立っていた。
「鷹斗……」
震える声で、愛しい小さな吸血鬼が、俺のことを呼ぶ。
「……おかえり」
俺は、立ち上がって――たぶん、軽く笑いながら――言った。
そして、ミアの体を抱き締める。
しばしためらった後、ミアが、俺の体に腕を回した。
空は、すでに夜の闇に支配されている。
そして、頭上には白い月。
その光を浴びながら、俺は、自らが夜の住人になったことを意識した。
もちろん、恐怖も、後悔も、不安も無い。
世界の半分は夜であり、闇なのだから。
そして人は、夜の間に癒され、闇の中で夢を見る。
つまり夜の闇は、俺達の憩いの場であり――そしていずれ帰るべき所なのだ。
だから、悲しいことなんて何もない。
泣くようなことは何一つとしてないのだ。
そんなことを――俺は、腕の中で小さな子供のように泣きじゃくるミアに、何度も何度も繰り返し言って聞かせたのだった。