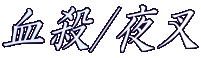
第九章
![]()
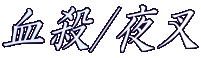
第九章
吸血鬼は、時を欺くことで、世界に対して負債を負い続ける。
その負債を、他者の命を以て贖うことこそが、“吸血行為”である。
吸血鬼は、すでに負債を負っているものであるため、吸血鬼の血によって吸血鬼の渇きを癒すことはできない。
そして、この、負債をどこまで許容できるかという容量――キャパシティーは、吸血鬼によって異なってくる。
例えば、モロイは、ヴァンピールに比べて遥かにキャパシティーが低い。
そして、このキャパシティーこそが、吸血鬼の能力の上限を決定するのだ。
吸血鬼は、吸血行為を通し、他者にこのキャパシティーを付与する事ができる。
吸血鬼によって吸血されたものが、吸血鬼となって蘇るのは、キャパシティーを付与されるか、自らの血統がキャパシティーを有していた時のみである。
そして、吸血鬼は、自らのキャパシティーを超えたキャパシティーを、相手に付与する事はできない。
新たに生まれた吸血鬼は、必ず、その“親”である吸血鬼と同等か、より低いキャパシティーを有するのだ。
それゆえ、吸血鬼は、緩やかにではあるが確実に衰退し続けている。
が、例外がある。
あらゆる吸血鬼の始祖とされる“カイン”と、そのキャパシティーを直接付与された“カインの花嫁”だ。
“カインの花嫁”は、二千年前、自らの血統の衰亡を予見したヴァンピールたちが、多くの犠牲を代償として創造した、“新たな吸血鬼の母”たるべき存在なのだ。
そして、もし“カインの花嫁”と同化することができれば、その吸血鬼は、無限に近いキャパシティーを得ることができる。
永遠をさらに超越した永遠――そんな矛盾を求める者こそ、吸血鬼と呼ばれるのだろう。
そして、“カインの花嫁”は、その吸血鬼の女神であると同時に、供物であり、生贄であったのだ。
――ミア。
二千年前、時を超えて召喚された“カイン”と交わることによって“カインの花嫁”とされた彼女は、自らを創造したヴァンピールたちに血を啜られ――そして、全てを奪い尽くされる寸前に、覚醒した。
その場に居た全ての吸血鬼たちを一瞬で葬り、逃亡したのだ。
そして――
――。
俺は、ミアと並んでベッドに横になり、天井を見つめていた。
ミアは、軽い寝息を立てながら、俺の体に身を寄せている。
先程の狂態が嘘のような、静かな、幼い寝顔。
ミアの冷たい肌が触れている箇所が、熱く、そして甘く、疼いている。
この、小さな体を、無限の貪欲に身を焦がす吸血鬼たちが、狙っている。
そして、吸血鬼たちがさらなる力を得ることを恐れる人間たちも、ミアの心臓を停止させようとしているのだ。
この広い世界と、永い時間の中で、ミアが安心して身を寄せることのできる場所は、本当に少ない。
人と、吸血鬼の狭間に身を隠す、黒い髪と赤い瞳の少女。
俺は、それを守る影だ。
この存在が終わる時まで、ミアの傍らに居てやろう。
そんな思いが、甘く温かな蜜のように、俺の内部を充たしている。
そして、俺は、ミアの華奢な手をそっと握り、目を閉じたのだった。
「緑郎さん、来てあげましたよ」
事務所のドアを開け、そう言ったのは、綺羅だった。
「はいはーい」
緑郎が、ディスプレイを見つめていた目を、綺羅に向ける。
明け方近い。ランは、とっくにアパートに帰っている。
雑然としたままの薄暗い事務所の中、ディスプレイから漏れる光が、緑郎の軽薄そうな顔を照らしている。
「ミアちゃんと鷹斗くん、出かけちゃったんですって?」
「うん。最後の棺の場所までね」
「……水臭いなあ。もう、あたしだって、体はきちんと動くのに」
「ミアちゃんたち、せっかく二人きりなんだからさ。お邪魔するのは野暮ってもんだよー」
そう言う緑郎の傍らに、綺羅が歩み寄る。
「じゃあ、どうして緑郎さんは、あたしを呼び出したりしたんです? しかも、こんな夜中に」
そう言ってから、綺羅が、その秀麗な顔に妖しい笑みを浮かべる。
「もしかしてぇ、もう、浮気しちゃいたくなったんですかー?」
「ゆーわくしないでよ。洒落にならなくなっちゃう」
緑郎が、大袈裟に肩をすくめた。
「別に、洒落で済ませなくてもいいんですよ?」
綺羅が、緑郎の顔に、必要以上に顔を寄せる。
が、緑郎は、普段の表情のままだ。
「……ま、今はいっか」
小さく溜息をつき、綺羅は背筋を伸ばした。
「“誰でもない”の居場所、つかめそうなんだよ。だから、ちょっと手伝ってほしくてさ」
緑郎の言葉に、綺羅が、少し目を見開く。
「いいですけど……見つけたら、どうすんです? 乗り込んじゃうんですか?」
「そうしよっかな、って思ってる。もう一つの決着が、そこでつくかもしれないし」
「は?」
「綺羅ちゃんにも、ちょっとは縁のある話だからね」
不審そうな顔をする綺羅に、緑郎は、微妙な笑みを見せながら、言った。
その場所に着いたのは、夕刻だった。
東海地方の、観光地として有名な風穴の近く。国道から大きく外れた山の中だ。
重なり合う緑の木々の間に、灰色の岩が、ところどころ剥き出しになっている。
昼間は雨が降っていたのだが、今は止み、西の空は晴れ渡っていた。
“誰でもない”差出人がメールで示した場所に向かい、すでに放棄されたハイキングコースの名残を、ミアと並んで歩く。
なんとも、穏やかな風景だった。
「ふふっ……」
ミアが、小さく笑った。
「ん?」
「なんだか、鷹斗と旅行してるみたい」
そう言って、ミアは、軽い足取りで、岩の一つに登った。
そのてっぺんに腰掛け、そっと目を閉じる。
風が木々の枝を鳴らし、そして、ふわりとミアの髪を揺らした。
しばしの間、ゆるやかに時間が過ぎる。
「……」
ミアが、瞼を開いた。
その双眸が、夕日よりも不吉な赤色に染まっている。
「見つけたわ……」
ぽつりとミアが言い、岩の上から飛び降りた。
「来たか……」
ノインテーターは、ゆっくりと身を起こしながら、言った。
ここ一カ月足らずのうちに、次々と自らの棺が破壊されたのを、ノインテーターは遥かな空間を超えて知覚している。
焦燥は、ない。
ノインテーターは、ただ、自らの立つ状況を冷静に分析していた。
“カインの花嫁”が、近付いている。
この場所まで到達するのも、時間の問題だ。
こちらの復活が完全でないうちに、決めてしまおうというのだろう。
が、それは、ノインテーターにとって最大の勝機でもある。
あの“花嫁”と、直接対峙することができるのだ。
ノインテーターは、痩せた体を棺から出した。
心地よい地底の闇が、白銀の髪の吸血鬼にまとわりつく。
周囲に、霧が出ていた。
ミアは、何かに導かれるように、丘の麓にある岩の裂け目を発見した。
木の茂る丘と丘の間の、谷間になった場所だ。
谷に流れる川は、上流であるにもかかわらず、意外なほど水量があった。この夏の長雨のせいかもしれない。
ノインテーターの気配を追って、ここまで来たのだ。
「この中よ」
そう言うミアに、俺はうなずき、ナップザックの中に入れていた銀の籠手を装着した。
そして、L字型の懐中電灯のスイッチを入れ、肩紐に固定する。
俺とミアは、狭い岩の透き間から、その中に入って行った。
霧が、視界を妨げている。どうやら、外との温度差で、霧が発生しているらしい。
深い洞窟だった。
所々、やや狭い場所を通過しながら、先へ、先へと進んでいく。
「……」
「……」
俺も、ミアも、無言だ。
周囲には闇が満ちている。
そのせいか、時間の感覚が、おかしくなっていくのを感じた。
そして、俺たちは、広い空間に出た。
「っ……」
思わず、息を飲む。
そこは、見事な鍾乳洞だった。
滑らかな、どこか原始的な生き物を思わせる鍾乳石が、水を滴らせながら無数に下がっている。
ぬめるような外見の内壁は、まるで、巨大な怪物の産道のようだ。
足元で、清浄な地下水が、幾筋かの小さな流れを作っている。
洞窟は更に続き、奥にはもっと大きな空間がありそうだ。
こんなにも大規模な鍾乳洞が、まだ人に発見されていなかったことに驚かされる。
入り口に当たる岩の裂け目が、周囲の風景に溶け込んでいたからだろう。
「いるわ」
ミアが、短く言う。
分かってる、という意思を込め、小さく肯いた。
さらに先を進む。
しばらく後、小さなホールくらいの空間に出て、俺とミアは立ち止まった。
奥の暗がりに、漆黒のマントを羽織った長身の男が立っている。
白銀の髪と、蒼白の肌。
目は、鮮血よりもなお紅い。
瞬時に、俺は理解した。
こいつが、ノインテーター……。
「最後の一歩を、其方から踏み出して来るとはな……」
言葉より先に、意味が、脳に響く。
「永かったぞ……“カインの花嫁”よ」
「あたしの名前は、ミアよ」
ミアが、距離を詰めながら、言った。
「誰の花嫁にもなった覚えはないわ」
「名前とは、其れだけ無意味だと云うことだ」
「無意味なのは、あなたの生そのものよ」
ミアが、天体を象った腕輪から、銀の糸を伸ばした。
「元より、生に意味などはない。有るのは、私という存在のみだ」
「意味は――生きる目的は、どこかに有るものなんかじゃないわ。――知るものよ」
「……汝の云う事は不可解だな」
「あたしには、あなたの言いたいこと、よく分かるわよ。賛成はしないけどね」
「成程……」
くくくくくくく……と、ノインテーターが、忍び笑いを漏らす。
その高い笑い声は洞窟の壁に反響し、何重にも聞こえた。
いや――
「――!」
一人、二人、三人、四人――
九人のノインテーターが、俺とミアを囲み、嗤っている。
綺羅さんから、話だけは聞いていたが……これが、分身か……。
一人一人が、幻覚ではあり得ない現実感をもって、そこにいる。
そう、この九人全てが、長い長い時を越えてここに立つ、本物のヴァンピール――ノインテーターなのだ。
「あなた……随分と無理をしているわね……」
ミアが、言った。
ノインテーターは、一度に多数の分身を出すほど、その後で存在の維持が難しくなるはずだ。
なのに、これだけの分身を現出させた。
つまり、この戦いに勝ち、ミアを手に入れることができなければ、自分自身が滅びるかもしれないということだろう。
「私も賭けを楽しみたくてな。此の様な気持に為ったのは、実に久し振りだ」
「そう……」
「其の少年にも、敬意を表さねば無礼に当たるだろうな」
初めて、ノインテーターが、俺に目を向けた。
ぞくん、と背筋が震える。
「良く、此れ迄“花嫁”を守って呉れた。礼を云おう」
「……」
俺は、答えない。
ただ、奴が動き出すどんな兆しも見逃すまいと、神経を研ぎ澄ます。
霧が漂う暗い闇の中で、次第に、視界が明瞭になってきた。
見える。
奴が、見える。
奴の視線の動きが――ゆるゆると動く指先が――笑みの形に歪んだ表情が――はっきりと、見える。
「しゃっ!」
九人のノインテーターが、ほぼ同時に、動いた。
俺は、くるりと身を翻し、ミアと背中合わせになる。
“両面宿儺 ”の構え。
互いに死角を補い合い、二人で多数の敵に相対する、葛城流の奥義だ。
初めて使う構えである。師匠と、その奥さんが、この奥義を使ったところを一回だけ見たことがあるだけだ。
しかし、俺は、この構えをとることにためらいはなかった。
背中に、ミアの気配を、しっかりと感じる。
ミアも、俺の意図を分かってくれているはずだ。
ミアが――動いた。
ぎゅわっ!
銀の糸が、軋んだ。
見なくても分かる。ミアの銀の糸が最初のノインテーターを葬ったのだ。
俺を排除し、ミアの背後を取ろうと、ノインテーターの一人が、迫る。
俺は、寸前で奴の爪をかわし、短い間合いから貫手を放った。
ぞぶっ!
銀の籠手の鋭い指先が、奴の心臓を貫いた。
が、こいつは囮だ。
別のノインテーターが、右側から俺の首筋を爪で切断しようとしている。
「はっ!」
俺は、今まさに炎に包まれ、灰に還ろうとしているその死体を、右側のノインテーター目がけ、両手で投げ付けた。
どん! と二つの体が激突する。
敵の体を盾とする――葛城流“月雲”。
動きを止められたノインテーターの体が、瞬時に寸断された。
ミアが、振り返り様に、銀の糸で絡め取り、それを引き絞ったのだ。
薄暗い闇に、火の粉のような灰が舞う。
そして、俺とミアは、崩れた態勢を整え、再び背中合わせになった。
「……」
目で、ノインテーターの数を数える。
三人、斃した
残りは六人。
「貴様……っ!」
俺の正面にいるノインテーターが、呻くように言った。
その、怜悧だった顔に、獣のように歪んだ表情が浮かんでいる。
明らかに、俺を見くびっていたのだろう。
人間である俺など、ノインテータにとっては、路傍の石にも等しい存在だったはずだ。
それでも、九人のうち一人を犠牲とし、万全の態勢で、俺を葬りにかかった。
なのに――結果は、この通りだ。
「貴様は、何者だ……?」
「……」
答えようのないその問いを、俺は無視する。
周囲にいるこの白銀の髪の吸血鬼たちと、背後のミアに、神経を集中した。
次は、奴も警戒してくるはずだ。
呼吸を整える。
“両面宿儺”の構えを崩さずにいれば、同時に攻撃してくるのは、一人に対し最大でも二人。三人目以降は、どうしてもタイミングが一瞬遅れる。
一度に二人をあしらえれば、少なくとも、次の瞬間までは生き延びることができるということである。
そして、生は、そんな一瞬の累積だ。
呼吸を、整える。
いかにノインテーターと言えども、ミアの、何重にも張り巡らされた銀の糸の結界を突破することは、至難の業のはずである。
あとは、俺が――
「きしゃああああッ!」
ノインテーターが、再び動いた。
「っ!」
ミアの動揺が、背中に伝わる。
ミアに二人。
そして、俺に四人。
二人による同時攻撃を、二回、ということか。
随分と高く買ってくれたものだ。
だが――
「うおおおっ!」
右から迫るノインテーターの心臓を、全身の力と体重をかけて、右手で貫く。
ノインテーターの、熱湯のように熱い血を、頭から浴びた。
「っりゃあああああああああああああっ!」
自分でも何を叫んでいるのか分からないまま、強引に体を捻り、左前方のノインテーターに向かい、走る。
予想外の動きだったのだろう。左のノインテーターの反応が、一瞬、遅れている。
今が、唯一の勝機だ。
どずっ!
右手にノインテーターの死体を串刺しにしてぶら下げたまま、さらに、もう一人のノインテーターの左胸に指先を抉り込んだ。
ごきん。
「ぐ!」
重い衝撃を伴った激痛に、思わず声が漏れた。
右肘が折れたらしい。さすがに負荷をかけ過ぎた。
二つの死体が、灰に還る。
解放された俺の右腕は、しかし、もう動かない。
俺は、まだ赤く燃えている灰を撒き散らすようにして身を翻し、第二波の攻撃を待つ事なく、右前に踏み込んだ。
そこに、ノインテーターがいる。
そいつの懐に飛び込み、爪による攻撃を無効化した。
鋭い爪がかすめた両の肩から、鮮血が飛び散る。
冷たいような激痛に、ぞわりと全身の毛が逆立った。
肉薄した俺の体を抱き締めるような格好で、ノインテータが長い牙を剥き出しにする。
信じられないほど大きく開かれた、獣のような口が、俺の喉笛を狙った。
「おおおおおおおおおっ!」
俺は、叫び声を上げながら、牙を避ける事なく、さらに前進した。
体の底から、自分でも驚くような力が湧き出ている。
首筋に牙の感触を感じながら、左手で奴の襟をつかみ、足を絡めて強引に倒した。
天地が、反転する。
「ぐぶっ!」
俺の喉に噛み付いた口から、熱い血が迸った。
俺の思惑どおり、天に向かって鋭く尖った鍾乳石――石筍が、奴の胸を心臓ごと貫いたのである。
奴が、俺の下で灰に還った。
垂直に傾いた視界の端で、ミアが、二人のノインテーターを同時に葬っている。
そして、最後のノインテーターが、俯せに倒れた俺を寸断すべく、無防備な背中に爪を立てようとしていた。
ここまでか――
どうにか起き上がろうとしながらも、俺は、一瞬だけ、死を意識した。
ぐんっ!
俺の意志とは関係なく、体が、何かに引っ張られるように宙を舞った。
ノインテーターの爪が空を切り裂き、その余波で、背中が大きく裂ける。
が、大量に血を失いながらも、俺は、生きた状態で地面に転がっていた。
ミアの足元だ。
「な……」
ノインテーターが、驚きの声をあげていた。
「何故、自らを危険に曝して迄、其の人間を助ける?」
ミアが――俺を?
ああ、そうか。
ミアは、俺のナップザックに、あらかじめ糸を絡めていたのか。
そして、それを引き寄せて――俺を救ってくれたのだ。
自らの武器を不完全な状態にしてまで……。
「あなたには、分からない?」
言いながら、ミアは、ふわりと手を舞わせた。
ノインテーターを囲む、銀の糸の結界が完成する。
「あなたほど長く生きていれば、あたしの今の気持ちも分かると思ったんだけど……」
「……」
ノインテーターは、何を思ったのか――その赤い目を閉じた。
思索にふける痩せた哲学者のような風貌が、そこに現れる。
ミアが、腕輪のギアを回転させ、糸を引き絞った。
ぎゅいいいいいいいっ! と、空間が軋む。
「已む無し――」
その一言を残し――
ノインテーターの体を構成していたものが、十幾つの肉片に分断された。
赤い血が舞い、そして、驚くほど大きな火柱が立つ。
ごう……っ!
そして――奴は灰になった。
他には、何も残らない。
「……鷹斗?」
ミアが、のろのろと立ち上がりかける俺に、声をかけた。
「だいじょうぶ?」
「……ああ」
右肘が砕け、両肩と、背中に大きな傷がある。
失血による悪寒で、歯の根が合わない。
が、それでも、俺は生きていた。
「少し休んだ方がいいわ」
「ああ……」
俺は、肯き、そしてその場にへたり込んでしまった。
全身が、細かく震えている。
その時――
「――!」
洞窟の奥から、新たな影が現れた。
綺羅と緑郎がたどり着いたのは、ごく普通のマンションの一室だった。
ただ、家具類の極端に少ないその部屋の中は、生活感に乏しい。
まるで、住人が入居して数日しか経っていないような雰囲気だ。
そんな中、薄暗いリビングの中だけが、乱雑に散らかっている。
部屋中に、さまざまなコード類が、のたうつように伸びていた。
そして、部屋のほぼ中央に据えられたパソコンラックには、大型のパソコンが収納されている。
パソコンの前には、電動式の車椅子があった。
車椅子には、小型の点滴台が備え付けられている。
その点滴台に提げられた透明なパックは、たった今も、車椅子に座る男に、生命維持のために必要な薬液を穏やかに注入し続けていた。
「こんばんは」
綺羅が、男に声をかけた。
男が、レバーを操作し、車椅子ごと綺羅の方を向く。
薄手のバスローブのようなものをまとったその全身に、白い包帯が巻かれていた。
顔にも、造作が分からないほどに、包帯が巻かれている。
粗い布の透き間から覗く青い目が、どこか乾いていた。
「あなたが“誰でもない”人ですか」
「……はい」
男の返事はしゃがれ、聞き取れないほどに小さかった。
男の命の灯が、消えそうになっているのが分かる。
だが、男は言葉を続けた。
「こんな格好で、失礼します……。つい先日までは、両足で立って歩くこともできたのですけどね……」
男のその声には聞き覚えがなかったが、綺羅も、緑郎も、その口調は知っていた。
「メールを使って、ハンターたちを誘導したのは、どうしてです?」
綺羅が、訊く。
「もちろん……あの、ノインテーターを、滅ぼすためですよ……」
「そんな体になってまで……。無理をしなければ、もっと穏やかな日々が送れたでしょうに」
「私の魂は……常に、神の御許にあります……。体の状態がどうであろうと、問題ではありません……」
「……」
男の言葉の空虚さよりも、その声の響きの弱々しさに、綺羅が、かすかに眉をしかめる。
「そろそろ……私に残された時間も、終わりのようです……。目の前のあなたを滅ぼすことができないのは、心残りですね……」
「あなたのささやかな満足のために死にたくはありませんから」
綺羅が、言う。
緑郎は、綺羅の背後に立ち、黙ったままだ。
が、その右手は、油断なく懐の中に入れられている。
「ミアちゃんを……“花嫁”さんを誘導したのは、なぜです?」
「……分かりませんか?」
男が、その罅割れた唇から、耳障りな擦過音を漏らした。
その、男の乾燥しきった笑い声が、かすかな咳き込みに変わる。
「あれは……私の……最後の、罠です……」
「……」
「こんな体になった私に、できたことは……情報を集め……駒を、動かすことだけ……。それでも……私は……」
男の口元から、言葉とともに、血がこぼれ落ちる。
照明が絞られた薄暗い部屋の中、男は、その生涯を終えようとしていた。
「魔女に、鉄槌を……吸血鬼に……杭を……人狼に……銀の……弾丸を……」
祈りの代わりに呪いを吐きながら、男は、がっくりとうなだれた。
しばし、静寂が、満ちる。
「あなたの――」
綺羅が、言った。
「あなたの思いどおりにはなりませんよ。……チボーさん」
車椅子の上の、ヴァチカンの異端審問官は、もう、その言葉を聞いていない。
ジョバンニ・バッティスタ・チボーは、死んだ。
その顔に、どんな表情が浮かんでいるのかは、包帯のせいで分からない。
「行こう、綺羅ちゃん。ここにいてもしょうがないよ」
緑郎が、右手を懐から出しながら、綺羅の背中に言った。
「外れくじ、引いちゃったね」
そう言う緑郎の顔には、滅多に人に見せない、暗く沈んだ表情が浮かんでいた。
なぜ、こいつが、洞窟の奥から――
別の入り口があったのか?
「フォン・ヴァルヴァゾル!」
ミアが声を上げた時には、フォン・ヴァルヴァゾルは、その左腕を振るっていた。
唸りを上げ、白いものが宙を貫き、疾走する。
――骨の杭?
自らの心臓を狙ったその杭を、ミアがかわそうとする。
が、杭は空中で大きく軌道を変え、凄まじい速度でミアの頭部に迫った。
「あ――」
「ミアっ!」
太い杭が、ミアの右目を深々と貫いた。
ミアの体が、人形のように倒れる。
立ち上がり、ミアに駆け寄ろうとする俺の足元で、岩が弾けた。
がおおおぉぉぉぉぉぉぉ……ん。
鋭い銃声が、洞窟の中に反響している。
見ると、フォン・ヴァルヴァゾルの左手に、拳銃が握られていた。ごつい、大口径の自動拳銃だ。
ミアの体が、ひくん、ひくん、と痙攣している。
“記憶の器”の術が――発動していない。
猛烈な頭痛の予兆を感じながら、俺は、混乱していた。
もし、脳が一時的に破壊されても、再生が終わるまで、ミアは俺の脳を使って動くことができるはずだ。
なのに――
「私――クルスニクの骨が、吸血鬼の邪悪なる技を封じているのですよ」
外さない距離にまで近付こうというのか、こちらにゆっくりと歩み寄りながら、フォン・ヴァルヴァゾルが言った。
その右腕は、肩から先がない。
「右肘のところで腕を切断されたのを機に、余った肩から肘にかけての骨で試してみたのです。ちょうど上腕骨の部分ですね」
淡々と、フォン・ヴァルヴァゾルが語る。
「幸い、予想通りの効果が得られました。私はこの結果に満足しています」
「貴様ぁ……っ!」
失血よりも、頭痛よりも、激怒で、目が眩んだ。
その眩んだ目が、フォン・ヴァルヴァゾルの姿を、かつてないほどはっきりと捉える。
一瞬一瞬が、まるでコマ送りのスローモーションのようだ。
時間は、瞬間の無限の連なり――
フォン・ヴァルヴァゾルが引き金を絞る一瞬前に、俺は動いた。
がうっ!
銃声が響くのと同時に、フォン・ヴァルヴァゾルが、拳銃を取り落とした。
踏み込む足で俺が蹴り飛ばした石が、拳銃に当たったのだ。
バランスを崩した状態で発砲した際の衝撃を、奴の左手が押さえきれなかったのである。
フォン・ヴァルヴァゾルが、懐に手を入れた。
取り出すのは、ナイフか、拳銃か――
そんなこと、もはや関係ない。
「しっ!」
奴の手前で地を蹴り、高く跳躍しながら前方に回転する。
いわゆる浴びせ蹴りの形だ。
俺の踵が、頭蓋骨の中でも急所である頭頂部を狙う。
フォン・ヴァルヴァゾルは、蹴りの威力を殺すため、前方に踏み込んだ。
――思惑どおりだ。
「りゃっ!」
「ぬうっ!」
フォン・ヴァルヴァゾルの驚愕の声を、俺は、すぐ間近で聞いた。
俺の両足が、前方からフォン・ヴァルヴァゾルの首に絡み付いている。
そのまま、俺は、前方に思い切り体重をかけながら、至近距離で左のフックを放った。
渾身の一撃が、フォン・ヴァルヴァゾルの顎を捕らえる。
脳を揺らされ、フォン・ヴァルヴァゾルの足が、がくんと折れたはずだ。
フォン・ヴァルヴァゾルが、後方に倒れる。
俺は、フォン・ヴァルヴァゾルの顎をすくい上げるようにして、奴に上を向かせていた。
がつっ!
堅い岩盤に、真っ先に、奴の頭のてっぺんが落下した。
衝撃で頸椎が砕けた感触を、左手に感じる。
“八雷 ”のうち、“大雷 ”。
葛城流奥義の、殺人技だ。
びくん――びくん――びくん――
フォン・ヴァルヴァゾルの巨体が、断続的に震える。断末魔の痙攣だ。
立ち上がり、奴の体を見下ろす。
フォン・ヴァルヴァゾルは、頭から白い脳漿の混じった血を溢れさせ、首を奇怪な角度に曲げながら――左手に、何かを握っていた。
アンテナのついた、小さな通信機のようなものだ。
「っ!」
危険を感じ、それを取り上げようとしたその時、痙攣するフォン・ヴァルヴァゾルの指が、その機械の赤いボタンを押した。
「しまった……」
どぉん――! という重い爆発音が響き、洞窟が大きく震える。
次々と鍾乳石が折れ、落下してきた。
「ミアぁっ!」
叫び、まだ横たわったままのミアの体に駆け寄る。
その時、思いのほか冷たい風が、ふわりと、背後から俺の体を撫でた。
どどどどどどどどどど……!
数瞬遅れ、連続した激しい音が、迫る。
振り向いた俺の視界には、大量の水があった。
洞窟の天井まで満たすほどの激流が、鍾乳石を次々と砕きながら、俺とミアに襲いかかる。
奴の仕掛けた爆薬が、地下水脈への通路を開いたのか――?
どっ――!
頭から水に飲み込まれた。
何も見えなくなる。
何も聞こえなくなる。
何も叫ぶことができなくなる。
身が凍るほど冷たい暗黒と静寂の中、俺は、激しい渦に撹拌され――そして、意識を失ってしまった。