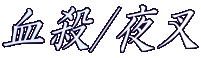
第八章
![]()
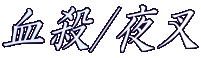
第八章
下水から脱出し、萌木氏が森の中に隠していたワゴンに乗ってからは、嘘のようにあっけなかった。
途中、ミアと、そして冬条綺羅と合流した。
綺羅さん――俺がこう呼ぶと、決まって彼女は“綺羅ちゃんって呼んで”と言うのだが――は、かなり消耗している様子だった。が、充分に休養を取れば元に戻ると、ミアは言った。
その綺羅さんとミアは、ノインテーターの本拠地を叩き、さらにはフォン・ヴァルヴァゾルと戦ってその片腕を奪ったという。
そして、今、俺達を乗せたワゴンは、東京方面に向けて高速道路を走っていた。
目的地は、東京近郊にある萌木氏の探偵事務所だ。
外の夜空では、歪んだカタチの朧月が、雲を照らしている。
「なんだか、何もかも中途半端ね」
そう言って、ミアは、同じ車内の師匠に視線をやった。
俺とミアは並んで最後列の席に座り、師匠は、それに向かい合う形で、後ろ向きにされた真ん中の席に座っている。綺羅さんは、半ば意識不明のまま、助手席にシートベルトで固定された状態だ。
師匠は、悠々とミアの視線を受け止めている。
「この人の扱いはどうするわけ? 仲間になったわけじゃないんでしょう?」
「どうするって訊かれてるぞ」
師匠は、にやにやと笑いながら俺に言った。
「言っておくけど、あたしはあなたに目を抉られたこと、忘れてなんかいないわよ」
「……恨みの深ェお嬢ちゃんだな」
師匠が、逞しい肩をすくめる。
「一緒に戦ってほしい、と言っても、いやだと言うんでしょう?」
俺の言葉に、師匠は、ふん、と鼻を鳴らした。
「お前さんこそ、ンなこと言うつもりはねえんだろうが」
「――はい」
「それでいいの? 鷹斗ちゃん」
俺の返事を聞いたのか、ワゴンを運転しながら、萌木氏が言った。
「師匠は、腕を両方とも傷めてますから」
「よく言うぜ。右は手前で折ったくせしやがって」
俺は、師匠の言葉に、沈黙で応えるしかない。
確かに、師匠の右腕を折ったのは俺だ。立ち会いの流れの中でのことと言えばそれまでかもしれないが、俺には、はっきりと師匠の利き腕を破壊しようという意志があった。
そして、師匠は、左腕にも深い傷を負っている。きちんと治るまで、その腕力は普段の十分の一も出せないだろう。
この傷だって、俺がもう少しうまく立ち回れれば、負うことはなかったのかもしれないのだ。
それに――
「おいおい、何か生意気なこと考えてやがんな」
ごつ、と師匠が、爪先で俺のすねを小突いた。
「俺のせいでとか俺がああすればとか考えてやがンだろう? 相変わらず頭に来る奴だな」
「……」
「俺とお前が並んで戦うことがねぇのは、もう、弟子でも師匠でもなくなったからだ。それだけのこったよ」
「俺は……」
「いずれ、息子をお前さんにぶつけてやる。鍛えてやってくれよ」
「知巳君を?」
「ああ。親子の縁だけは切れねえからな。ま、お前さんは分家、こっちは本家って奴だ。けど、遠慮することァねえンだぜ? 当たり前だがよ」
「……はい」
「――緑郎、いいぞ。ここで降ろしてくれ」
師匠が、首を捻り、運転席の萌木氏に言った。
「ここで?」
萌木氏が聞き返す。
外を見ると、ちょうど高速の出口が近付いている。
「このまま首都高に入る予定なんスけどねえ」
「俺を降ろしてからは好きにしろ。俺には、もうお前さんがたと一緒にいる理由はねえんだ」
「……逃げるわけ?」
ミアが、師匠に言う。
「仕切り直しだよ。今度また会ったら、決着を付けようぜ」
「我儘な人ね」
呆れたように、ミアが言う。師匠は、にやにやと笑ったままだ。
ワゴンが、一般道に出た。
街灯が、当たり前のように路面を照らしている。
萌木氏がワゴンを路肩に停めた。
俺が開けようとする前に、師匠が、引き裂いた布を巻いただけの傷ついた左手でドアを開ける。
「じゃあ、鷹斗のこと頼んだぜ。お嬢ちゃんよォ」
道路に立つ師匠にそう言われ、ミアは、少し間を置いてから肯いた。
「……そうだ、鷹斗」
師匠が、俺の方を向く。
「夕子ちゃんは、どうしたんだ?」
普段とほとんど変わらぬ口調で、師匠が言う。
俺は、師匠の細い目を見つめながら、口を開いた。
「吸血鬼になって――俺の目の前で、殺されました」
「……それで?」
「夕子を殺した奴は、俺が、殺しました」
「――分かった」
ふうっ、と師匠が太い息を吐いた。
そして、視線を地面に落とす。
「達者でな」
「はい、師匠も」
「俺は、もうお前の師匠じゃねえよ」
「いえ。そんなことはないです」
「可愛くねぇよなあ、お前って奴はよ」
言って、師匠は、うつむいたまま、ワゴンのドアを閉めた。
そして、俺達に背を向け、歩きだす。
萌木氏が、無言で車を発進させた。
未練がましく、窓の外の師匠の姿を見る。
視界から消えるまで、師匠は、一度もこちらを見てはくれなかった。
一週間後の、昼下がり。
「あーあ」
緑郎は、自らの事務所の真ん中に立ち、盛大にため息をついた。
部屋の中は、足の踏み場も無いほどに散らかっている。
「ちょっとォ、緑郎ってば、サボんないでよ」
そう、緑郎の背後から声をかけてきたのは、この探偵事務所で事務員の真似事をしている犬月ランだ。
彼女の兄である飄次郎は、ここにはいない。
綺羅は、彼女の自宅であるアパートの押入の中で眠っており、鷹斗とミアは都心のホテルに潜伏している。
外は、珍しく晴れ、何日かぶりの青空を白い雲が横切っていた。
夏の盛りのはずなのだが、気温はさして高くない。何年かぶりかの冷夏だ。
「そろそろ一休みしよーよー」
「だーめ。今日こそは、ここに人を上げられるようにするの!」
あからさまにだらけた緑郎の声に、エプロンをしてバンダナで髪をまとめたランが眉を怒らせる。
事務所再開のために掃除を始めてから丸三日目。緑郎自身が、カモフラージュを目的にやりたい放題に取り散らかした部屋の中は、一向に片付いていない。
「はっきり言って、今月、むちゃくちゃ赤字なんだよ? 怪物退治のお金も振り込まれてないし」
「やっぱり?」
「だからァ、普通のお客さんを呼べるようなかんきょーにしないとダメじゃない!」
「うんうんそのとーり。オレたち結婚しても、家計はランちゃんに任せとけば安心だにゃ〜」
「バカなこと言ってないで!」
ランが、顔を耳まで真っ赤にしながら、そこらに落ちていたファイルを次々に投げ付ける。
「ちょ、ちょっと、こんな所で夫婦ゲンカの予行演習なんてやめてってば」
「ふざけないで!」
「オレは本気だよ〜。帰ってきた時、プロポーズしたっしょ?」
「だ、だから、どうしていきなりあんなこと……!」
「ランちゃんはわあわあ泣いてたから知らなかったろうけどねえ、あの時、飄次郎ちゃん、すんごい目でオレのこと睨んでたんだよ?」
緑郎の言葉に、ランは手を止めた。
「……じゃあ、お兄ちゃんをおとなしくさせるために言っただけってこと?」
「そうじゃないよ。ただ、オレが本気なんだってことを知らせるには、いい機会だなって思ったんだって」
「あ、あたしの気持ちはどうなるのよお」
「ランちゃんの気持ちは、オレ、よーっく分かってるつもりだよん」
「ううう〜」
ランが、子犬のようなうなり声を上げる。
と、りんごーん、という安っぽい電子音が、部屋に響いた。
この部屋で真っ先に復元されたデスクトップパソコンが鳴らした音だ。
「……緑郎、メール来てる」
ディスプレイを確認したランが、緑郎に言う。
「誰から?」
「……あの人。“誰でもない ”って人よ」
「ふーん……」
緑郎は、珍しく真顔になり、ディスプレイを覗いた。
「やっぱ英語? なんて書いてあるの?」
「いつもと同じようなことだね」
辞書を探しかけて諦めた緑郎が、画面をスクロールさせる必要もないほど短い文面を、自らの英語力だけで翻訳する。
「“棺の数は九つ。今、八つ目の棺が破壊された。残る棺は一つ。その場所は……”か。おーお、地図まで添付してくれちゃって」
言いながら、緑郎は、慣れた手つきでマウスとキーボードを操った。
メールの出所を逆探知しようとしているのだ。
が、さして時間をかける事なく、マウスを放り出す。
「だめだなあ。やっぱ、いつもと同じだわ」
「同じなの?」
「うん。ここ以外にも、いろいろと目ぼしい裏稼業の連中に出してるって事は分かるんだけど……誰が出してるかは、さっぱり。さすがは“誰でもない”だけあるわ」
「……気味悪いね」
そう、ランが言った時、電話が鳴った。びく、とその小さな体が震える。
緑郎が、コードレスの受話器を取った。
「もしもし――ああ、飄次郎ちゃん? そっちでは、栄二ちゃんと仲良くしてる?」
緑郎が、そう口に出して言ったのを聞いて、ランがほっと息をつく。
「そっか……。お疲れさま。たった今、こっちにもメールが届いたよ。そう。見譜ちゃんなんかにも届いてた、あれがね」
ちら、とパソコンに視線を向けながら、緑郎が言う。
「足止め? そっか……。飄次郎ちゃんのパスポート、急いで作ったもんだからねえ。行きはよいよい帰りは恐い、だねー」
緑郎の言葉に、ランがそのはっきりした眉を寄せた。
「うん。きちんとしたの、すぐに手配するよ。今どこ? ――ゲッチンゲン? じゃあ、前に言った靴屋さんとこで待ってて」
話を続けながら、さらさらと手近な紙にメモを取る。
「え? ……あはは。もちろん仲良くやってるよ、お義兄サマ♪ うん。……んじゃねー」
緑郎が、受話器を元に戻し、ランに向き直った。
「飄次郎ちゃん、元気そうだったよ。荒事はほとんど無かったって」
「ちょっとは、あったんだ?」
「あの二人が相手じゃあ、並の吸血鬼が一ダース出て来たって何の障害にもならなかったと思うけどね。でも、警察に足止め食らいそうになったんだってさ。偽造パスポート見破られたみたい」
「……」
ランは、口をへの字に曲げて押し黙った。
今、萌木探偵事務所の切り札である飄次郎は、ドイツにいる。独自の路線でノインテーターの足取りを追ってヨーロッパにまで行った知人から、助力を頼まれたのだ。
強力な念動発火の能力を有するその男は、ノインテーターの本拠とも言える場所で、いくつかの棺を発見し、焼却していた。が、最近になって、ノインテーターの手の者らしき勢力からのプレッシャーが増してきたのである。
飄次郎は、緑郎と入れ替わるように、彼の地に向かった。そのためのパスポートは、緑郎が偽造したものである。そもそも、飄次郎はきちんとした戸籍をもっていない。
「で、飄次郎ちゃんは栄二ちゃんと一緒に八個目の棺をぶっこわしちゃったわけだけど……」
「残るは一つ、ね」
「うん。で、どうしてか、そのことを触れ回ってるのがいる。しかも、今度は九個目の棺桶の場所までおまけで付けてね」
「どこなの? そこ」
「えっとね……」
ランの質問に、緑郎が、顔を寄せ、小声で答えた。
「……罠、かなあ」
緑郎の答えを聞いたランが、難しい顔で言う。
「たぶんね」
「このこと……ミアちゃんに、知らせるの?」
ランが、メガネの奥の瞳に、心配そうな色を浮かべた。
「ミアちゃんのこと、気になるんだ?」
「そりゃあ、だって……友達になって、って言われちゃったもん」
そう言いながら、ランは、柔らかそうな頬をほんのりと染めた。
「でも、知らせないわけにはいかないよ。それに、ミアちゃんや鷹斗ちゃんだって、自前の情報ルートくらいあるだろうしね。ま、オレほどじゃないにしても」
「……」
「大丈夫。あの二人だったら心配ないよ。それに、ノインテーターをやっつけるチャンスは今しかないんだし」
「そう、かもしれないけどさ……」
「何しろ、あの二人にはオレたちの結婚式に出てもらわないといけないからねー」
「もう……ほんとにバカ」
ランは、呆れたように言い、そして、ちょっとだけ、笑った。
俺は、萌木氏からの電話が切れたのを確認し、携帯電話を充電スタンドに戻した。
高層ビル街のホテルの一室だ。
別に、こんなご大層な場所に泊まる必要はないのだが、大きいホテルであればあるほど身を隠しやすい、というのが、ミアの持論だ。
ただ、最近は、実はミア自身が、こういう豪奢な雰囲気の部屋が好きなのかもしれない、と思う。
居心地は、確かに悪くはないが、いいとも思わない。俺にとっては猫に小判だ。
ただ、こういう部屋にいると……ミアとの最初の夜を、思い出してしまう。
「……誰から?」
幼い声に似合わない物憂げな口調に、現実に引き戻された。
見ると、大きなベッドで眠っていたはずのミアが、体を起こしている。
まだ、ミアが目を覚ますには少し早い時間だ。
「萌木氏から、連絡があった」
「……あの、“誰でもない”相手からの手紙の件?」
「ああ。ここにきて、いきなり状況が錯綜してきたな」
「ヴァチカンが勢いを盛り返してきたのと関係あるのかもね。あの連中を無視し過ぎたのかもしれないわ」
「最初の棺を破壊したのは、ヴァチカンだったな」
「まあ、棺が教皇庁のお膝下にあったからかもしれないけどね。他にも、薔薇十字騎士団の残党や、上海に残った第八機密機関の別動隊、テンプルナイツ……それに、特務局や、緑郎の事務所の狼男まで……」
ミアが数え上げているのは、“誰でもない”男――男とは限らないが――のメールに導かれ、ここ一カ月の間にノインテーターの棺を破壊した勢力たちだ。
「ちょうど、日本が空っぽになったな」
まるで、一連のメールに誘導されるように。
「――そして、最後の棺の場所を知らせてきた」
ミアは、その細い指を組んだ。
「罠だろうな。誰が仕掛けたものかは分からないが」
「あたしも、罠だと思うわ」
俺の言葉に、ミアはあっさりと同意した。
「どうしようかしらね?」
訊かれて、俺は、一瞬だけ間を開けた。
反射的に、ミアはどうするつもりなのかを聞き返しかけ、やめる。
なぜなら――
「行こう」
「賛成だわ」
ミアの答えは、分かっていたから。
この目の前の吸血鬼には、永遠の安息の日などは訪れないかもしれない。
それでも、ミアが、束の間でも、憩いの時を過ごす様を、俺は見たいと思っている。
そのためにしなくてならないことなら、躊躇すべきではないのだ。
「鷹斗……」
ふっ、とミアは、窓の外に目を転じた。
「あの……男爵が、あなたに何か言わなかった?」
「え?」
「例えば……“記憶の器”のこととか……」
空は、次第に夕暮色に染まりつつある。
久しぶりに見るオレンジ色。
雨がずっとこの都市の空気を洗っていたためか、いつになくそれが鮮やかに見える。
「ミア……」
俺は、ベッドに腰掛けるミアの右側に座り、その細い肩に手を置いた。
こちらを向かせようとすると、逆らわずに、ミアが俺に顔を向ける。
濡れた、漆黒の瞳。
そこに映る俺の顔は――きちんとミアを安心させてやっているだろうか?
「俺は、ミアが好きだ」
「鷹斗……」
「ミアが側にいてくれて嬉しいと思うし、ミアにしてやれることがあるなら、なんでもしてやりたい。だから、俺を“記憶の器”として使ってくれるなら、それでいいと思ってる。……ただ、それだけだ」
「――それだけ?」
「いや、それだけじゃない、な」
俺は、言葉を探した。
もちろん、うまい言葉なんて見つからない。
脳裏に――夕子の苦笑いしている顔が浮かび、消えた。
「俺は、ミアのことが欲しい、って思っている」
「鷹斗……」
「そして、もし、お前が全てを忘れるようなことがあっても……俺は、お前のことを憶えているよ」
「……うん」
ミアは、肯き、俺に体を預けてきた。
薄い布地の向こうの、かすかな体温。
ほんのりと香る髪に、胸の奥がざわめく。
「ありがとう……」
つぶやくように言うミアの顔を上げさせ、口付けした。
驚くほどの体温を秘めた舌に、舌を絡める。
「ん……ちゅっ……うん……んぅん……」
甘えるようなミアの吐息が、唇と唇の間から漏れる。
俺は、その響きにかっと頭を熱くしながら、右手でミアの胸をまさぐった。
小ぶりなその胸の感触を、布越しに感じる。
幼い体を愛撫することへの、拭いがたい罪悪感が、ますます俺を興奮させた。
震えそうになる指で服のボタンを外し、左手でミアの肩を抱いたまま、右手を差し入れる。
「ちゅっ……うぅん……鷹斗……あっ、あン……ちゅっ、ちゅぶ……うぅン……」
キスの合間に漏れる、悩ましい喘ぎ声。
それを聞きながら、清楚なシルクの下着を上にずらし、白い乳房を露出させた。
はだけた黒い服の隙間から姿を現したその膨らみの頂点で、桜色の乳首が勃起している。
可憐な突起を指の間に挟むようにして、乳房を揉んだ。
「あん……あぁんっ……きもちいい……もっと……もっとして……」
ミアが、可愛らしい声を情欲に濡らしながら、ねだる。
俺は、自分の呼吸が荒くなっていくのを自覚しながら、ミアの胸を交互に手の平で愛撫した。
そうしながら、唇や頬、首筋、耳たぶへと、キスを繰り返す。
まるで陶器のように滑らかで冷たい、ミアの肌。
が、その奥に流れる血の熱さが、俺には感じられる。
まるで、ミアの血液の循環と、俺自身の心臓の拍動が、同調しているような感覚。
ミアの感じている快感と興奮が、手の平と唇から伝わってくる。
「鷹斗……あなた……」
と、ミアが、切なそうに眉を寄せた。
「気付いてるのね……自分が、あたしと同じようになってることに……」
「……ああ」
俺は、小さく肯いた。
そう、分かっている。
“記憶の器”である俺は、ミアと肌を重ねることで、純粋な“ヒト”とは別の存在へと変質させられているのだ。
漠然と感じていたそのことを、俺は、師匠と対峙した時に実感した。
自分の体力や感覚が、通常の成長とは違う次元で、劇的に昂進していたのに気付かされたのである。
もしかすると、あの骨の杭で傷つけられた箇所が、まだかすかに疼いているのも、そのことと関係しているのかもしれない。
俺の体は、吸血鬼のそれに近付いている。
だが――
「分かってる……。でも、これでいいんだ……」
俺は、ミアの艶やかな黒い髪を梳いてやりながら、言った。
「やっぱり、鷹斗には、何も隠し事できないのね……」
ミアの目尻に、涙が浮かぶ。
「本当は、あたしからきちんと言わなくちゃいけなかったのに……」
かすかに震える唇を、キスで塞いだ。
もう、これ以上、そのことを話す必要は無いと言う代わりに……。
そんな俺の気持ちを察したように、ミアが、狂おしく舌を絡め、唇を吸ってくる。
俺は、舌と唇でそれに応え、一層激しく乳房を愛撫した。
固く尖った左右の乳首を指で交互に摘み、鳥が嘴でついばむように刺激する。
「あぁん……ちゅっ、ちゅぶ……んちゅ……はぁん……鷹斗……鷹斗……っ」
うっとりとした声音で名前を呼ばれるたびに、脳髄が痺れる。
「ね、鷹斗……おねがい……下も、脱がせて……」
「え?」
「だ、だって……このままだと、染みになっちゃうわ……」
頬を赤く染め、きゅっと俺の服を小さなこぶしで握りながら、ミアが言う。
俺は、肯き、まるで王女にかしずく従者のように、ミアの足元に膝を付いた。
そして、スカートのホックを外し、するりと抜き取る。
それに合わせるように、ミアは、黒いブラウスを脱ぎ捨て、ブラを外した。
見ると、ミアの言った通り、ブラと揃いになったシルクのショーツに、船底型の染みがある。
思わず、じっと見入ってしまう。
「やっ……そんなに見ないで……」
ミアが、小さな両手でその部分を隠そうとする。
俺は、その手を遮り、そして、ショーツに両手をかけた。
「あぁ……」
ミアの熱い吐息を聞きながら、ショーツを下にずらす。
無毛の、いたいけな外観の秘唇が、露になった。
かすかに綻び、透明な蜜に濡れている肉の花弁に、顔を寄せる。
「だ、だめ……」
俺の息がそこにかかったのを感じたのか、ミアが、俺の頭を弱々しく押し止どめようとする。
その手にあらがい、俺は、ミアのその部分に口付けた。
「きゃう……!」
ミアが、小さく悲鳴を上げる。
俺は、濡れた肉襞の熱さに少し驚きを覚えながら、舌を突き出した。
甘やかにさえ感じられるミアの愛液を舐め取るように、舌を動かし、そこを刺激する。
ミアのその部分を口で愛撫するのは初めてだったが、俺には、それがとても自然なことのように思えた。
「だめ、だめよ、そんな……ああンっ! そこは……そこは……っ!」
そう言いながらも、ミアは、もう俺を押しのけようとはしていない。
熱く潤んだクレヴァスに沿って舌を上下に動かし、足の付け根の部分をてろてろと舐め回す。
「きゃ……っ!」
クレヴァスの上の部分を舌で刺激すると、ミアの体が、びくん、と反応した。
ちょうどそこがクリトリスにあたることを思い出し、夢中になって舌を蠢かす。
「あ、あう……きゃうん……っ! あ、ああ、ああ、あ……あんんんンッ!」
ひくんっ、ひくんっ、とミアの体が断続的に震える。
その快楽の源泉を口淫する俺の頭を、ミアは、いつしかしっかりと押さえ付けていた。
「ああ、だめェ……あたし、あたしもう……がまんできない……っ!」
ぎゅっ、と俺の頭を抱え込むように、ミアが上体を前に倒した。
「鷹斗……鷹斗が、あたしのを……ああぁ……すごい……すごいの……っ!」
新たに溢れる蜜が俺の口元を濡らし、甘く淫らな匂いがさらに強くなる。
俺は、まるで強い酒に酔ったような気持ちになりながら、ますます激しく口による愛撫を続けた。
襞と襞の間を舐め上げ、陰唇をしゃぶり、クレヴァスとアヌスの間にまで舌を伸ばす。
「すごいわ……あたし……あんっ、あん、あんんっ! おねがい、もっと、もっと強くして……おねがいよ……ああああああああっ!」
幼い声で紡がれる、淫らな願い。
それに応え、かすかに残っていた遠慮をかなぐり捨てて、唇と舌でミアの秘裂を蹂躙する。
「イ、イク……イクわ……あたし、もう……あああんっ! ねえ、鷹斗……イっていい? あたし、あたし、イキたい……イキたいの……ああうっ!」
がくがくと震える、ミアのいたいけなヒップ。
それを両手で固定し、勃起したクリトリスを強く吸引する。
「あーっ! イ、イクっ! イっちゃうっ! イっちゃうっ! イっちゃうっ! イっちゃううっ!」
ぷしゃあっ、と熱いしぶきが迸り、俺の顔を濡らす。
ミアは、俺の頭を抱え込んだまま、びくん、びくん、と体を震わせた。
ミアの絶頂が、俺の血流をどうしようもなくざわめかす。
全身が、異常なほどに火照っていた。
「あ、ああぁ……あぁ……はぁ、はぁ、はぁ……」
硬直していたミアの体が、ゆっくりと弛緩する。
俺は、荒い息をつきながら立ち上がった。
股間のモノが、隠しようがないほどに、スラックスを内側から圧している。
ミアは、そんな俺の下半身を、ねっとりと濡れた目で見つめていた。
その瞳が、朱色に染まっている。
「来て、鷹斗……」
ミアが、かすれたような声で俺を誘った。
服を脱ぎ、ベッドに上がる。
俺とミアは、大きなマットレスの上で膝立ちになり、互いに抱きしめ合った。
ちゅっ、ちゅっ、とミアが俺の胸に口付けする。
小さな舌で乳首をちろちろと舐められ、俺は、思わずのけぞってしまった。
シーツに尻を落として胡座をかくと、ミアが、俺の頬に両手を当てた。
そして、彼女自身の愛液で濡れた俺の顔を、てろてろと舐める。
手の平はひんやりと冷たいのに、彼女の舌は、驚くほどに熱かった。
「鷹斗の顔……あたしのいやらしい味がするわ……」
ふっ、と、その幼げな顔には淫らすぎる笑みを浮かべながら、ミアが言った。
その表情を見ただけで、すでに完全に勃起しているペニスに、さらに熱い血液が集まる。
ミアが、そっと右手を下にやり、俺のペニスに手を沿えた。
「熱いわ……」
うっとりと、ミアは言った。
「熱くって、固くって……ぴくぴく動いてるわ……素敵よ、鷹斗のペニス……」
俺の耳に口を寄せ、ミアが、淫らな言葉でさらに俺を昂ぶらせる。
俺は、たまらなくなって、ミアの細い腰を引き寄せた。
「あん……」
どこか嬉しげな悲鳴を上げて、ミアが、俺に身を寄せる。
「したいの? 鷹斗……」
ミアの問いに、俺は、肯いた。
もう、声なんて出せるような状態じゃない。
ミアは、満足そうに微笑んだ。
「うふ……鷹斗、素直ね……嬉しいわ……」
ミアが、俺の腰を膝でまたぐような姿勢のまま、焦らすようにゆるゆると俺のペニスを右手で扱いた。
もしかすると、さっき俺に一方的にイかされた仕返しのつもりかもしれない。
鈴口から溢れ出た汚穢な体液が、ミアの細い指をにちょにちょと濡らす。
「ああ、本当に素敵……どうしよう……触ってるだけで、体が熱くなっちゃうわ……」
ちろり、とミアの舌が、唇を舐めた。
「やっぱり、もう我慢できない……。い、挿れるわね、鷹斗……」
そう言って、俺の返事も待たず、ミアは、俺の亀頭部を自らの秘部にあてがった。
「あうん……」
熱い粘膜と粘膜が触れただけで、ミアの体から、力が抜けかかる。
俺は、ミアの腰をさらに引き寄せ、徐々に落としていった。
「あ、ああっ……す、すごい……入ってくる……入ってきちゃう……!」
肉竿が、ミアの膣内と擦れ、鮮烈な快感を紡ぐ。
「んっ……んあ……あああ……あぁン……! きもち、いい……きゃうっ!」
先端が、ミアの最深部に到達した。
熱く、ぬめらかな粘膜が、俺のペニスを根元まで包み込む。
あのいきり立った肉棒が、全てミアの小さな腰の中に入ってしまったことが、少し信じられない。
見かけよりよほど貪欲なミアの秘部が、うねうねと動き、俺を刺激する。
「あ、あぁ……鷹斗のペニス……奥まで届いてるわ……嬉しい……」
きゅっ、とミアが俺の首に両手を回した。
肌と肌が密着し、互いの息が耳朶をくすぐる。
「鷹斗ので、あたし、いっぱいになってる……すごいの……すごく、幸せ……」
「ああ」
俺は、肯いて、そしてミアの小さなヒップをゆっくりと動かした。
「あ、ああん……あっ……ああン……鷹斗……たか、と……っ!」
しっかりと絡み付いた膣肉の締め付けに逆らうように、ミアの腰を上下させる。
充分すぎるほどの愛液にぬめった粘膜と粘膜が、滑らかに擦れ合いながら、鋭い快楽を生む。
「ああん……う、動いてる……動いてるの……鷹斗のが、あたしの中で、動いて……あんっ、あうっ、あん、あんんっ……!」
次第に、ミアは、自ら腰を動かし始めた。
くいん、くいん、と、水蜜桃を思わせる瑞々しいヒップが、可愛らしく踊る。
「あくっ……んん……はぁン……腰が、勝手に動いちゃう……あン……あぁン……」
喘ぎ、声を上げながら、ミアが俺にしがみついた。
半開きになった唇で、俺の口元を探る。
顔をずらし、キスをすると、ミアが、切迫した様子で鼻を鳴らした。
普段からは考えられないようなミアの乱れた様子に、股間のものがますます膨張してしまう。
「んっ……んむっ……ちゅ……ちゅばっ……ぷはっ、はーっ、はーっ、はーっ……んちゅっ……んーっ……」
キスの合間に息をつき、そしてまたキスをする。
まさに、貪るような、噛み付くような口付け。
高まる性感に、ミアの喘ぎはますます激しくなる。
「あん、あぁん、あん……鷹斗……好き……好きよ……好きっ……!」
「俺も……ミアのことが、好きだ……!」
互いに分かり過ぎるほど分かっているはずのことを、それでも言わずにはいられない。
想いを告白することで、ますます性器が熱くなり、快感が高まっていく。
まるで、この想いすら、俺とミアが感じている快楽に奉仕しているかのようだ。
「はーっ、はーっ、はっ……んあっ……あ、はあぁっ……!」
ミアの声が、ますます高くなっている。
俺は、ミアが、勃起した乳首を俺の胸にこすりつけているのに気が付いた。
と、俺の視線の動きで、ミアも、自分のしていることに初めて気付いたようだ。
「あ……やぁん……」
ミアが、恥ずかしそうに顔を背ける。
ぷくん、と乳輪の部分まで充血して固くしこった乳首。
それを、ミアは、俺の肌にこすりつけ続けている。
「だ、だって、しょうがないじゃない……きもちいいんだからァ……あんっ、あんんっ……!」
拗ねたような声でそう言いながら、幼く白い体が、全身で快楽を貪っている。
俺には、ミアのそんな様子すら、愛しく思えた。
左手でミアの体を支え、右手の指で、ミアの乳首を愛撫する。
「あうっ……! きゃん! あうんっ!」
ミアは鋭い声を上げ、喉を反らした。
小粒のサクランボを思わせる乳首を指先で転がし、摘み、軽くひねる。
「ひっ、ひあああああああんっ! あんっ! やっ、やああっ!」
少し強く引っ張ると、ミアは、いやいやとかぶりを振った。
「悪い、痛かったか?」
「ちっ、ちがう……の……感じ、すぎて……あぁん、恥ずかしいィ……」
口調までどこか幼くしながら、ミアが、言う。
俺は、ミアの乳首や乳房を左右交互に嬲り続けながら、自らも腰を突き上げた。
「あんっ! あうっ! あんっ! ああんっ! あんっ!」
俺の動きに合わせ、ミアが断続的に悲鳴を上げた。
きゅんっ、きゅんっ、とミアの体内が締まるのを、ペニス全体で感じる。
まるで、手で握られてるような、そんな締め付けだ。
柔らかく、それでいて強烈な、膣内の動き。
それが、次第に俺を追い詰めて行く。
が、絶頂が近いのは、ミアも同じだった。
「あっ、ああっ! 鷹斗っ! あたし……あたし、また……ああんっ!」
膣肉の動きは、ミアがアクメを迎える前兆だ。
それが、俺のペニスを搾り上げ、容赦なく射精を促す。
単調なはずのリズムが俺とミアを追い詰め、そして、シンクロさせていた。
「鷹斗っ……! ああんっ! 好きィ……好きなの……! 鷹斗が……鷹斗が好きっ……! ああん、イイっ……鷹斗のオチンチン、きもちイイのっ……好きっ……!」
もう、俺は、ミアのあられもない言葉の意味を追うことすらできず、ただその興奮をダイレクトに感じるだけだ。
同調する鼓動。重複する血流。
ひりひりするような、痛みと紙一重の危険なまでの愉悦を、ミアとともに感じる。
ペニスが、熱い。
そして、それを包み込むミアのヴァギナも、火傷しそうなほどに熱かった。
「イイの……あぁんっ、きもちイイ……っ! 鷹斗の……鷹斗のオチンチン好きィ……っ! イク……イクイクイクうっ! 鷹斗のオチンチンでイっちゃうううぅーッ!」
熱い塊が、体の一番底からマグマのように迫り上がる。
ペニスを破裂させんばかりに強烈な射精欲求が、限界にまで達していた快感をさらに高めた。
「イ、クうぅ……ッ!」
ぐっ! とミアが俺の背中に爪を立てた。
ミアの絶頂に呼応して、俺も、精を迸らせる。
膣内に溢れ出る大量の精液が、重力に逆らって、激しい勢いで子宮口を叩いた。
「んんんんんんんっ! んあっ! あーっ! ああああああああああああああああああぁぁぁぁぁぁぁぁーっ!」
血液が逆流し、肉体が反転するかのような快楽の渦が、俺とミアとをどろどろに融かす。
冷たさを覚えるほどに鋭い性感と、目が眩みそうなほどに激しい愉悦。
そして、燃えるように熱く、血のように赤い、圧倒的な奔流。
存在そのものが剥奪され、蹂躙され、凌辱される。
死と、ほぼ同意儀の、快感……。
自我が、しばし消える。
俺が俺でなくなる。
そして――
――。
ミアの記憶が、準備された“器”である俺の脳に流れ込む。
そして俺は、“カインの花嫁”とは何であるのかを、今、知ったのだった。