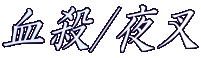
第七章
![]()
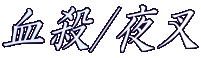
第七章
夜空の星の光さえ届かぬ、湿った闇。
その闇に包まれたさらなる暗黒の中で、彼は、覚醒した。
赤い瞳にかすかな光を灯らせ、棺の蓋を開けて、半身を起こす。
白銀の髪。蒼白の肌。
漆黒のマントに包まれたその体躯は、まるで病んでいるように痩せ衰えて見える。
この次元に姿を現すために、かなりの無理を重ねた。
月の満ち欠けが、少なくともあと一度は暦を刻まねば、ここに戻ることは出来ないはずだったのだ。
ようやく形を持った姿を現すことが出来るようにはなったが、全ての分身を同時に制御するには、まだ幾許かの時を暗闇の中で過ごし、休まねばならないだろう。
手遅れになるかもしれない。
すでに自らの“巣”が破壊され、右腕と頼んだ女も灰に還ってしまった。
それでも、まだ、この国の中枢に植え付けた自らの種子は、増殖を続けている。
早急に力を取り戻さなくてはならない。――“カインの花嫁”を手に入れることで。
そして、敵を排除し、態勢を整えれば、まだ充分に勝機はあるはずだ。
すでに、薔薇十字結社は壊滅させた。
ヴァチカンと第八機密機関を滅ぼし、さらには“舞踏会”を完全に掌握する。
そのために、あの黒髪の女は、自ら犠牲となったのだから――。
もとより、祈りの言葉など、口にする意志も資格も無い。それでも彼は、千坂静夜のために、しばらく、黙祷した。
そして、ゆっくりと顔を上げ、閉じていた目を開く。
その真紅の瞳に――わずかな疑惑の色が有った。
「――誰かが、此の場所に来たな」
闇に語りかけるように、静かに呟く。
「誰かが――私の棺に――触れた」
そして、ノインテーターは、微かな笑みを浮かべながら、再び棺の中に身を横たえ、その蓋を閉めた。
「一時休戦だ」
サイレンが鳴り終わった時、師匠は俺に言った。
「俺は、このまま続けてもいいんですよ」
「分かったよ。じゃあ、取り敢えず俺の負けってことでいい」
「取り敢えず、ですか?」
「ごちゃごちゃうっせえなあ、とにかく走れ!」
そんなことを言い合ってるうちに、空気が煙っぽくなってきた。
俺と師匠は、煙が満ちてきた廊下を走りだした。
ここは、建物の中でもかなり内側に当たるはずだ。確かに、ぼさっとしていては、脱出に支障が出る。
廊下は、所々、防火シャッターらしきものに塞がれていた。
ただのシャッターではない。鋼鉄製の、おそろしく頑丈そうなものだ。
外から操作して開けることも、できそうにない。
廊下をあてもなく走ってるうちに、煙が充満してきた。
すでに、蛍光灯の明かりが切れ、非常灯らしきものに切り替わっている。
「こりゃあ、ちょっとやべえな」
師匠が立ち止まり、苦笑いに似た表情を浮かべ、言った。
「何が起こったんでしょう?」
「知るかよ。まあ、事故じゃねえだろうけどな」
俺の問いに、師匠が答える。
「俺だって、ここに招待されて日が浅いンだ。それに、きちんと中を案内されたわけじゃねェしな」
「……閉じ込められましたかね?」
「かもな。どうも、建物の中へ中へと追い込まれてるような気がする」
「そうですか」
「――けっ。もう少し可愛げのある反応を返したらどうなんだよ」
ずいぶんと理不尽なことを言いながら、師匠が、再び走りだす。
とりあえず、煙が薄い方へ、薄い方へと、俺達は移動した。
一向に、窓のある場所には出ない。
と、俺は、あるドアの前で立ち止まった。
「どうした?」
「……いえ、何だか、ちょっと気になって」
「はあ?」
師匠の怪訝そうな声を聞きながら、ドアを見つめる。
黒い、鉄製の、大きな扉。
俺の勘が正しければ、ちょうど、建物の中央に当たる場所だ。
「おい、ンなとこ開けたって、外には通じてねェぞ」
「俺もそう思います」
言いながら、レバー型のノブに、手をかける。
鍵がかかっている。ノブの下に、カードスロットがあるところを見ると、カードキーか何かを差し込む仕掛けらしい。
「ただ……この中から、呼ばれてるような気がして……」
「なんだと?」
「それに、多分、このまま奥に行っても外には出られないですよ」
「おいおい、何を根拠にンなこと言ってるんだ? それに鍵を開けることだってできねえだろ?」
「それは……」
その時、ノブを握っていた俺の手に、かたん、と小さな手応えがあった。
ノブを動かすと、鍵が開いている。
「――開きました」
「なにィ?」
言って、師匠は、その細い目で周囲を見回した。
そして、天井の一点に目を止める。
「……あそこに、監視カメラがあるな」
「え?」
「あれだ。もしかしたら、あれで俺達を見張ってた奴が、外から操作したのかもしれねえ」
「……罠、ですかね?」
「さあな」
そう言ってる間も、廊下には、薄い煙が充満してきた。
少し、呼吸が苦しくなる。
「開けます」
「分かった。お前さんの好きにしな」
俺は、重いドアを開けた。
中は真っ暗だ。やはり、どこにも窓は無いらしい。
俺は、部屋の中に入った。師匠もそれに続く。
煙を防ぐため、ドアを閉めた。
明かりのスイッチを探り、それを点ける。
薄暗い照明が、室内を照らした。
「……っ」
隣で、師匠がかすかに息を飲む。
コンクリートが剥き出しになった、学校の教室ほどの広さの部屋に、様々な道具が転がっている。
それは――全て、拷問具だった。
大小様々な刃物。内側に刺のある手枷と足枷。刺の生えた鞭。巨大なペンチを思わせる鉄具。斧。鋸。火鉢と焼き鏝。部屋の中央にある粗末な寝台には、奇妙な滑車やレバーのような物が備え付けられている。
人体を痛め付け、破壊するための様々な器械が、冷たい金属の構造を晒していた。
部屋の中央の寝台の上に、あの銀の籠手がある。
フォン・ヴァルヴァゾルに拘束される時に、奴に奪われたものだ。
つまり、ここは……あのフォン・ヴァルヴァゾルの部屋、というわけか。
部屋には、かすかに鉄と血の匂いが漂い、床と壁にはぞっとするような黒い染みがある。
そして、こちらから見て左右にある壁には、奇妙な磔台があった。
幅三〇センチほどの得体の知れない黒い金属で作られた、高さ二メートル以上はある十字架。
そこに、それぞれ、少年と女が括り付けられていた。
胸の所で交差した黒い革のベルトが、十字架の交差する部分に、それぞれの体を結び付けている。
「こいつぁえげつねェな……」
師匠が、吐き捨てるように言った。
俺も、喉元に込み上げてくる何かを、こらえている。
少年と女には、四肢が無かったのだ。
腕は、肘関節で、脚は、膝関節で、それぞれ切断されている。
剥き出しの傷口には包帯らしきものが巻かれ、それを、鮮やかな色の血が濡らしていた。
少年も、女も、金色の髪をした白人である。全裸だ。
二人の容貌の美しさが、一層、状況の無残さを際立たせている。
と、女が、うっすらと目を開いた。
青灰色の瞳が――瞬時に赤く染まる。
「鷹斗っ!」
師匠の声に、反射的に身を捻った。
視界の端で、師匠も、左手で右肘をかばいながら、飛びすさっている。
白い棒状の何かが、宙を飛び、俺と師匠に襲いかかってきたのだ。
それは、フォン・ヴァルヴァゾルの武器――骨の杭だった。
一瞬、この部屋に奴が潜んでいるのかと思ったが、その様子は無い。
どこかに置かれていた骨の杭が、独りでに、俺と師匠を狙って飛んできたのだろう。
杭の数は、四本。
俺に二本、師匠に二本だ。
杭は、奇妙な唸りを上げながら空中で方向を変え、執拗に俺と師匠を狙ってくる。
「くそがっ!」
師匠が、目の前に迫った杭を、蹴り上げた。
が、杭は、ただ空中に舞い上げられただけで、再び師匠に襲いかかる。
「師匠!」
ざくっ!
叫んだ俺の左の脇腹を、杭がかすめた。
あの強烈な痛みが、そこで弾ける。
「俺に気を取られてる場合か! この間抜け!」
師匠が、俺を怒鳴りつける。
しゃああああああ……ッ!
毒蛇の威嚇音にも似た声が、部屋に響く。
あの女の唇から発せられた音だ。
女が、鋭い歯を剥き出しにし、狂おしい飢餓感に赤い目を光らせながら、声を上げている。
どくん、と、体が疼いた。
右足と、左の肩と、脇腹――あの、骨の杭に傷付けられた箇所が、熱をもち、痛む。
まるで、女の飢えと、傷が、共鳴しているようだ。
「殺して――」
と、別の声が、響いた。
「彼女を、殺してあげてください!」
まるで、血を吐くような、叫び。
それは少年の声だった。
見ると、少年が、その目を開いている。
緑褐色の、不思議な色合いの瞳が、痛切な哀しみを湛えていた。
部屋の中央の寝台の上に転がっている、銀の籠手を取り、素早く右手に装着する。
そして俺は、少年の言葉に応えるべく、女に向かって走った。
ざあっ!
音をたてて、鮮血が舞った。
森の下草が赤色にに染まる。
「く……!」
地面に降り立ち、ミアは、声をあげた。
その黒い服の胸元が大きく裂け、白い胸元があらわになっている。
ミアの額には、大きな傷が走っていた。
溢れた血が、ミアの白い顔を赤く汚している。
「やりますね」
地面に立ったフォン・ヴァルヴァゾルが、その声に、ほとんど何の感情も込めずに、言う。
その背後に立っているのは、冬条綺羅だ。
綺羅は、ミア以上にダメージを負っている。その上、再生速度も遅い。
ノインテーターに捕らえられてからの度重なる凌辱に、体力を消耗しきっているのだ。
そんな綺羅を犯した千坂静夜も、今は、灰に還っている。
「あなた達は、本当に強い。新たに手に入れたこの杭が無ければ、二対一では戦えなかったかもしれません」
そう言うフォン・ヴァルヴァゾルは、呼吸を乱してすらいない。
その大きな両手には、杭が二本ずつ握られている。
二本の杭を、親指、人差し指、中指のそれぞれの間に構え、時に、それぞれを投擲しながら、フォン・ヴァルヴァゾルは、ミアと綺羅を翻弄し、そして確実に追い詰めていた。
脳と心臓の双方を同時に狙われ続け、ミアは、これまで有効な攻撃を行うことができていない。
もとより綺羅は防戦一方だ。
「綺羅、逃げていいわよ」
ミアは、フォン・ヴァルヴァゾルの向こう側にいる綺羅に、言った。
「あなたは疲れきっているし――いつまでも居られても、邪魔だわ」
一瞬、眉をひそめかけた綺羅が、ふっと微笑む。
「またァ、ミアちゃん、無理して強がっちゃって」
「本当のことを言っているのよ」
「そーかもしれませんけど、この人、素直にあたしを帰してくれると思います? 何が何でも三輪車希望って感じですよ」
「……下品ね、あなた」
ミアが、軽くため息をつきつつ、言う。
フォン・ヴァルヴァゾルは、二人の会話に口を挟まない。
まるで、それをきっかけにペースを乱されるのを警戒しているかのように、口をつぐんでいる。
クルスニクには、吸血鬼の暗示や幻術が、効かない。
ただ、互いの純粋な戦闘力のみが、勝敗を決するのだ。
フォン・ヴァルヴァゾルが、四本の骨の杭を構えた。
いかなる格闘技にも無い、変則的な構えである。
腕を交差し、両の拳を左右の肩に付けるような格好だ。
拳からは、それぞれ二本、骨の杭が突き出ている。
フォン・ヴァルヴァゾルは、その姿勢で、前方のミアを睨んでいた。
ミアは、両手を下げ、足を軽く開いている。
次にどのような攻撃が来ても、即座に対応できるような、自然体の構えだ。
綺羅は、やや前かがみで、フォン・ヴァルヴァゾルの広い背中を見つめている。
両手の指の先で伸びた爪が、細かく震えている。もはや限界が近いようだ。
次第に闇が満ちていく中、フォン・ヴァルヴァゾルの小さな両目が、白く光っている。
森の中の暗闇に、いささかも視覚を妨げられていない様子だ。
奇妙な静寂が、森の中にある。
命で満ちているはずのこの場所の生態系そのものが、息を潜めているような、不自然な静けさ。
大気さえも、何かをはばかるように動きを止めている。
三人は、互いの心臓の音を盗み聞こうとするかのように、感覚を研ぎ澄ましていた。
そして――
全てが、同時だった。
師匠の抑えられた呻き声。
背中に杭が突き刺さる激しい痛み。
銀の籠手を装着した右の貫手が胸郭を破る感触。
そして、高い絶叫。
きゃあああああああああああああああああ――……。
ぼっ、と熱の無い炎が女を包み、そして、その体を灰にした。
俺の背中に刺さっていた杭も、消える。
俺は、膝を付きそうになるのを耐え、振り返った。
師匠が、右腕とともに、左の腕も、だらりと下げている。どうやら骨の杭に傷付けられたらしい。
「大丈夫ですか?」
「大丈夫に見えるかよォ」
普段の口調で、師匠が言う。
そして、もう一つの磔台に、視線を移した。
少年が、師匠と、そして俺の視線を、奇妙に穏やかな顔で受け止める。
「また会ったな、坊主」
「……はい」
少年は、師匠の言葉に、静かに答えた。
そして、俺に、その緑褐色の瞳を向ける。
「あなたが、羽室鷹斗さん?」
俺は、頷いた。
少年が、まるで眩しい物を見た時のように、一瞬だけ目を細める。
ぞろりと――脳の表面を嘗められたような感触が、あった。
師匠は、黙って、俺と少年を見比べている。
「そうですか……あなたが……」
少年は、そう言って、かすかに微笑んだ。
「あなたに会えてよかった」
「?」
俺は、少年の小さな声を聞き取るために、その体に近付いた。
その無残と言うも愚かな様相に、自然と眉をしかめてしまう。
見ると、切断された四肢に巻かれた包帯に、金糸で不思議な文様が織り込まれていた。
これは、傷を癒すためではなく、吸血鬼の再生を妨げるための物なのだろう。
しかし、何のために――?
「フォン・ヴァルヴァゾルが、僕の手足の骨を、武器に使っているんです」
俺の疑問に答えるように、少年が言った。
こんな目に遭っていながら、哀しいくらいに理性的な声だ。
「もう、僕の体は元に戻りません。いつか、あの人のように、苦痛と無力感のために、気を狂わせてしまうでしょう」
「……」
「お願いです。僕を殺してください」
半ば予想していたその言葉を、少年が言った。
無意識のうちに、唇を噛んでしまう。
「鷹斗さんは、フォン・ヴァルヴァゾルと敵対しているんでしょう? 僕を滅ぼすことができれば、彼の武器を奪うことができます」
「それは……」
「僕は、自らの命を断つことすらできない。舌を噛んでも、頭をこの十字架に打ち付けても、痛みを感じながら、緩やかに傷を再生してしまうだけなんです」
「……」
「僕を、殺してください」
俺は、銀の籠手を嵌めた右手を、ぎゅっと握り締めた。
俺の貫手は、造作も無く、この少年の胸を貫き、心臓を停止させるだろう。
そして、俺は、これまで何人もの吸血鬼をそのようにして斃してきた。
人を殺したことも、ある。
今更、血を見るのを惧れているんだとしたら、そのこと自体、嗤うべき欺瞞だ。
「もう、疲れました……。僕は、ここで滅びるべきなんです」
「……」
「僕を救ってくれませんか?」
「……駄目だ」
俺は、震える声で、言った。
「相手を救うために殺すことは、俺にはできない。俺は……それは、間違いだと思う」
「僕がそれを望んでいても?」
「……そうだ」
きりきりと歯を食いしばりながら、俺が呻くように言う。
少年は、その少女のような顔に困ったような笑みを浮かべ、溜息をついた。
そんな表情が、何故か――ミアを連想させる。
背中に師匠の強い視線を感じながら、俺は、その場に立ち尽くしていた。
「あなたには、暗示も通じないみたいですね」
「らしいな」
「――夕子さんと同じだ」
少年が、両目を次第に朱に染めながら、言った。
「なに……?」
どくん――。
心臓が、跳ねる。
少年は、その唇を、三日月型に歪めた。
尖った歯の先端が、口元から覗く。
「自己紹介が遅れましたね。――僕の名は、アラン・ラクロワ」
「おい……!」
師匠が、少年の言葉を遮ろうとする。
が、それは間に合わなかった。
「矢神夕子さんを吸血鬼にしたのは、僕です」
「ふっ!」
短い気合とともに、フォン・ヴァルヴァゾルが、反時計回りに振り向き、背後の綺羅に骨の杭を投じる。
左手に握っていた二本の杭だ。
自分に背中を向けたフォン・ヴァルヴァゾルに、ミアが、右手で銀の糸を放つ。
フォン・ヴァルヴァゾルが、助走無しで地面を蹴った。
その肥満した巨体が斜め前方に宙を飛び、木の幹に両足を付く。
そして、フォン・ヴァルヴァゾルは、さらに上方に飛んだ。
「くうっ――!」
ミアは、左手の糸を繰り出し、空中にいるフォン・ヴァルヴァゾルを捕捉しようとした。
夜気を切り裂き、銀の錘に導かれた五本の糸が、疾走する。
それらが、すでに落下の態勢に入ってるフォン・ヴァルヴァゾルを包み込もうとした。
全ての糸を同時に逃れる術は――無い。
フォン・ヴァルヴァゾルは、両手にそれぞれ一本ずつ、杭を握っていた。一本を、宙で左手に持ち替えたのだ。
その二本の杭で、フォン・ヴァルヴァゾルは、目の前を薙ぎ払った。
連続する澄んだ軽い音に、勝利を確信しかけていたミアの目が、見開かれる。
フォン・ヴァルヴァゾルによって弾かれた二つの銀の錘が、それぞれ一つずつ別の錘を弾き、軌道を変えたのだ。
もはや、フォン・ヴァルヴァゾルを捕らえるはずだった糸の檻は、完全に形を崩している。
残った一本の糸で、フォン・ヴァルヴァゾルの攻撃を防ぐことは、不可能だ。
迫る二本の生白い杭を真紅の瞳に写し、ミアは、死を覚悟した。
俺は――
俺は、目を見開いていた。
伸ばされた俺の指が、少年の――アランの胸に、ずぶりと突き刺さっている。
その光景を見て、俺は、それを、間違いなく自分の意志で行ったのだということに気付いていた。
華奢な少年の体を犯す、銀の指。
それは、俺の激怒であり、憎悪であり――そして嫉妬だった。
俺は、そんな感情に衝き動かされるまま、右手を突き出してしまったのだ。
アランの心臓を貫いた激情が、未だに、俺の全身を震わせている。
もし、まだ俺の体が動いていなかったら、間違いなく、改めて俺はアランの薄い胸に貫手を突き立てていただろう。
しかし、それでも俺は――
「ありがとう……鷹斗さん……」
熱の無い炎に包まれながら、アランが言った。
その顔には、あの穏やかな笑みが戻っている。
夕子も、少年の、この優しげな笑顔を見たのだろうか。
「これで……いいんです……なにもかも……」
なんだと?
いいはずがない。
こんなことが、許されていいわけがない。
俺は、また、取り返しのつかないことを――
「夕子さんは……」
そう、言いかけて――アランは、灰になった。
だらりと、俺の右腕が下がる。
アランの心臓の感触は、俺の右手に、いつまでも残っていた。
どん、というショックがあった。
フォン・ヴァルヴァゾルの拳が、ミアの胸を叩いている。
が、それ以上の衝撃は、無かった。
杭が、消えていた。いや、灰に還ったのだ。
「くっ!」
「……っ!」
まず、フォン・ヴァルヴァゾルが反応し、大きく飛びすさる。
それを、ミアの銀の糸が、追った。
両手に五本ずつ、十本の糸。
その攻撃を避けながら、フォン・ヴァルヴァゾルが、懐に右手を差し込もうとする。
ざん!
血飛沫が、闇の中で舞った。
悲鳴は聞こえない。
――どす、と意外なほど重い音をたてて、太い右腕が地面に落ちた。
肘の部分で切断された、フォン・ヴァルヴァゾルの腕だ。
フォン・ヴァルヴァゾルの巨体は、木々の間の闇の中に、姿を消している。
気配の名残すら、察知することができない。
「片腕一本、わざと犠牲にするつもりだったのね……。鮮やかなものだわ」
ミアが、小さく溜息をつき、そして綺羅のいた方向に視線を投じる。
地面に、黒い影が横たわっていた。
影が薄い煙をあげて、傷ついた人型の紙片となる。
その向こうに、口元から血を流しながら、綺羅が立っていた。
「あなた、それ、お腹の中で飼ってたんじゃないでしょうね?」
身代わりの式神となった呪符を指差しながら、ミアが言った。
綺羅が、口からあの式神を吐き出し、骨の杭に対する盾としたのを、ミアは視界の端で捉えていたのだ。
「まひゃか」
綺羅が、はっきりしない口調で言った。
「舌の裏に、おフダを縫ひつけておいたんれひゅよ。まさに切り札ってやつれひゅねー」
言ってから、綺羅は、ごほごほと咳き込んだ。口の中の血が喉に入ってしまったらしい。
「追いかけなくて、いーんれひゅか?」
「無駄よ。もう血の匂いもしないし……。よっぽど素早く止血したようね」
そう言いながら、ミアが、綺羅の体を支えてやる。
「右腕を奪えただけでも上出来だわ。あなたも、もう休んだ方がいいわよ」
「……ありがとーございまひゅ」
ようやくそれだけ言って、綺羅は、がっくりとその体を弛緩させた。
がこん、という音が、床から響いた。排水口のある場所だ。
見ると、格子状の蓋が、下から押し上げられている。
「どもー。鷹斗ちゃん、お元気?」
一メートル四方ほどの穴から頭を出したのは、萌木氏だった。頑丈そうなラップトップのパソコンを肩にかけ、頭にはヘッドライトを付けている。
「しばらくぶりだな」
師匠が、皮肉げな口調で言った。
「あ、こりゃどーもご無沙汰してます。修三師匠もお変わりなく?」
「……火事は、お前さんの仕業だな?」
「半分は本物、半分は発煙筒ですけどねー」
「本当に燃やしたところもあったのか。意外と豪気な奴だな」
「いい嘘をつくには、半分は本当のことを言わなくちゃいけませんから。この施設の人達とセキュリティの両方を騙すには仕方なかったんですよ」
そう言って、萌木氏が俺に視線を移す。
「顔色悪いみたいだねー。だいじょぶ?」
「はい。……ありがとうございます」
「OK。んじゃ、脱出と行きましょーか。師匠はどうします?」
「こんな状況でここに残るメリットは何もねえな。一緒にずらからせてもらうさ」
「はいはい。手間賃はいただきませんよ」
「こっちが迷惑料を取りてえくらいだ。人の信用ガタ落ちにしやがって」
そんなことを言いながら、師匠と、そして俺は、萌木氏に案内されるまま下水道の中に入った。
「しかし、えらくいいタイミングだったじゃねえか」
暗く狭い下水道を辿りながら、師匠が萌木氏に言った。
「何のことスか?」
「あのけたくそ悪ィ部屋に俺達をご案内したのはお前さんだろ? 鍵まで開けてよォ。なのに、切った張ったが収まるまで顔出さなかったな?」
「いろいろ、脱出の手筈を整えてたんすけどねー」
「ま、お前さんが出て来たって何の足しにもならなかったと思うけどな」
「――そーいう事ですよ」
萌木氏が、少し間を置いてから、言った。
「出来る人が出来る範囲で出来ることをするしかないですからな、世の中は」
ちら、と萌木氏が、俺の方を振り向いた。
「悟ったようなこと言ってンじゃねえよ」
師匠が、言う。
俺は、あのアランという少年のことを考えるのを一時中断し、きちんと前を見た。
まだ何も終わってはいない。
まずは、ここを出なくては。
下水の出口らしき明かりは、未だ、見えなかった。