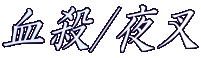
第六章
![]()
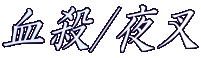
第六章
少女は、驚愕していた。
廊下に立ちすくみ、赤い目を見開く。
その視線の先で、最後まで残っていた三人の仲間が、一瞬にして切り刻まれ、灰に還っていた。
熱の無い炎の向こうから、少女よりもなお幼い影が、姿を現す。
自らの支配者から、話にだけは聞いたことがある。“カインの花嫁”だ。
やや癖のある漆黒の髪。幼い、しかし貴族的な容貌。真紅の瞳。
銀色の腕輪から、髪の毛よりもさらに細い何本もの糸が、優美な曲線を描いて垂れ下がっている。
白銀の髪をしたこの学園の支配者が求める、二千年紀の時を超えてきた吸血鬼。
その“花嫁”が、学園の吸血鬼たちを虐殺した。
まるで人形を壊すよりも呆気なく、銀の糸を縦横に繰り出し、学園の制服を着たヴァンピールたちを寸断していったのだ。
学園の生徒たちのうち、ヴァンピールとして新たな生を与えられたのは、約三十人。全校生徒の一割以上に及ぶ。
そして、教員のうち半数にあたる十人もまた、ヴァンピールであった。
総勢四十名に及ぶ吸血鬼たち。その大半が、“花嫁”一人によって斃され、灰と化してしまった。
当初、彼女達は、自分たちの支配者であるノインテーターの意に添うべく、“花嫁”を捕獲しようとしていた。
が、最初の十人をいとも簡単に滅ぼされ、ヴァンピール達は、認識を改めた。
“花嫁”は、この学園の吸血鬼たちを皆殺しにするためにやって来たのだ。
残りのヴァンピール達は、次々と破壊されていく仲間たちの血を浴びながら、“花嫁”の体に鋭い爪を伸ばし、その心臓を停止させようと試みた。
が、結局は、あらゆる攻撃が無意味だった。
宙を疾走する何重もの糸の結界をくぐり抜け、“花嫁”に肉薄しても、最後には、“花嫁”自身の爪によって、この世ならぬ鼓動を刻む心臓を抉られるのだ。
“花嫁”に返り血を浴びせることのできたヴァンピールは、わずかに三体であった。
その血も、本体が灰に還ると同時に、薄い煙をあげて消えていく。
血に塗れた廊下は数分後には普段の様子を取り戻し、そこを、“花嫁”は歩調を変えることなく歩いていた。
半時間に満たない一方的な殺戮の後、今、この場所で生き残っている吸血鬼は、彼女と、彼女に歩み寄る“花嫁”のみだ。
いや、“花嫁”が、自分とは全く異なるモノであることに、ようやく少女は気付いていた。
吸血鬼でありながら、さらにその上位に存在するモノ。
少女は、目に涙を滲ませながら、“花嫁”を見ていた。
これまでの日々が、脳裏に現れては、消えていく。
未だ人間のままでいる級友達を暗示で操り、その心を弄んでいた、歪んだ悦楽の毎日。
ノインテーターの精を浴び、哀れな獲物の血を絞り取っていた、昏い淫獄の夜。
親友とともに、夜を歩くものとなった背徳の幸せを確かめ合った、あの日の夕暮れ。
いつまでも続くと思われた、腐りかけの果実のように甘い時間が、今は、海の上の幻のように遠い。
死にたくない――と、少女は、思った。
不覚にも、この瞬間まで、生と死について深く考えることがなかったが、それでも、少女は死にたくないと思った。
もはや、ノインテーターの支配や、千坂静夜の命令すら、少女にとっては些事に過ぎない。
少女は、死を恐れた。
自らの体に爪を立てたくなるような焦燥感に襲われながら、“花嫁”の隙を探る。
逆襲するつもりなど毛頭なかった。ただ、逃げることさえできればよかったのだ。
“カインの花嫁”は、無言のまま、歩を進めている。
少女は、そんな“花嫁”の隙を見つけられぬまま、絶望的な思いで、走り出した。
目をつぶり、“花嫁”の横を擦り抜けようとする。
がくん――。
軽いショックの後に、奇妙な落下感があった。
そして、鈍く重い衝撃があり、上下感覚が混乱する。
「あれ……?」
少女は、幼い声をあげ、目を開いた。
ぼやけた視界の中、垂直に傾いた廊下を、制服を着た影が、こちらに背中を向けた状態で、ぎくしゃくと走っている。
その体には、首から上がなかった。
「うそ……」
そう、つぶやこうとしたが、もはや喉は奇妙な音を立てるのみだ。
頭のない体が、つんのめるように倒れかけ、そのまま、血飛沫をあげていくつかの肉片と化した。
今、灰に還っているのが自分の体なのだということを理解しかけた少女の視界を、朱色の炎が覆う。
少女は、無へと還元された。
自分に向かって来た最後の吸血鬼を仕留め、ミアは、周囲を見回した。
ここまでミアを導いた“木霊”の呪符は、戦闘の最中に見失ってしまった。
周りに、人影は見えない。学園は正午前の授業中だったのだが、まだ人間だった生徒たちは、みな、校外に逃れてしまったようだ。
警察の介入があるかもしれない。あまり時間はなかった。
と、かすかなすすり泣きを聞いて、ミアはすぐそばの教室を覗き込んだ。
「……」
二人の女生徒が、教室の片隅で互いに抱き合い、がたがたと震えている。
どうやら、腰を抜かして逃げ損ねたらしい。強烈なショックによって暗示が解け、そのまま廊下から響くヴァンピールたちの絶叫を聞き続けていたのだろう。
ミアは、無表情のまま、その少女達の心を読み取った。二人の記憶の中にある学園の見取り図の中で、怪しそうな場所をピックアップするためだ。
大量の吸血鬼が短時間のうちに消滅したため、次元の位相が乱れている。綺羅や、まだ残っているかもしれない敵の気配を探るには、あまりいい条件ではない。
ミアは、彼女たちの記憶の中から、級友の一人が出入りしていた地下の部屋に、あたりをつけた。
その級友とは、ミアが、先ほど、一番最後に滅ぼしたヴァンピールだった。
「騒がせてごめんなさい。余裕があったら、あなたたちの記憶をいじってあげてもよかったんだけど、時間がないの」
そう、ミアは言って、体を翻した。
地下に降りる階段を見つけ、そこを下る。
暗い廊下に出た。
左右にある幾つかのドアのうち一つに、目をやる。
ドアの奥は、もともとは倉庫だったのだろうが、今は、全く別の目的に使われているようだ。
警戒しながらミアが近付くと、いきなり、ドアが鋭い破壊音をたてて吹き飛んだ。
「っ!」
一瞬後、全裸の千坂静夜が、ミアの目の前に現れる。
妊婦のように腹部が膨らみ、股間からは男根の生えたその姿に、ミアは、かすかに眉を寄せる。
一方、静夜は、驚愕の表情だ。
「そんな所に隠れてるなんて……つくづく生き意地の汚い男ね」
静夜本人を無視するように、ミアが言う。
と、ドアを失った地下室の入り口から、冬条綺羅が現れた。
綺羅は、全身に負った傷を再生しきれないでいる。かなり消耗しているのだろう。
それでも、綺羅の瞳は、赤く燃えるように光っていた。
三人の吸血鬼が、狭い廊下で、互いに視線を交わす。
「上の連中は片付けたわよ」
ミアは、冷たく乾いた声で言った。
静夜が、きりきりと歯を食いしばる。
「助太刀は、結構ですよ。こんにゃろは、あたしが仕留めます」
綺羅が、喘ぎながら言った。
「あなたの意地になんか興味ないわ。あたし、時間がないの」
そう言って、ミアは、銀の糸の先端にある涙滴型の錘を、次々に床に落とした。
きぃん、きぃん、と澄んだ音が、響く。
「……」
静夜が、無言で周囲に目をやる。
逃げ場は、無い。
ミアと綺羅が、わずかに腰を落とし、攻撃の態勢に移る。
静夜は、大きく右手を振った。
ばこっ!
鈍い音を立てて、天井が崩れ落ちた。
「なっ!」
「くっ!」
驚きの声をあげるミアと綺羅の視界を、崩落したコンクリートと、一瞬のうちにたちこめた埃が、塞ぐ。
「まったくもーっ!」
綺羅が、崩れかかる瓦礫の小山に登り、上を見た。
ぽっかりと開いた、歪んだ円形の大きな穴が、一階にまで続いている。
綺羅が、垂直に跳躍し、一階に上がった。
ミアが、それに続く。
静夜の姿は、消えていた。
「追いましょう!」
綺羅が、ミアに振り返って、言った。
「いいけど、あなた裸じゃない」
ミアが、綺羅に冷たく言う。
「そんなこと構いません!」
「あたしが構うのよ。並んで走ってて恥ずかしいでしょう。それに、ちょっとは休んだ方がいいわよ」
言いながら、ミアは、手近な教室を覗き、無造作にロッカーを開けた。
そして、臙脂色のジャージを見つけ、綺羅に放り投げる。
「こんなの着ろって言うんですか?」
「贅沢言わないでよ。さ、早くして」
「……胸がきっついです」
素早くジャージを着込んだ綺羅が、かすかに苦笑しながら言う。
「知ったことじゃ無いわ」
言って、ミアは、静夜の気配を追って走りだした。
学園の外は、位相の乱れもそれほどではない。静夜のような存在が発する次元の歪みを追跡するのは、不可能ではないはずだ。
雲間から差し込む陽光に影を落とす事なく、ミアと綺羅は、学園の裏庭を横切り、敷地に隣接する森の中へと入っていった。
俺は、部屋の中で、じっと時間を過ごしていた。
脱出に使えそうなダクトの類いなどは、見つからない。
昼食は、ドアの下にある開口部から差し入れられたのだが、その時も、相手の腕を捕まえるような隙は無かった。
ただ、無為に時間が過ぎて行く。
胸の中に、焦燥感と、それ以外の感情があった。
まるで黒く渦を巻く煙のような、正体不明の不快感。
それは、ミアに対する――いや、これまでの自分自身に対する疑惑だったのかもしれない。
腕時計の針が午後五時を大きく回った頃、突然、部屋のドアが開いた。
巨大な影が、入り口のほとんどを塞いでいる。
「……師匠」
「よお」
普段どおりの口調でそう言う師匠の表情は、逆光でよく見えない。
「男爵から、あの“花嫁”の話を聞いたらしいな」
「“男爵”?」
「フォン・ヴァルヴァゾルのことさ」
「……」
俺は、ベッド兼用のベンチから立ち上がり、師匠と対峙した。
目が慣れると、師匠が、まるで同情でもするような顔で、俺を見ているのが分かった。
「師匠は……」
無意識のうちに、言葉が、口から出ていた。
「ん?」
「師匠は、俺を、どうするつもりなんですか?」
「そうさなあ……」
のんびりとした口調で言い、師匠が、部屋の中に入ってきた。
その大きな口が、淡い笑みを浮かべている。
しかし――師匠の目は、少しも笑ってなかった。
「!」
反射的に、身を引く。
が、師匠は、右手を下から伸ばし、難無く俺のベルトを掴んでいた。
そのまま、凄まじい勢いで、俺の体を力任せに投げる。
どっ! と右の肩から、落ちた。
いや、落ちたというより、壁に叩きつけられたのだ。
「俺がお前さんをどうするかなんて、訊いてる場合じゃねえだろ?」
激痛に声が漏れそうになっている俺に、師匠が言った。
「お前がどうしたいか。それをすることができるのか。それだけだろうが……!」
立ち上がりかける俺の頭部目がけ、師匠が容赦なく蹴りを放つ。
俺は、前方に転がり、その蹴りをかいくぐった。
師匠の丸太のような足が、俺の体をかすめる。
開きっぱなしになっているドアから廊下に出た。
そして、やはり廊下に出てきた師匠と、対峙する。
右腕が動かない。どうやら、脱臼か何かしたらしい。
「……お前さんは、間抜けな部外者である俺の隙をついて、ここから脱出した」
師匠が、歯を剥き出しにして笑いながら、言う。
「今、男爵の野郎はお出掛け中だ。事態に気付き、銃をもった警備員がここに駆けつけるまで、長く見積もっても三分」
俺は、左手で右肩を押さえながら、師匠の言葉を聞いた。
「三分で俺を倒せれば、お前の勝ちだ。ここまで分かり易くしてやんなきゃ駄目か?」
「――」
俺は、肯いたり、返事をしたり、頭を下げたりする代わりに――ごきん、と自分の右肩を、嵌めた。
それを合図に、師匠が床を蹴る。
俺は、左腕と両足のみで、どうにか師匠の攻撃をさばいた。
右腕は、まだきちんと動かない。そう何回も使えはしないだろう。
それでも、どうにか、師匠の攻撃を受け止め、受け流す。
「しっ!」
師匠の暴風のようなラッシュが緩んだ隙に、跳躍した。
壁に足を付き、空手で言う三角飛びの要領で、飛び蹴りを放つ。葛木流では“山彦”と呼ばれる技だ。
が、師匠は、俺と反対側の壁を、俺より高く登っていた。
鉞 のように振り下ろされる師匠の蹴りを、空中で身をひねり、かわす。
そして、一足先に着地した俺は、くるりと身を翻し、師匠に左手の裏拳を放った。
師匠が、インパクトの一瞬前に、腕で頭部をガードする。
俺は、弾かれたように飛びすさり、再び距離を取って対峙した。
「ふふん」
師匠が、笑みの形を微妙に変える。
食事の前に虎や熊が笑ったらこうなるんじゃないかと思うような、そんな笑みだ。
俺は、乱れた呼吸を整える。
フォン・ヴァルヴァゾルにやられた右足と左肩の傷が、また熱をもってきた。もし、奴の言っていたことが本当なら、血液の循環を激しくしたことで、消滅しかけていた“骨片”に血を与えてしまったのかもしれない。
それが、俺の体にどんな影響を与えるかは、無論、不明だ。
そんなことよりも、今は、目の前の師匠を倒すことに集中しなくてはならない。
そう――倒すしか、ない。
ぶん、と唸りを上げて、師匠の左のローキックが、俺の右膝を破壊しようと迫る。
が、俺は、それを事前に察知できていた。
下がる代わりに、熱く疼く右足を振り上げ、師匠の顎を狙って垂直に蹴りを放つ。
師匠が首を右に振ってそれをかわした。
その逃げた師匠の顎を、さらに俺の左の爪先が真下から狙う。
俺は、後方宙返りの体勢だ。
師匠が、大きく身を捻って、俺の左右の蹴り足から逃れた。
俺が、床に着地する。
「“比翼”か……。なかなか、楽しめる男になった」
師匠が、目を輝かせた。
「けど、惜しいな。時間切れだぜ」
ちら、と腕時計に目をやって師匠が言った。
「今日はここまでだ。俺は、お前をぶちのめしてまたあの牢屋に入れる。あとの機会は自分で探しな」
――そう言われ、はいそうですかと返事ができる訳がない。
師匠のわずかな隙も見逃すまいと、全神経を集中する。
そんな俺に、師匠が、大きく踏み込んで再び左のローキックを放った。
それをカットする俺に、左右の拳が襲い来る。
まるで詰め将棋のように、俺の逃げ場を奪っていく師匠の連続攻撃。
避けたつもりでも、かすめただけで体勢が崩れ、ガードしてもその箇所が痺れる。
そして、大きくよろけた俺の顔面に、師匠が右の拳を放った。
葛城流も何もない。その膂力と体重を完全に乗せきった、感動すら覚えるような右ストレートだ。
俺は、体を右に倒すような形で、どうにか顔面にそれが当たるのを回避した。
拳が、左の頬をかすめる。
頬が大きく裂け、鮮血が舞った。
師匠の、次の一手を、俺は避けられない。
が、その攻撃が来る前に、俺は、左腕を師匠の右腕に絡めていた。
クロスカウンターに似た形だが、俺の目的は、頭部と左腕で師匠の右肘の関節をロックすることにある。
「ぬっ!」
師匠の驚きの声を聞きながら、右腕も使い、完全に師匠の右腕を捕らえた。
その時には、俺は、両足で師匠の右足を刈っている。
そのまま、もつれ合うようにして、俺と師匠が倒れた。
風景が反転する。
そして、ごぎっ! という鈍い感触を、両腕で感じた。
「うお……っ!」
師匠が、うめき声を上げる。
俺と師匠の二人分の体重を集中し、師匠の右肘の関節を破壊したのだ。
完全に、折れたはずである。
“八雷 ”のうち、“土雷 ”。
“八雷”とは、倒れ様に、その勢いと二人分の体重で相手の体を破壊する技の総称だ。
本来なら、“土雷”は、互いに組んだ状態から入る技である。そこから、相手の腕を取り、捻りながら極め、そしてその時には足を刈っている、という流れだ。
今、俺がやった“土雷”は、流れの中で強引に完成させたものだ。師匠にとっては、半ば以上、不意討ちだったに違いない。
俺は、師匠から離れ、立ち上がった。
師匠も、立ち上がる。
その右腕が、肘のところで、通常とは逆方向に曲がっていた。
「や……やりやがったなァ……」
師匠が、歯を剥き出しにして言う。
ようやく、五分といったところだろうか。
師匠の言葉どおり、そろそろ、この施設の連中がここに来るだろう。恐らくそいつらは銃器で武装している。
だが、銃を持った数人の男たちよりも、まだ、今の師匠の方が障害としては大きいはずだ。
ここで、完全に決着を付けなくてはならない。
改めてそう思った時――建物中に、火災報知器のサイレンが鳴った。
静夜は、暗くなりかけた森を全裸で走っていた。
あれから、六時間近くが過ぎている。
まだ、あの学園での惨状が、頭から離れない。
吸血鬼は、滅びる時に灰となり、そしてその灰もいつのまにか消えてしまう。
校舎に、四十人にも及ぶヴァンピールが存在したという痕跡は、微塵も残っていなかった。
それでも、静夜は、半時間のうちに殲滅させられたヴァンピールたちの断末魔の名残を、次元の歪みとして知覚していた。
一滴の血すらも残っていない廊下が、静夜には、酸鼻を極めた光景に感じられた。
それが、あの“カインの花嫁”一人の仕業であることに戦慄を覚えながら、静夜は、森の中を逃げた。
“花嫁”と綺羅の二人を同時に相手にすることなど、できるわけがない。
せめて、自分の胎内に潜むノインテーターの一人でもこの次元に帰還するまで、逃げ続けなくてはならなかった。
“花嫁”と綺羅は、自分を追ってきているだろう。
だが、この森にいる限り、地の利は自分にある。
あの二人の強烈な気配は、まだ、自分に近付いてきてはいない。逃げおおせることは充分に可能なはずだ。
と、静夜は、足を止めた。
かすかに、ヴァンピールらしき気配を感じたのだ。
“花嫁”や綺羅のそれではない。もっと弱い、そして無個性な次元波動だ。
――あの虐殺から逃れた、学園の生徒かもしれない。
そんな希望的観測が、静夜の反応を致命的に遅らせてしまった。
どん!
銃声より先に、衝撃が来た。
「くっ!」
右肩を撃ち抜かれ、静夜は、地面に倒れた。
キュゥー……ン、という高い音が、遥か遠くから響く。
ライフルの発射音だ。
「ぐうっ……!」
弾丸は、銀だ。それが傷口に残っている限り、傷口は再生しない。
静夜は、歯を食いしばりながら、自らの銃創を爪で切り裂き、銀の弾丸を抉り出した。
次第に闇が深まる森の中で、目を凝らし、耳を澄ます。
間違いなく、自分を狙撃したのは人間だ。吸血鬼の気配ばかりに気を取られていたために、不覚を取ってしまった。
五感に意識を集中し、生きた人間の発する音や匂いを探る。
包囲されていた。
人数は――六人。
ハンターに間違いない。恐らくは第八機密機関の連中だろう。
静夜は、地面に腹這いになったまま、数秒間、目を閉じた。
そして、ゆっくりと目を開く。
その瞳が、深い赤色に光っている。
狩られるモノであっては、その先にあるのは死でしかない。
狩るモノにならなくては――
と、鋭い表情を浮かべていた静夜の頬が、一瞬、緩んだ。
厳しいが、生徒の良き相談相手として教壇に立っていた頃の面影が、思いがけなく、その美貌に甦る。
それは、安堵の表情だったのかもしれない。
「ノインテーター様……」
闇の中に――いや、この世界に隣接する次元の狭間にわだかまる一対の赤い瞳に、静夜は語りかけた。
「――行きます」
別れの言葉も、まして想いの告白も、今は無意味。
静夜は、しなやかな雪豹のように、四つん這いの姿勢になった。
膨らんでいたその腹部が、元に戻っている。
そして、静夜は、奇妙な笑みを浮かべながら、木々の間へと跳躍した。
銃声が、五つ。
そして、森の中の離れた場所で、五人の男たちが、次々とずたずたに引き裂かれ、その鮮血を空しく地面に吸わせた。
「聞きました?」
「ええ」
綺羅の問いかけに、ミアが答えた。
なおも深まる夕闇の中、二人は、足音すら立てずに走っている。
綺羅が言ったのは、ライフルのものらしき鋭い銃声のことだ。
散発的に何度か銃声が響き、そして、今は静寂が戻っている。
「……!」
二人は、まだ新しい無残な死体を発見し、足を止めた。
迷彩服をまとった体。ライフルを握った両手。ブーツを履いた脚。そして、暗視ゴーグルらしきものを装着した頭部。
それらが、まるで子供の八つ当たりにあった人形のように、あちこちに散らばっている。
「第八機密機関の兵士ね」
ミアが、つぶやいた。
「これ、あんにゃろの仕業ですねー。まったく、こんなに散らかして、お行儀が悪い」
鮮やかすぎる切断面を見て、顔をしかめながら、綺羅が言う。
ミアは、目を閉じ、意識を集中した。
静夜のものらしき気配が、近い。
「誰かと、戦っているようね」
「分かるんですか?」
ミアほど吸血鬼の気配を読むことに慣れていない綺羅が、訊く。
「ええ。あなたも、百年もすればいやでも感じられるようになるわ」
「……決着がつくまで、待ちます?」
「ずるい女ね、あなたって」
ミアは、そう言ってから、しばし考え、言葉を続けた。
「行きましょう。どちらが勝つにしても、その相手とは戦わなくてはならないんだから、戦っているところを見ておいた方がいいわ」
「……ミアちゃんだって、そーとーずるっこいと思いますよ」
そして、二人の吸血鬼は、再び森の中を走りだした。
暗い緑色の風景の中で、ねっとりとまとわりつく、ぬるい空気。
それを、耳で捕らえられないほど鋭い音が、引き裂いた。
ミアと綺羅が、ほぼ同時に立ち止まった。
目の前で、一抱え以上はありそうな杉の木が、磨かれたように滑らかな断面を見せながら、音をたてて倒れる。
そして――開けた視界の先に、灰色のコートをまとった巨漢が、こちらに背中を向けて立っていた。
真っすぐに伸ばされた右手が握る白い杭が、全裸の若い女の豊かな乳房の間を、正確に貫いている。
女が静夜であることを綺羅が認めた時、熱の無い炎が、その体を一瞬のうちに包んだ。
灰が、わずかな風に舞い散り、そして消える。
巨漢が、振り向いた。
濃褐色の髪と、同じ色の髭が、その顔の造作を隠している。
宵闇の中で、小さな目が、一瞬、生白い光を放った。
「ようやく会うことができましたね、“カインの花嫁”――」
穏やかな声で、クルスニクの“男爵”オスカー・フォン・ヴァルヴァゾルが、言った。