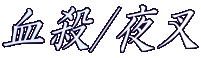
第五章
![]()
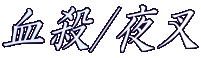
第五章
激しい雨が、俺の全身を叩き、ずぶ濡れにする。
雨水に足を取られないようにしながら、ワゴンの屋根を後方へと移動した。
軍用車に乗っているのは、運転者一人のようだ。
闇の中、ヘッドライトの光芒に切り取られた風景が、すごい勢いで溶け流れている。
が、車同士の相対速度は、大したことはない。
軍用車が、迫る。
俺は、屋根の上で腰を浮かした。
大気が、俺の背中を押す。
それに逆らわず、俺は、軍用車のボンネット目がけ跳躍した。
一瞬の、無重力――
だん!
俺は、軍用車の広いボンネットの、やや向かって右寄りに飛び付いた。
ぎゅいいいいいいっ!
何かに慌てたようなブレーキ音とともに、軍用車の車体が振れる。
そのまま、車体がぐねぐねと蛇行した。
両足の、膝から先が、外側にはみ出る。
「くっ……!」
さすがに、声を漏らしてしまう。
そのまま振り落とされそうになりながら、俺は、ボンネットとフロントガラスの間の隙間に、左手の指を突っ込んだ。
ぐるりと体を半回転させ、ボンネットの上に仰向けになる。
さらに半回転し、俯せの態勢を取ろうとした時だった。
ぎゅわっ!
急ブレーキに、前方に投げ出された。
雨に濡れた左手の指が、ずるっ、と外れる。
闇の中、恐らく時速100キロ以上で、宙を舞いそうになる。
このまま路面に叩き付けられればそれで一巻の終わりだ。
夢中で手を伸ばし、右手でバンパーを掴んだ。
膝を曲げ、足を縮めて、足が路面をこすらないように注意しながら、バンパーにしがみつく。
太い金属製のパイプで構成されたバンパーだ。これまで何度も萌木氏のワゴンに激突したはずなのに、ほとんど形が歪んでいない。
その頑丈さに、今だけ、感謝した。
両手両足を使って、軍用車のバンパーによじ登る。
そして、ブレーキをかけられる前に、四つん這いの態勢を整えた。
このまま、フロントガラスを叩いたって、何の意味もないだろう。
狙うのは、ワイパーだ。
右手で、フロントガラスの上部を支点にして忙しく動いているワイパーを掴み――折る。
ざああっ! とフロントガラスを叩く雨滴が、運転者の視界の半分を奪った。
ぐうん、と軍用車が減速する。
構わず、残ったもう一本のワイパーも、折った。
これで、もう視界はゼロのはずだ。
前を走っていた萌木氏のワゴンとの距離が、みるみる開いていく。
さて、どうやって合流するか……。
そう思った時、いきなり、軍用車が道を外れた。
縁石を越え、林の中に入り、垂直に近い急斜面を下っていく。
張り出した枝が、俺の体を容赦なく叩いた。
車体が、大きく上下に揺れる。
「ちっ!」
俺は、投げ出されないよう、車の屋根を越え、向こう側の荷台に逃れた。
軍用車は、斜面をすさまじい勢いで下る。
よほど悪路に強いのだろう。とても普通の車が通れないような場所を走りながらも、軍用車は進み続ける。
完全に、道から外れてしまった。
次第に斜面がなだらかになり、木の密度が上がってくる。
と、やや開けた場所に、車が出た。
谷間とは言うほどでもない、ちょっとした窪地のような場所。
そこで、ようやく軍用車は止まった。
「ふぅ……」
思わず、安堵の吐息をついてしまう。
その時、運転席側のドアが、開いた。
雨の中、灰色のコートをまとった巨漢が、その姿を現す。
身長は一八〇ほどだろうか。かなり肥満している。長く伸びた髪と髭で、表情は分からない。
「フォン・ヴァルヴァゾルといいます」
荷台の上に立ち上がった俺に顔を向け、流暢な日本語でその男は言った。
フォン・ヴァルヴァゾル――名前だけは、ミアや萌木氏に聞いたことがある。第八機密機関の腕利きハンターだ。
「……羽室鷹斗さんですね?」
「……」
俺は、無言でフォン・ヴァルヴァゾルという男を見た。
こちらの方が、高い場所にいる。一般的には有利な位置だ。
が、相手の手の内を知らない以上、油断は禁物だった。
何しろ、この男がどのような戦い方をするのか、ミアや萌木氏でも知らなかったのだ。
「葛木修三さんは、こちら側にいます」
「こちら側?」
「我々に協力をいただいているということです」
「……」
「あなたには、色々とお話したいことがあるのですが」
丁寧な口調でそう言うフォン・ヴァルヴァゾルからは、いかなる敵意も感じられない。
それでいながら、俺の本能は、この目の前の男がとてつもなく危険な存在だと告げていた。
何しろこの男は、車に取り付いた俺を殺すつもりだったのだ。
それが、なぜ、今になって俺を説得をするようなまねをしているのか、その意図が分からない。
「このまま、おとなしく車に乗っていただけませんか?」
「……断る」
「そう言われると思っていました」
短く、フォン・ヴァルヴァゾルが嘆息した。
「不本意ながら、実力行使という事になりますね」
そして――何の予備動作もなく、フォン・ヴァルヴァゾルが右腕を一閃させた。
ゆったりとしたコートの袖から、白い何かが飛び出る。
俺の足を狙ってきたそれを、高く跳躍してかわした。
そのまま、フォン・ヴァルヴァゾルの頭部を狙い、蹴りを放つ。
右足による蹴りが、弾かれた。
「くううっ!」
激しい痛みにうめきながら、俺は、地面へと降り立った。
右足のすねが、ずきずきと痛む。
傷は、浅い。出血も大したことはないはずだ。
だが、まるでその部分に何かが突き刺さったままでいるような痛みが、右足を痺れさせる。
フォン・ヴァルヴァゾルは、左手に、先ほど投擲したものと同じ物を握っていた。それで、俺の蹴りを弾いたのだ。
奇妙に白い、先端の尖った棒状の武器。
杭、と言えばいいのだろうか。
それが、雨に打たれ、音にならない音を発しているように思える。
その、可聴領域から外れた不快な音波に、右足の傷が共鳴しているようだ。
「まだ立っていられるのですか。さすがは、葛城さんのお弟子ですね」
言いながら、フォン・ヴァルヴァゾルが、俺に近付く。
何だ、これは……毒でも塗ってあったのか?
右足が、思うように動かない。
俺は、足を引きずるように後ずさりしながら、フォン・ヴァルヴァゾルと距離を取ろうとした。
が、フォン・ヴァルヴァゾルはそれを許さない。
左手に持っていた杭を右手に持ち替え、滑るような足取りで、俺に迫る。
肥満した巨体に似合わぬ、素早い動き。
足を半ば殺された俺では、逃れようがない。
ならば、勝機は――カウンターしかないだろう。
全神経を奴の動きに集中し、機会を窺う。
フォン・ヴァルヴァゾルが、攻撃に移るその時を――
そろそろ、奴の間合いだろう。
勝負は一瞬だ。
――来た!
俺の顔を目がけて繰り出された、白い杭。
それを、銀の籠手をはめた手の甲で、外に弾く。
空手で言う回転受けに近い動きのまま、相手の右腕を腋に挟むようにして、腕を絡めた。
そのまま、フックぎみに左拳を放ち、右腕を折ろうとする。
“山蔓 ”という技だ。
が――
全く予想外の方向から、攻撃が来た。
固めかけていたフォン・ヴァルヴァゾルの右腕を放し、身を捻って避けようとする。
ざくっ。
左肩に、浅く、杭が突き刺さった。
ここには、俺とフォン・ヴァルヴァゾル以外は、誰の気配もない。
と言うことは、この杭は、独りでに動いたのか?
「ぐ……うううううっ!」
杭が、空中で身をよじりながら、俺の肩にさらに食い込もうとする。
これは……この杭は、生きている……?
「……っ!」
俺は、杭を右手で掴み、放り投げた。
それを、俺から距離を取ったフォン・ヴァルヴァゾルが、まるで軌道を読んでいたように左手で受け止める。
右足と左肩に、信じられないような激痛があった。
何か小さく堅い物が、俺の体の奥へ奥へと、身を震わせながら入り込んでくる。
あまりの痛みに、脳が飽和状態になった。
もはや、体を強く叩いているはずの雨滴の存在すら、感じられない。
ただ、熱いような、冷たいような、痺れるような、そんな痛みを知覚するのみだ。
「微細な骨片が、あなたの血を求め、体の中へと食い込んでいるのですよ」
耳鳴りに、フォン・ヴァルヴァゾルの穏やかな声が重なった。
だが、俺には、そんな奴の言葉を理解するような余裕はない。
「安心してください。数時間もすれば、あなたの体内の骨片は、その存在を維持できなくなって自己崩壊します。それまでの辛抱です」
まるで、講義でもするような口調で言いながら、フォン・ヴァルヴァゾルの体が近付く。
俺は、右手の人差し指と中指を、フォン・ヴァルヴァゾルの顔面に向けて突き出した。
右足と左肩の激痛のため、全身の動きがバラバラだ。
俺の一撃を難無くかわし、フォン・ヴァルヴァゾルが、くるりと俺の右側に回った。
ごっ! と杭の根元による容赦のない打撃を、俺の延髄に打ち下ろす。
俺は、意識を失いながらも、闇の中で、まだあの痛みに苛まれていた。
「どう?」
車内に戻って来た緑郎に、ミアが聞いた。
もう、時間は明け方近い。だが、重くのしかかるような雨雲は未だ太陽の光を遮っている。
「ごめん。足取りを見失った」
普段の軽薄な調子からは考えられないほど沈痛な顔で、緑郎が答えた。
「一度あの中に入って、そのまま林を突っ切って別の道に出たみたいだね。そっから先は、追跡しようがないよ」
「あなた、それでも情報屋?」
「目撃者がいないと、情報も収集しようがないんだ」
その大きな瞳を赤く染めるミアに、緑郎は肩をすくめて見せた。
「……」
「じゃあ、行くよ」
「行くって、どこに?」
「綺羅ちゃんがいる所だよ」
「冗談じゃないわ!」
運転席に座り、イグニッションキーを回す緑郎に、ミアは叫んだ。
「あなたは鷹斗を見殺しにするつもりなの?」
「鷹斗ちゃんを見殺しにするつもりはないよ。――綺羅ちゃんもね」
緑郎は、無表情な顔で言った。
見ようによっては普段より格段に美男子に見えるその顔を、ミアが睨みつける。
「あたしは、冬条綺羅なんてどうでもいいわよ!」
「でも、綺羅ちゃんの居場所は分かってるんだし、しかも相手はノインテーターなんだよ」
緑郎が、ミアの視線を正面から受け止めながら、言った。
「一方、第八機密機関の潜伏場所は分からない。さらに言うなら、向こうにはたぶん修三さんがいるんだ。すぐに鷹斗ちゃんに危害が加えられる公算は低いと思う」
「でも、あの車は、鷹斗を轢き殺そうとしたじゃない!」
「あれは、ほとんど正当防衛だと思うけどね。……それに、結局はそうしなかったみたいだし」
「……」
「もし確保できるんだったら確保したいと思ってたんだと思うよ。修三さんに恩を売ることができるからね」
「それは、みんなあなたの推測じゃない」
「そうだよ」
あっさりと、緑郎が答える。
「そもそも……葛城修三は、あたしの敵よ」
ミアの瞳が、ますます鮮烈な赤光を放った。
「でも、鷹斗ちゃんのお師匠さんでもあるんだ。あの時も、修三さんは鷹斗ちゃんをすぐに殺そうとはしなかったんでしょ?」
「……」
きりっ、と堅い音が、車内に響いた。
ミアがその歯を食いしばった音だ。
「車、降りる? オレは、それを止めることはできないけど」
次第に雨足が弱まってきた窓の外を見ながら、緑郎は言った。
「でも、ミアちゃんには、短時間のうちに第八機密機関のアジトを探るなんて事、できないよね?」
「っ……」
「もし、ミアちゃんがオレのことを操っても、それは同じことだよ」
危険な色を帯びたミアの目を見つめながら、緑郎は続けた。
ミアは、ゆっくりと目を閉じた。
「あなた、見かけよりずっとひどい人ね」
瞼を開きながら、ミアが言う。
「ミアちゃんにそう言われるのはつらいけど、そーかもしんない」
「……」
ミアは、運転席と助手席の間から身を乗り出して、ダッシュボードの上でひらひらと動いている“木霊”の呪符に手を伸ばした。
ミアの白い手の中で、漆黒の人型が、もがくように動く。
「折衷案と行きましょう」
「せっちゅうあん?」
「あたしは、この紙人形の示す方へ行って、綺羅と合流するわ」
「……で、その間、オレは第八機密機関のアジトを探し出して、鷹斗ちゃんを救出する、ってわけ?」
「不満?」
ミアが、その小さな口をぎゅっと引き締める。
「――ううん。ミアちゃんの方からそう言ってくれて、助かったよ」
緑郎は、その口元に、ようやく笑みを浮かべた。
「適材適所だと思うよ。何しろ、第八機密機関の人達が一番警戒してるのは、吸血鬼に逆襲されちゃうことだからね。俺だったら、まだあの人たちの裏をかけるかもしれない」
「一方、あなたは、綺羅と合流しても戦力にならない……。そう言いたい訳ね」
「うん」
「癪ね。あなたの思いどおりに事が進むなんて」
「ごめん」
ぺこ、と緑郎が頭を下げる。
ミアは、小さく嘆息した。
「いいわ。あなたの小さな恋人に、あなたの事よろしくって言われちゃったしね」
「にひひひひひー」
「いやらしい笑い方」
むすっとした顔で、ミアは、窓の外を見た。
雨は、霧に変わっている。
「一つ忠告しておくけどね、ヴァンピールを相手に、あんまり神経を逆撫でするようなことを言うのはやめた方がいいわよ。あたし達は、かなり感情的な種族なんだから」
「うんうん。ミアちゃんがクールな見かけによらず情熱家だって事は、よーく分かってるよ」
「それをやめなさいって言ってるの!」
大声で言って、ミアは、ぷい、とそっぽを向いた。
その頬が、かすかに赤くなってる。
「じゃあ、鷹斗のこと、お願いね」
「おっけー。まかしといて。それより、むこうで綺羅ちゃんとケンカしちゃダメだよん」
「努力するわ」
言って、ミアは、ワゴンのドアを開けた。
そして、手に持っていた人型の呪符を、そっと放す。
“木霊”の呪符は、しばしとまどったように宙を舞っていたかと思うと、ついっ――と風に乗るように動き出した。
「じゃあね」
ミアが、軽い足取りで車から降り、それを追う。
呪符は、それを追う者に合わせるかのように、次第に速度を上げていった。
ミアが、フリルのついた黒いスカートを両手でたくしあげ、全力疾走の態勢をとる。
そんな小さな吸血鬼の姿が、緑郎の見守る中、フロントガラスの向こうの霧に飲み込まれるように消えた。
「さて、と……」
緑郎が、表情を引き締めた。
そして、懐から、愛用のメモ帳を取りだし、ぱらぱらとページをめくる。
しばらく後、緑郎は、一人頷いて、ワゴンを発進させた。
フォン・ヴァルヴァゾルが運転する軍用車がその場所に着いたちょうどその時に、俺は、意識を取り戻していた。
未だ、右足と左肩に、熱を帯びた疼痛がある。
身をよじろうとして、俺は、自分が拘束服を着せられていることに気付いた。
腕組みをしたような状態で袖は固定され、足はすっぽりと袋状の布に覆われて、ベルトで縛られている。
どうにか首から上は動かすことができるが、口にも猿轡がかまされている状態だ。
と、俺が転がされている後部座席のドアが、開いた。
「申し訳ありません。できるだけ平和にこちらに来て頂きたかったものですから」
フォン・ヴァルヴァゾルが、そう言いながら、俺を肩にかつぎ上げた。
屈辱に判断を鈍らせないように気持ちを落ち着けながら、周囲を確認する。
もう、朝だ。雨は止んでいるが、まだ空には雲がある。
そこは、きちんと舗装された駐車場だった。そこに隣接した白い建物に、フォン・ヴァルヴァゾルが歩いて行く。
二階建てくらいの、なかなか大きな建物である。壁は白く清潔で、まるで、真新しい工場か、何かの研究施設のように見える。
玄関にフォン・ヴァルヴァゾルが立つと、警備員の格好をした男が、両開きのガラスドアを開けた。
フォン・ヴァルヴァゾルに担がれた俺を見ても、男は何も言わない。
「すいません、この周辺の地図を用意してくれませんか?」
フォン・ヴァルヴァゾルが、警備員に丁寧な口調で言った。
警備員の顔が、かすかに強ばる。
「“花嫁”を、途中まで追跡することができました。これまでの情報と総合すれば、目的地を特定するのも容易いでしょう」
「はい」
警備員は、固い声で返事をして、奥へと行ってしまった。
どうやら、このフォン・ヴァルヴァゾルという男を相当恐れているらしい。
フォン・ヴァルヴァゾルは、悠々とした足取りで、廊下を、警備員とは逆方向に歩きだした。
途中、白衣や、フォン・ヴァルヴァゾルのように灰色のコートをまとった男女とすれ違う。
皆、拘束され、荷物のように運ばれている俺を見ても、表情をほとんど変えなかった。
フォン・ヴァルヴァゾルは、建物の奥の方にある部屋に入り、俺を下ろした。
簡素な部屋だ。小さな、壁に折り畳むことのできるベッドと、そして洋式の便器がある。どうやら、人を監禁するための部屋のようだ。
フォン・ヴァルヴァゾルが、俺をベッドに座らせ、そして猿轡を外す。拘束服はそのままだ。
「時間が無いので、手短に事実だけ言いましょう」
フォン・ヴァルヴァゾルは、相変わらず静かな口調で、言った。
髪と髭に覆われたその顔からは、いかなる表情も読み取れない。
「あなたは、あの“カインの花嫁”に、特別な感情を抱いていますね」
「……」
俺は、長いこと猿轡をかまされ、まだ痺れたままの口を、開かない。
構わず、フォン・ヴァルヴァゾルは続けた。
「しかし、それを恋愛感情であると誤解してはなりません」
「……」
「“カインの花嫁”の戦闘能力の根幹は、その長い偽りの生の間に蓄積された膨大な経験にあります。だからこそ、“カインの花嫁”は、心臓のほかに、脳――記憶部分をも弱点としているのです」
「……」
「それゆえに、あの“カインの花嫁”は、自らの記憶を他人に預ける術を身につけました。あなたは、その犠牲者なのですよ」
それは、知っている。
そんなことをいちいちここで説明されなくても、俺は、実際にそれを体験したのだ。
俺は、ミアに脳を犯され――そして、その凌辱を受け入れたのだ。
「あなたは、言わば“記憶の器”です。……しかし、吸血鬼の呪われた記憶を受容する存在など、一朝一夕に形成できるものではありません」
ぞわり、と、背筋を嫌な感触が撫でた。
この目の前の大きな男が、前髪に隠された小さい目から、針のように鋭い視線を放っているのを感じる。
「あなたは、昔、“カインの花嫁”に会いましたね」
フォン・ヴァルヴァゾルが、断定した。
あの日――あの、赤い山の中で――俺は――
赤色の原風景に、灰色の男が侵入する。
「その時です。その時、既に、“カインの花嫁”はあなたを選び、ある術をかけてしまったのです。“記憶の器”とするための術を、ね」
見てきたように、フォン・ヴァルヴァゾルは言った。
「“カインの花嫁”が、昨年、あなたの住む街に現れたのは、偶然ではありません。彼女は、かつて仕込んだ“記憶の器”の出来具合を確かめるつもりだったのですよ」
そう、なのか?
もし、そうなら――いろいろなことに、納得がいく。
今まで、あまりにも出来過ぎた偶然だと思っていたことに、理由がつくのだ。
しかし――
「もし、“カインの花嫁”との間に、何等かの精神的な繋がりがあるように感じられたとしても、それは、“記憶の器”たるべく仕組まれたあなたとあの吸血鬼との、呪術的な親和力に過ぎません。吸血鬼との間に、真の愛情など成立するわけが無いのです」
「……」
「あなたは、自分が、他の人達とやや異なる精神的性向を有しているとは思いませんか?」
「……」
「それゆえに、本来、もっと大事にすべきであった他の人達との関係を、冷たく乾いたものにしてしまいませんでしたか?」
「……」
「それは、“記憶の器”の術によるものです。“カインの花嫁”は、あなたが人生において受けるべきだった喜びと温もりを、不当に剥奪してしまったのですよ」
それは――
そんなことは――
「そして、今も、あなたは人としての幸福から程遠い所にいる」
仕上げのように、フォン・ヴァルヴァゾルは言った。
「これが、事実です。あなたへの説得は、あなたに近しい方にお願いするとしましょう」
「……」
「葛木修三さんが、いずれいらっしゃいます。それまでここでお待ち下さい」
そう言って、フォン・ヴァルヴァゾルが、拘束服の留め金のうち幾つかを外した。
「これで、あとは自力で外すことができます。乱暴なことをしてすいませんでした」
フォン・ヴァルヴァゾルが、部屋から去る。
部屋に満ちる静けさが――なぜか、妙に俺の心をささくれさせた。
「はぁっ、はぁっ、はぁっ、はぁっ……」
「あっ……あぁっ……あんっ……やぁっ……」
地下室の中で、悩ましい二つの声が重なっている。
静夜と、綺羅の喘ぎだ。
綺羅は、ベッドの上で獣のように四つん這いにさせられ、背後から犯されていた。
手枷と足枷に繋がれた鎖が、それぞれ交差し、ぴんと張っている。
が、それを引き千切るような力は、今の綺羅には無い。
「くくくっ……また、アソコの中がぴくぴくしてきたわよ……」
「やぁっ……い、言わないでェ……」
屈辱と羞恥に震える綺羅の声に、どこか甘えるような響きが混じり始めているのを、静夜は聞き逃さなかった。
「いいのよ? またイクんでしょう? ノインテーター様のペニスで、何度でもイクといいわ」
「やんっ! いやっ! いやなのっ……ああああっ!」
静夜が、巧みに腰をグラインドさせ、綺羅の密壷を、股間から生えた赤黒い触手でかき回した。
溢れた愛液は綺羅の太ももを伝い、シーツに大きな染みを作っている。
「んっ……くうううっ……う、ううっ……んあっ……」
「うふふふふふ……」
綺羅の、悔しげなすすり泣きを聞きながら、静夜は自らの唇を淫らに舐めた。
その指は綺羅の細いウェストに深く食い込み、爪が肌を傷つけて血を滲ませている。
「ああっ……出そうよ……あなたの中に、ノインテーター様の精液を注いであげるわね」
「い、いやあっ……もう、もうやめてェ……っ!」
「うまくいけば、あなたの子宮にも、ノインテーター様が宿られるわよ」
「イヤああああああっ!」
静夜の言葉に、綺羅が大きくかぶりを振る。
「んんンっ! 出るっ! 出るわっ! たっぷりあなたの中にかけてあげるっ!」
「やめてえッ! お願い! 中は、中はもう許してェ!」
「駄目よ! あなたもノインテーター様を孕むがいいわ!」
静夜が、狂気じみた声で叫び、腰を前後に激しく動かす。
「んああああああああッ! イクうッ! イクうーッ!」
胎内に潜む支配者と同調し、静夜が絶頂を極めた。
ぶびゅうううううううううッ!
「イヤあああああああああああああああああああああああああああああああああー!」
綺羅が、強制的に絶頂に追い込まれながら、しなやかな白い背中を反らした。
膨張した触手が律動し、熱い白濁液を、大量に綺羅の体内へと送り込む。
「イヤぁ……イヤぁ……入ってくる……一杯になっちゃう……」
涙に濡れた声で、綺羅がすすり泣くように言う。
すでに何度も何度も注ぎ込まれた精液が綺羅の膣内で逆流し、ごぽごぽと泡を立てながら、接合部の隙間から溢れ出た。
が、疲れを知らない触手は、一向に萎える様子を見せない。
「さあ、続けていくわよ……」
綺羅よりも先に呼吸を整えた静夜が、その大きくなった腹部で綺羅のヒップを圧するように、腰を突き出す。
「ひゃぐうっ!」
綺羅は、シーツに顔を押し付けるような格好で、悲鳴をあげた。
「も……ダメぇ……ゆる……ゆるし、てぇ……」
「そんなこと言って、あなたのオマンコ、嬉しそうにペニスを離さないわよ!」
「んぐっ! あっ! ひいんっ! そ、そんなこと……ひあうっ!」
静夜の言う通り、綺羅の秘肉はうねうねと蠢き、長大な人外のペニスを淫猥に貪っている。
自らの体の反逆に涙をこぼしながら、綺羅は、ひくひくとその背中を震わせた。
抽送に合わせ、静夜と綺羅、二人の美乳がたぷたぷと揺れる。
シーツにこすれた乳首はしっかりと勃起し、快楽の電流で綺羅の全身を痺れさせた。
「ひあっ! ひっ! ひああっ! もう……もう、ダメぇ……!」
絶望的なまでに甘美な更なる絶頂の予兆が、再び綺羅の膣肉を痙攣させる。
静夜が、勝利を確信した笑みを、その淫らに赤い唇に浮かべた。
その時――
「っ!」
誰も侵入するはずの無いこの部屋に、かすかな気配を感じ、静夜は振り向いた。
「そこっ!」
叫びとともに、静夜は、右手を一閃させ、次元断層を発生させた。
き――いいいいいいいいいいいンンンンンンン……!
音にならない震動が空間構造を揺らし、部屋中に反響する。
「な……?」
静夜は、思わず両手で耳を押さえた。
狭い部屋の中、静夜自身の放った次元断層がでたらめに跳ね回っている。
ぱっ! と鮮血が霧となって散った。
複数の次元断層が、静夜の白い体に、幾つもの傷を走らせたのだ。
数秒して、ようやく、無音の共鳴が静まる。
「な、何が……」
思わず呟く静夜の目の前に、ずたずたに切り裂かれた人型の呪符が落ちる。
「木霊」の二文字が書かれた、黒い呪符だ。静夜が察知したのは、扉の隙間から入り込んだこの式神の気配だったのである。
がくん、と鉄パイプ製のベッドが、二つ折りになった。
「くっ!」
その姿からは信じられないような身のこなしで、静夜が宙を跳び、床に降り立った。
がらあん、と音を立てて、ベッドが潰れる。
ベッドの残骸を挟んで静夜の反対側に、綺羅が立ち上がった。
その四肢を戒めていた鎖は、全て、切断されている。
部屋の中を縦横に疾走した次元断層によるものだ。
「……」
どんよりと濁ったような目をした綺羅が、顔を静夜に向けたまま、右手の人差し指で、自らの胸元に触れる。
そのまま綺羅は、するどく伸びた爪を突き立て、胸から腹にかけてを一気に切り裂いた。
ばあっ! と鮮血が溢れ――そして、傷が次第に塞がっていく。
「よくも……」
その傷の痛みをきっかけにしたかのように、綺羅の目に、光が戻った。
「よくもやってくれやがりましたね……」
綺羅が、歯を食いしばるようにして、言う
「あの紙人形が、私の力を跳ね返したの……?」
茫然と綺羅の様子を見つめていた静夜が、思い出したように呟いた。
「“木霊”ですからね。でも、まさかこんなふーになるとは思いませんでしたよ」
今までの凌辱で汚された顔に、綺羅が、皮肉な笑みを浮かべる。
「式神さんが、最期に機転を利かせてくれたのか、それとも単なる偶然か……。何にせよ、これも日頃の行いがいいからですね」
「――さっきまで、情けなくひいひい泣いていたこと、忘れたの?」
言いながら、静夜が、紅い目を光らせた。
「……忘れてくれって言われたって、忘れませんよー、だ」
その口調に反し、綺羅の瞳も、不吉な赤色に輝いている。
そして――二人は、ほぼ同時に、互いに向かって大きく跳躍した。