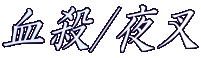
第三章
![]()
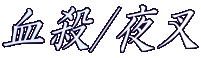
第三章
男は、高級ホテルの一室で、女と交わっていた。
最高の女だ。
男の貧弱な想像力では思いもよらなかったような快楽が、全身を支配している。
もともと、この女は“心付け”の中に入っていた訳ではない。
“心付け”として学園が差し出した少女たちを引率してきたのが、この女だ。
少女たちは、いずれも劣らぬ美貌の持ち主だったが、男は、この女を選んだ。
若い娘が嫌いな訳では、無論ない。しかし、地味なスーツを身にまとい、一見きつそうな表情をその整った顔に浮かべた女の本質を、男は、牡の本能で察知したのだ。
少女たちではなく、この女を選んだ時、女の顔に、ぞくりとするような淫蕩な笑みが浮かんだ。
女は、スーツの下に、扇情的な真紅の下着をまとっていた。
まるで血のようなその色が、女の青白い肌に映えていた。
女は、積極的だった。
その細く長い指と、ルージュが必要ないほどに鮮やかな色の唇、そして、柔らかいながらも弾力に富んだ豊満な胸で、男の勃起に奉仕した。
口内に二度、顔と胸に一度ずつ、たっぷりと射精した。
これほど立て続けに精を吐き出したのは、学生時代以来だった。
中央省庁の中でも、うま味が少ないと言われる教育官庁に進んで入庁した当初は、それなりの理想と野心を抱きながら、この国の教育行政に身を捧げるつもりだった。
だが、お決まりの挫折と無力感が、男を呆気なく堕落させた。
所詮、数値と道徳などで――いや、いかなる手段によっても、子供たちを制御することなど不可能なのだという当たり前のことを、男は、不覚にも最近になって気付いたのだ。
以来、男は、ありうべからざる事件の隠蔽と、ありもしない健全さの演出のために、一日のうち何割かの時間を割く、ごく普通の高級教育官吏となったのだ。
そして、今、ある学校に関するいくつかの不測の事態を“解決”した見返りとして、その学校からの“心付け”を貪っている。
女の蜜は、甘く、熱く、そしてかすかに血の匂いと味がした。
それを、女主人にかしずく奴隷のようにはいつくばって、舐め啜る。
「あぁ……すてき……すてきですわ……」
口調だけは丁寧なまま、女は、ベッドの上でしどけなく足を広げ、男の口唇愛撫に身を委ねている。
その瞳に、燃えるような情欲がある。
が、そのさらに奥にあるのは、氷のように冷たい蔑みの色だ。
「もっと、もっとしてください……ああ、そこを、もっと強く……」
女の甘く媚びるような声に、男は嬉々として従っている。
親子ほども年の違う男と女のうち、主導権を握っているのは、今や、明らかに女の方だ。
男は、犬のように荒い息をつきながら、犬のように四つん這いになり、犬のように舌を使っている。
すでにその脳を支配しているのも、犬のように単純な性欲だけだろう。
姿形とは全く異なる次元での醜悪さにまみれた中年男の姿が、そこにあった。
そして、そうであればあるほど、女の美しさが、際立つのだ。
冷たく、鋭く、酷薄な、女の表情。
そうであればあるほどに、女の顔は美しく、そして淫らに見えた。
「きもちいい……きもちいいです……うっ、ああっ……ああん……!」
女の体がうねり、もだえ、のたうつ。
それは、シーツの上で身をくねらせる、生白く鱗のない蛇を思わせた。
ほどけ、乱れている髪は、漆黒の蛇の群れ。
無彩色の妖しい蛇たちが、赤い舌をちろちろと踊らせながら、哀れな犬を呑み込もうとしている。
「お、おねがい……もう、がまんできないんです……」
慎ましさを擬態したかすかに震える声が、男を誘う。
「私のそこに、貴方のを挿れてください……早く私を犯して……!」
女の声に、男は、犬そのものの声をあげた。
白くしなやかな体に、褐色のたるんだ肉がのしかかる。
これまでよりさらに大きく膨張したペニスが、女の、しとどに濡れたクレヴァスを探り当て、その中へと分け入って行く。
「あ……はああああっ!」
亀頭が膣道を擦り上げるようにして侵入してくる感覚に、女は、高い声を上げた。
男が、余裕のない動きで、腰を動かす。
二人の接合部で、淫猥な音が弾け、熱い愛液がしぶいた。
「あぁん! いっ! いいです! いいですっ!」
男の腰の運動に合わせ、女が声を上げ、男の背中に腕を回す。
愛情あっての動きではない。男の動きを制御し、より強い快楽を得ようとしてのことだ。
知らぬ間に、抽送の深さやリズムを支配されながら、男は、凄まじいまでの快感に獣のように喘いでいた。
膣の中の粘膜がざわめき、まるで無数の微細な舌に愛撫されているかのような快楽をもたらす。
さらに、その締め付けはきつく、何度も射精を繰り返したペニスが痛みを感じるほどだ。
それでも、それを上回る快感が、男を圧倒する。
「すてき……すてきですっ! ああんっ! オチンポいいっ! オチンポきもちいいですっ!」
すでに沸点を超えてしまっている男の興奮をさらに煽ろうとするかのように、女が、あからさまな言葉を繰り返す。
「す、すごい……! オチンポが、私のをえぐって……ぐりぐり動いてますっ! イキそうっ! オマンコいきそうですわっ!」
女が、男の背中に爪を立てる。
男の皮膚は易々と引き裂かれ、溢れる血が、女の手指を濡らした。
女の顔に、恍惚の表情が浮かぶ。
汗とともに血の雫を飛び散らせて腰を動かしながら、男は、性感に捕らわれ続けている。
「イクっ! イキますっ! あうっ! あっ! あああああんッ!」
女が、その白く細い腕で、男の頭を引き寄せた。
そして、男を射精に導くべく、膣肉をさらに蠢かせ、ペニスを搾り上げる。
「イっ……イクうぅゥーッ!」
高い声で叫び、そして、女は、男の首筋に噛み付いた。
長く伸びていた白い牙が男の喉を噛み破り、かっと開かれた目が、燠火のように赤く燃える。
「おおおおおおおおおおおお!」
男が、屠殺される獣そのままの声を上げた。
びしゅうううっ! と、人として最後の精を、男が、女の体内に放つ。
時がねじれてしまったような、歪んだ沈黙。
それが、長く、長く、続く。
「……ふう」
女は、男を押しのけるようにして、上体を起こした。
男の体が、ごろりとベッドの上を回転し、そのまま床に落ちる。
女は、そんな男に目もくれず、血にまみれた口元を、舌で舐めた。
そして、やはり男の血に濡れた自らの指を、一本一本、丁寧に舐め上げる。
男のペニスをフェラチオをしていた時よりさらに淫らな表情が、女の顔に浮かんでいた。
と、その顔に、緊張が走った。
赤く染まったままの瞳を、ドアに向ける。
ドアが、ゆっくりと開いた。
「おじゃましますよー」
場違いな明るい声が、部屋に響く。
「お取り込みは終わったみたいですね」
Tシャツとスリムジーンズといういで立ちに、サマージャケットを羽織った若い女が、その姿を現した。
「千坂静夜さん、ですね?」
「……あなたは?」
「わけあって吸血鬼探偵なんてしてる、冬条綺羅ってもんです」
そう言いながら、綺羅は、静夜に白い歯を見せて笑った。その犬歯の先が、かすかに尖っている。
静夜は、全裸のまま、ベッドから降り立った。
「何の用かしら?」
赤い瞳で、未だ黒いままの綺羅の瞳を見つめながら、静夜が訊く。
「いえ、大したことじゃないんですけどねー」
綺羅は、笑みを崩さず、言った。
「静夜さんのご主人様って、どこにいるんです?」
「――そう尋ねられて、答えると思ってるの?」
「思ってませんけどね」
綺羅は、サマージャケットのポケットに手を突っ込みながら、軽く溜息をついた。
「じゃあ……いきますか」
綺羅が、無造作にポケットから手を出した。
そのまま、何かの形に折られた黒い紙片を、床に放る。
紙片は、床に落ちる前に渦巻く黒い煙を上げ、奇怪な獣に変じていた。
「っ!」
驚きの声を上げる静夜に、四体の黒い異形の獣たちが殺到する。
大きく鋭い門歯をもつもの、鱗と粘液に覆われたもの、黒い炎に包まれた猫のようなもの、自ら回転し旋風を巻き起こすもの――
だが、獣たちの爪や牙は、静夜の体には届かなかった。
床に転がっていた男が起き上がり、静夜を庇うように立ちはだかったのだ。
男の目は鈍い赤色に光っており、その顔は、生まれたばかりの吸血鬼特有のこの世ならぬ飢餓感に歪んでいる。
その男の体が、一抱えほどの大きさの獣たちに覆われた。
ぐじゅっ! という耳を覆いたくなるよう音が、響いた。
鮮血が、散る。
男の体は、一瞬のうちに引き裂かれ、噛み砕かれていた。
熱のない炎が、男の体を構成していた肉片を包み、灰に返す。
床に降り立った漆黒の獣たちが、目の無い顔を静夜に向ける。
「くうううううっ!」
静夜が、右手を大きく振った。
その爪は、獣たちのいずれにも届かない。
が、今にも静夜に飛びかかろうとしていた四体の獣たちは、動きを止めていた。
「――」
一言も声を上げないまま、獣たちが床に崩れ落ちる。
そして、それは、それぞれ表面に「鉄鼠」「水虎」「火車」「風狸」と書かれた呪符へと姿を変えてしまった。
「次元断層ですか。やりますねー」
余裕を感じさせる口調で、綺羅が言った。
その姿は、元の場所から一歩も動いていない。
「しゃっ!」
静夜が、右手を、綺羅のいる方向へと繰り出した。
その指先は、この世界を構成する空間に裂け目を発生させ、あらゆるものを切断する刃を形成する。
綺羅の姿が、まさに四分五裂した。
そして――床に、人型に折られた黒い呪符の細かな切片が、はらはらと落ちる。
「むきになっちゃって、可愛いですねー」
その声は、驚愕する静夜のすぐ右側から聞こえた。
慌てて向き直ろうとする静夜の右の手首を、白い手が、意外なほど強い力で掴む。
「くっ!」
振り払いざま、次元断層を発生させようとする静夜の動きを、綺羅が、巧みな体重移動でコントロールする。
ぐるん、と静夜の周囲で、世界が回転した。
綺羅が、静夜の右手を取ったまま、合気の動きで投げたのだ。
どっ! と容赦の無い力で、静夜は頭から床に叩きつけられた。
綺羅が、朦朧とした静夜を俯せにして、その右手を捻り上げる。
「この……はなしてっ!」
身をよじる静夜の背中に、綺羅が右膝で体重をかける。
そして、綺羅は、静夜の右手を両手で持ち、無造作に捻った。
「んぎいっ!」
ごきん、というシンプルな音を掻き消すように、静夜が、短く鋭い悲鳴を上げる。
その肩から先が、ありえない角度に曲がっていた。
「右手が武器なんですから、きちんと破壊しておきませんとねー」
綺羅が、涼しい声で言う。
「これが、あなたの選んだ世界のやり方なんですよ。覚悟、できてました?」
静夜には、綺羅がどんな顔で話をしているのか、見ることができない。
が、その口調は、普段どおりのものだ。
「うあ、あああ、あぁ……」
静夜は、その目から涙をこぼし、泣き声を上げていた。
「さ、教えてもらいましょうか。ノインテーターがどこにいるのか」
「う……」
「あまり、手間はかけないでくださいね」
「――ぎゃっ!」
再び、静夜が悲鳴を上げた。
今度は、肘だ。
静夜の剥き出しの右腕は、もはや、何かの前衛芸術を思わせる形に歪み、ねじれている。
「も、もう、やめて――」
喘ぎのような泣き声の合間に、ようやく、静夜が言う。
「あなたがどーしてほしいのかなんて、訊いてないです」
綺羅が、つまらなそうな声で言う。
「ノインテーターは、どこですか?」
「そ……それは……」
かすれ声で言いかける静夜の顔に、綺羅が、顔を近付ける。
その時――
「其の辺にしておいてやれ」
どことも知れぬ暗がりの奥から、その声が響いた。
「っ!」
綺羅が、静夜をそのままにして、大きく飛びのく。
広い部屋の中央に降り立ち、綺羅は、赤色に変わった目で周囲を見回した。
部屋の四隅で、闇が、ゆるゆると凝り固まる。
「ノインテーター様……!」
静夜が、安堵と畏怖に声を震わせながら、言った。
「最初からそこにいやがったわけですか……」
言いながら、綺羅は、油断なく四方に目を配った。
ノインテーターは、一度に多くの分身を実体化させるほど、その後の行動に支障を来す。
そのことをミアから聞いていた綺羅は、必死になって、白銀の髪の吸血鬼の気配を数えていた。
一度に、何体なのか。それによって、綺羅がこれから起こすべき行動の選択は変わってくる。
「静夜よ、良い勉強になったろう」
ノインテーターは、綺羅の思惑など知らぬげに、静夜に語りかけた。
「人を嬲る術を学ぶのは大事だ。然し、何時かは同種と対峙する事も念頭に置いておかねばな」
「は、はい……」
どこか面白がっているような口調のノインテーターに、静夜が頭をうなだれて返事をする。
ノインテーターは、完全に姿を現していた。
四体。
他に、気配は無い。
「きついですけど、頑張りますか」
綺羅が、右手をサマージャケットの懐に差し入れながら、言った。
「決断が早いな。其の様な所も、あの父親に似ている」
四対八つの赤い瞳が、綺羅を見据える。
静夜よりも、綺羅よりも、鮮やかな真紅の瞳。
その色に心を奪われまいとするかのように、綺羅が、半目を閉じる。
四人のノインテーターがまとう漆黒のマントが、かすかに揺れた。
ばっ!
綺羅が、「野衾」と書かれた無数の黒い呪符を、ばら蒔く。
それは、小さなコウモリともムササビともつかぬ奇怪な禽獣となって、ノインテーターの視界を奪った。
それに構わず、ノインテーターが部屋の中を縦横に駆ける。
綺羅の姿も、ノインテーターの影も、呪符が変じた妖異の目くらましの中、もはや常人の視覚では捕らえきれない。
異獣の翼と引き裂かれた黒い呪符が舞い狂う中、銀色の光が四条、宙を貫いた。
「むっ!」
驚きの声が、あがる。
呪符が全て引き裂かれ、床に落ちた時には、ノインテーターは、四体とも、奇怪な祓串 によって体を貫かれ、動きを封じられていた。
黒く染められた呪符を紙垂 とし、長い銀の針を大幣 とした、退魔のための祓串だ。
その祓串に心臓を貫かれた二体のノインテーターが、炎をあげて瞬時に灰に還る。
「打率十割、打点二ってとこですね」
両手にそれぞれ祓串を握り、綺羅が言う。その体には、一筋の傷も付いていない。
「腕を上げたか……?」
肺を傷つけたのか、苦しげな声で、ノインテーターが言う。
「これが本来の実力です」
綺羅は、そう答えながら祓串を振りかぶった。
残り二体のノインテーターの顔に、全く同じ奇妙な笑みが浮かぶ。
「いけない!」
その声と同時に、綺羅は、態勢を崩していた。
投擲された二本の祓串のうち一本が、一体のノインテーターの心臓を貫く。
が、もう一本は、空しく壁を貫くのみだ。
「くっ!」
綺羅が、声を上げながら、もがく。
静夜が、左腕一本で背中から綺羅の体にしがみつき、首に牙を立てたのだ。
「――未だ旅の終りには早いと云う事か」
言いながら、残り一人となったノインテーターが、右の胸を貫いたままの祓串を引き抜いた。
「このおっ!」
静夜の牙と爪に傷つけられながら、綺羅が、祓串を逆手に構えて、ノインテーターに向かって走る。
ノインテーターの牙や爪よりも、綺羅の祓串の間合いの方が、深い。
しかし――
どずっ!
ノインテーターのマントを突き破って出現した触手が、綺羅の下腹部を、その先にある静夜の体もろともに貫いた。
「あ……」
静夜が、激痛に失神し、力無く床に倒れる。
傷は、やはり腹部だ。大量の血が溢れてはいるが、静夜の呪われた生はまだ終っていない。
「っ……!」
綺羅は、ぎりぎりと歯を食いしばった。
そして、体を貫かれたまま、それでもさらに前に進もうとする。
「我が一族は、往生際が悪いな」
ノインテーターは、笑みを含んだ声で言いながら、触手で綺羅の体を持ち上げた。
「ぐうっ……!」
ようやく、綺羅の口から悲鳴らしきものが漏れる。
そんな綺羅を、ノインテーターの触手が、凄まじい力で床に叩きつけた。
「あうっ!」
新たな鮮血が、綺羅の傷口から溢れ出る。
「う……あ……」
綺羅が、目を見開いたまま、動きを止めた。
ずるりと、触手が、綺羅の下腹部の傷からその身を抜き出す。
その瞬間、まるで犯された直後の少女のように、綺羅の体が一度だけびくりと痙攣した。
「さて……行くか……」
ノインテーターは、誰にともなく呟いて、綺羅と静夜の血にまみれた体を、それぞれ両腕で抱え上げた。
「……」
「……」
俺とミアは、その部屋の真ん中で声を失っていた。
萌木探偵事務所の、事務室。
いろいろと探りを入れ、この地域の安全を確認するまで、一週間はかかった。
そして、夜、この事務所を訪ねたのだ。
外から見ると、どんな深夜にも明かりがついていたこの事務所の窓が、真っ暗になっていた。
その時点で萌木氏に電話を入れたのだが、いっこうに応答がない。
事務所のドアノブをひねると、鍵はかかっていなかった。
俺達は、何度も訪れたこの事務所の中に入り、電灯のスイッチを点けた。
部屋は、散々な有様だった。
まるで小さな竜巻が部屋の中で吹き荒れたかのように、床に書類が散乱している。
机やキャビネットの引き出しは明けられ、中身がぶちまけられていた。
徹底的に家捜しをされた結果であろう事が、容易に想像できた。
「ひどいものね」
長い沈黙の後、意外と冷静な口調で、ミアが評した。
「……ああ」
俺は、そう答える以外にない。
「戦闘の形跡はないわね。血の匂いもしないし……幸いなことに、と言うべきかしら」
「そうだな」
「さて、どうしましょうか」
細い腰に両手を当て、溜息ににた苦笑を漏らしながら、ミアが言う。
「どうもこうも……萌木氏がどこに消えたのかが問題だな」
「彼のワゴン、駐車場に無かったわね。それで逃亡中ってところじゃないかしら」
「俺も、そう思う」
言いながら、俺は、萌木氏がどこに向かったかの手掛かりになりそうなものを、探した。
だが、ここまで散らかされていると、どこをどう探していいか見当もつかない。
そもそも、そういう捜索活動が一番得意なのは、俺が知る限り萌木氏なのだ。
「……これ、壊れてるわ。電源が入らない」
ミアが、机の上のデスクトップPCのスイッチをいじりながら、言った。
「多分、中身もそれなりに処理されてるんでしょうけど……部品、持ち帰ってみる?」
「やめておこう。データを復活させるツテなんて、それこそ萌木氏しかいなかったわけだし」
「……後手に回ったわね」
ミアが、定位置とはかなり離れた場所にある椅子に腰掛け、言った。
「誰の仕業かな?」
「ノインテーターか、ハンター達か……ハンターだったら、第八機密機関でしょうね。ヴァチカンは、あれ以来、静観を決め込んでいるみたいだし」
ミアが言うのは、異端審問官のジョバンニ・バッティスタ・チボーが、ホテルの屋上から墜死した件だ。確かに、あの後、奴の仲間らしき人間との接触はない。
「この国のそういう稼業の人達は、最初から随分おとなしいみたいだしね」
「なぜかな?」
「冬条綺羅や“破壊屋”でさえ梃子摺ってるのを見て、二の足を踏んでるんでしょうね」
「なるほど」
綺羅や、師匠の実力は、裏の世界でもトップクラスに位置する。そのうち一人が――表向きは――死に、そしてもう一人が行方不明になるような件には、好んで近付きたいとは思わないのだろう。
自分が、強烈な渦のまさに中心にいるのだということを意識して、俺は、天井を仰いだ。
「もしかしたら、萌木緑郎は……」
そう言いかけ、ミアが、口をつぐんだ。
俺も、その気配を察し、ドアの方に目を向ける。
気配が、二人分。それがドアのすぐ外にあった。
緊張はしているが、敵意はない。そんな足運びが立てる物音を、俺は、聞き分けることができるようになっていた。
ドアが開く。
長身の、半白の髪を長く伸ばした若い男と、中学生くらいの眼鏡をかけた少女が、部屋に入ってきた。
言葉を交わしたことはほとんどないが、この事務所で見かけたことがある。萌木氏のボディーガードと、そして事務を務める、犬月という兄妹だ。
「言っておくけど、あたしたちがこんなふうにしたわけじゃないわよ」
部屋の惨状に息を飲む少女に、ミアが、笑みを含んだ声で言った。
「わ、分かってるわよ、それくらい!」
確か、ランという名前の少女が、声をあげる。
「羽室鷹斗と……“カインの花嫁”のミアだな?」
「その名前で呼ばないでよ」
飄次郎という名のその男の言葉に、今度はミアが不機嫌な声を出す。
「明かりがついてたんで、おそらくと思って来たんだ。君達を待っていた」
なるほど。この事務所の見えるどこかに、この二人は潜伏していたのだろう。
「緑郎から預かり物だ」
言いながら、飄次郎氏は、黒いスーツの懐から携帯電話を取り出した。
「メモリの中に入ってる番号のどれかで、あいつと連絡が取れる。だが、ここでは使うな、という話だ。盗聴の心配のない、人気のない場所で使ってくれということを言付かってる」
「萌木氏は、どこなんです?」
「俺も聞いてない」
俺に携帯電話を渡しながら、飄次郎氏が、秀麗な眉を寄せる。
「別件で、俺は身動きが取れないんだ。本来なら、君らを手伝って、緑郎と合流したいんだが……」
ちら、と飄次郎氏は、本人に気付かれないように、自らの妹に目をやった。
それで、俺は合点が行った。飄次郎氏は、この少女やその他、萌木氏に近しい人間を守るために、この街を動けないのだろう。
ミアを非友好的な視線でにらんでいるこの少女のことを、萌木氏は「彼女」だと言っていたことがある。それは冗談だとしても、大事な人間であることは違いない。
「分かりました。この件は、俺達でどうにかします」
「すまない」
「いえ、もともと俺達のことですから」
そう言うと、飄次郎氏に、なぜか痛ましいものを見るような目で見られてしまった。
「とりあえず、ここをできるだけ早く離れた方がいい。敵の手はすぐ近くまで迫っている」
「そうみたいね」
飄次郎氏の言葉に答え、ミアが軽やかな動作で立ち上がった。
「こんなこと、あんたみたいな人に頼むの、ヤなんだけど――」
自分に向けられたこの言葉に、ミアが、ランの方に顔を向けた。
「お願いだから、緑郎のこと、助けてあげて」
「口の利き方を知らない子ね」
呆れたように笑いながら、ミアが言う。
「すまない。ろくに学校に行かせてないもんでな」
「お兄ちゃんは黙ってて!」
几帳面に謝る飄次郎氏に、ランが声をあげる。
「とにかく、お願い――あたしにできることだったら、なんでもするから!」
「なんでも?」
くすっ、とミアが笑った。
「いいの、そんなこと言って? あたしが何者なのか、お兄さんや彼氏に聞いてるんじゃないの?」
「分かってるわ」
ミアの意地の悪い物言いに、ランは、少しだけ声を固くした。
「あたしの血が欲しいんだったら、いくらでもあげるわよ。緑郎のためだったら、そんなの、ぜんぜん恐くないもの!」
「あら、見上げた覚悟ね」
ミアが、挑発的に笑う。
「た、ただ、その……あたし、もうバージンじゃないけど……」
ランのこの発言に、飄次郎氏が、瞬間的に凍りついた。
「ふふふっ……。別に、処女の血になんて興味ないわ」
真っ赤になったランの顔と、青ざめた飄次郎氏の顔を見比べながら、ミアは言った。
「もしあなたに恩を売ることができたら、あなたには、もっとイヤなことを頼んであげる」
「分かったわ……。じゃあ、緑郎のこと、お願いしたからね!」
「はいはい」
くすくすと笑いながら、ミアが言う。
ランは、奇妙な目で、そんなミアをじっと見つめた。
「行こ、お兄ちゃん……って、どうしたの?」
「い、いや……」
飄次郎氏の声はわずかに震えていた。何か言いたいのだが、何も言えない。そんな様子だ。
そして、二人は、事務所から出て行った。
「ああいう妹がいたら、楽しそうね」
ミアが、まだ笑みの名残を唇に溜めながら言った。
「すぐ、あっちがお姉さんになっちゃうんだけど」
「……あの子に、何を頼むつもりなんだ?」
いささか心配になって、ミアに訊く。
「内緒よ」
そう言うミアの横顔に、寂しげな影がよぎる。
「けど……ヴァンピールなら、誰だって同じこと、言うんじゃないかしらね……」
自分だけに言い聞かせるような、ミアの囁き声。
俺は、なぜか、それが聞こえなかった振りをしてしまったのだった。