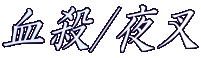
第二章
![]()
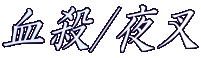
第二章
「はぁ……っ」
艶めいたため息をつきながら、ミアが、床に腰を落とした。
そして、まだ少しぼうっとしていた俺に向き直り、俺の下半身に抱き着いてくる。
「お、おい……」
「鷹斗……鷹斗のここ、べとべとよ?」
そう言って、ミアが、萎えかけの俺のペニスに、ちゅっ、と口付けする。
「あたしが、綺麗にしてあげる……」
「それは……んっ」
思わず、小さく声をあげる。
ミアが、その舌で、まだ敏感なままの亀頭をぺろりとなめたのだ。
そのまま、てろっ、てろっ、てろっ……と舌を踊らせ、俺の肉棒に付着したままの粘液を舐め取っていく。
「ミア、お前……」
ただ一度、しかも夢とも幻ともつかない体験の中でそうされて以来、俺はこのような口唇愛撫を受けたことがない。
思わず引けそうになる腰にぎゅっと腕を回し、ミアは、ぴちゃぴちゃと音を立てて、精液と愛液で汚れた俺のペニスを舐めしゃぶった。
「ずっと……ずっとコレ、したかったの……」
ちゅっ、ちゅっ、と肉茎の側面に唇を寄せ、軽く吸引することを繰り返しながら、ミアが言う。
その声は、未だ情欲に濡れているようだ。
「はしたないと思われるのがいやだったから、我慢してたけど……もう限界……」
「ミア……」
「うふっ、可愛い……鷹斗の、ぴくぴくして……また元気になってきたわよ?」
ミアの言葉どおり、俺のペニスは、彼女の絶妙な愛撫によって、すでに半ば勃起してしまっていた。
そんな俺の浅ましい生殖器官を、ミアの可憐な舌と唇が、清めていく。
精液と愛液が舐め取られ、唾液が、俺の肉棒を濡らす。
一通りペニスの表面を舐めしゃぶった後、ミアは、猫のように目を細めて、俺の亀頭部分を咥え込んだ。
「ん……ふぅん……んんん……っ」
悩ましい息を鼻から漏らしながら、ミアが、先端を口に含んだ状態で、舌を動かした。
くちゅくちゅという湿った音が、ミアの口元からあがる。
舌の裏側を使っているのか、異様に柔らかい感触が、俺の亀頭を這い回る。
「ミア……お前……」
俺は、淫らな口技を施すミアのことを、半ば茫然と見下ろすばかりだ。
時折、鮮やかな赤い色に染まったミアの瞳が、ちら、ちら、と俺の顔を伺う。
自分がどんな表情をしているのかは分からないが、俺の顔を見るたびに、ミアは、満足そうに目で笑った。
そして、いっそう激しく舌を使うのだ。
すでに完全に勃起してしまっている俺のペニスの先端から、断続的に、腺液が漏れる。
ミアの口の中を穢したくないという思いは、しかし、うっとりとその液を啜るミアの表情の前に、まるで薄い氷のカケラのように溶け崩れてしまった。
「んっ……ちゅっ……ちゅぶ……ぴちゅっ……ちゅぅっ……ちゅぱ……」
湿った音をかすかにたてながら、ミアが、俺のペニスをしゃぶり続ける。
腰に回されていた両腕は解かれ、両手の指先は、浅ましく静脈を浮かしていきり立つ肉茎の表面を、あやすように撫で、こすっていた。
時には、指がさらに下に動き、垂れ下がった陰嚢を愛しそうに揉み、軽く引っ掻くように刺激する。
さらに、意図してのことかどうか、ミアの歯が、たまに俺の亀頭の表面をこすった。
その鮮烈な感触は、俺の性感を危険なほどに高ぶらせる。
「んっ……ぷはっ……ふふふ……もう、こんなに元気にして……」
一度口を離し、ミアが、完全に天を向いた俺のペニスを、指先でつーっと上から下に撫でる。
その刺激だけで、俺のペニスは、ぴゅるっ、と激しく先走りの汁を溢れさせてしまった。
「あん……もったいない……」
自らが漏らした体液で濡れた俺のペニスを、ミアが、ハーモニカでも吹くように横咥えにする。
そのまま、ちゅるるっ、と唇をスライドされ、俺は思わず軽くのけぞってしまった。
「んっ……んんっ……はあっ……気持ちいいのね、鷹斗……」
ペニスの根元と先端を指先で軽くつまむようにして固定し、褐色のシャフトにぴちゃぴちゃと舌を使いながら、ミアが言った。
俺は、ミアの言葉に、曖昧に頷くことしかできない。
「もっと、気持ち良くしてあげる……」
そう言って、ミアは、再び俺のペニスを口の中に収めた。
「ん……んく……っ」
そのまま、何かを飲み込むように、ミアは俺のペニスを喉の奥にまで迎え入れた。
「ん……っ!」
ミアの舌と口蓋がシャフトをこすり、そして柔らかな喉の粘膜が先端にまとわりつく感触に、俺は、声にならない声をあげてしまった。
一度射精していなかったら、今の刺激だけで、ミアの喉の奥に精をぶちまけてしまったはずだ。
が、これは、始まりに過ぎなかった。
「んっ……んぶっ、んぶっ……んぐっ、んんんっ……!」
ミアが、頭を大きく前後させ、口の中全体を使って、俺のペニスを扱き始めた。
きゅっと締め付けられた赤い唇の圧力が、俺のシャフトを前後に滑る。
裏筋で、軟体動物のように蠢く舌を感じ、亀頭で、心ならずもミアの喉奥をリズミカルに小突く。
「あっ……あぁっ……あ……!」
俺は、情けない声をあげながら、腰が砕けて倒れそうになるのを、必死にこらえていた。
ぐぷっ、ぐぷっ、ぐぷっ、ぐぷっ……という卑猥な音が、ミアの唇からあがる。
ミアは、苦しそうな、それでいながらどこか恍惚とした表情で、俺のペニスを口で刺激し続けた。
秘部がもたらすそれとは全く異なる快感が、俺を追い詰めていく。
口全体で、扱かれ、吸われ、搾られる。
ペニスの根元で、射精欲求がぐつぐつと煮立っているいるようだ。
それを、俺は、必死にこらえる。
それが、ミアの口をこれ以上汚したくないと思ってのことか、それともこの快感を一秒でも長く味わっていたいという気持ちによるものか、自分でも判然としない。
ただ、耐えれば耐えるほど、射精への欲望は危険なほど高まっていった。
それを、奥歯を噛み締めるようにして、どうにかこらえる。
「はぁっ……」
ミアが、焦れたように、口を離した。
「ね、早く出して……早く私に飲ませて……」
右手で肉茎を扱き、左手で陰嚢を揉みながら、ミアが言う。
「欲しいの……鷹斗のが……ねぇ、遠慮なんかしないで……あたしの口に、たくさん出して……」
言葉の合間にも、我慢できなくなったように、ぴちゃぴちゃと舌先で亀頭をしゃぶり、射精をねだる。
「欲しいの……お願い……私に鷹斗の熱い精液、飲ませて……私の口の中で射精して……!」
隠しようのない淫らな欲情が滲んだ、甘く媚びるような声。
そして、ミアは、俺のペニスを一気に根元まで吸引した。
「うあっ!」
ペニスの表面をずるんとこする、生温かく濡れた柔らかい感触。
俺の忍耐は、それで、呆気なく砕け散った。
びゅううううっ、と――
ミアの口の一番奥で、俺は、大量に射精してしまった。
何度も、何度も、何度も、何度も、ペニスが律動し、精液のカタマリをミアの喉にたたき込む。
一度目と同じくらいの量を、一度目より激しい勢いで……
「んぶっ! んぐっ……んぶ、んんんっ!」
ミアの、苦しげな声。
慌ててミアの頭を股間から引き離そうとする。
だが、結局、あまりの快感に俺はうまく体を動かすことができず、むしろミアの顔をますます腰に押し付けるような格好になってしまった。
目の眩むような快楽。
幼い少女の喉奥に精を注ぎ続ける、背徳的な愉悦。
いつしかそれに捕らわれ、俺は、ミアの艶やかな髪を掴んで、その頭部を固定していた。
「ん……んぐ……ぐ……んううっ……」
ミアが、かすかに喉を鳴らす。
「ん……んぐっ……んくっ、んくっ、んくっ……」
口内に溜まった精液を少しずつ飲み込む、ミアの喉の動き。
それを、次第に力を失っていくペニスで感じる。
全身から、力が抜けた。
そして俺は、ようやくミアの髪から手を放していた。
「んくっ……ちゅぶ……ちゅば……ちゅっ……」
ミアは、ひとしきり精液を飲み終わった後、丁寧な舌使いで俺の肉棒を舐め回した。
白濁液にまみれた俺のペニスを舌で清め、尿道に残っていた精液まで残らずすすり上げる。
「んふっ……美味しかったわ、鷹斗……ご馳走様♪」」
ようやく俺のペニスを口から解放して、ミアは言った。
「ぁ……」
俺は、強烈すぎた快感の余韻に、まともに口を利くことができない。
数歩、よろめくように後ずさると、そこにベッドがあった。
思わず、ベッドに座り込む。
「素敵だったわ……」
立ち上がり、俺の顔に顔を寄せながら、ミアが言った。
その目許はほんのりと赤く染まり、濡れた瞳は、真紅から漆黒へと色を変えている。
「あたしも……鷹斗のを飲みながら、イっちゃった」
くすっ、と悪戯っぽく笑い、俺にしなだれかかる。
俺は、ミアの軽い体すら支えきれず、そのまま仰向けにベッドに横たわってしまった。
ミアが、そんな俺の胸にすりすりと頬を寄せてくる。
「今日は、お疲れさま……」
そんな声をぼんやりと聞きながら、俺は、ゆっくりと眠りの中に沈んでいった。
「鷹斗……寝ちゃった?」
ささやくような声が、ホテルの部屋に、響いた。
鷹斗の返事はない。
ゆっくりと、全裸のままの小さな吸血鬼が、ほっそりとした上体を起こした。
今は漆黒の瞳が、若々しく精悍な鷹斗の顔を見下ろす。
鷹斗の、右のこめかみから頬にかけて、白い傷痕が走っている。
ダンピールの第八機密執行者――ユーリー・グロボフとの戦いの中で負った傷だ。
他にも、無数の小さな傷が、鷹斗の体には、ある。
ここ一年のうちに負った、ヒトならぬモノと戦い、生き延びてきた代償の数々。
それらに目をやってから、ミアは、再び鷹斗の顔に視線を戻した。
「また、頼っちゃってる……」
ぽつん、とミアはつぶやいた。
「そんなつもりじゃないはずなのに、あたし……」
その奥に、狂おしい赤い炎を秘めた、黒い双眸。
それが、じっと、鷹斗の額を見据える。
「でも……いつか……あたし、また……」
何かを恐れるような小さな声で言いながら、鷹斗の額に額を寄せる。
鷹斗の頭を抱えるようにして、額と額を触れ合わせ、目を閉じる。
「その時は、お願いね……鷹斗……」
そして、ミアは、軽く、鷹斗の唇に口付けした。
「あなただけが、頼りなの……」
そう言って、ミアは、鷹斗が待つはずの昏い夢に、自らを重ね合わせていった。
朝、時間ギリギリにチェックアウトした。
ミアが、フロントに金を払いながら、係の目を見つめている。
係は、どこか夢見るような目で、ミアの差し出す金を受け取っていた。
あまり良いことではないが、仕方ないだろう。俺達に関する記憶は、できるだけ残しておきたくない。
それに、どう見ても十代半ばの外人らしき少女と、二十歳そこそこの男の二人連れなどという組み合わせが、警察などの余計な関心を引くのも厄介だ。
理屈や現実に合わないことを信じさせるのならともかく、少し俺達の印象を違うものにするだけなら、ミアにも、暗示を受ける側にも、さして負担はかからないらしい。
それでも……人の心を操るという行為に対する忌避感は、拭いがたいものがある。
「お待たせ」
「ああ」
滑らかな足取りでこちらに歩み寄るミアにそう返事をした、二人で並んでビジネスホテルを出る。
空は、今日もどんよりと曇っていた。
こんな天気が続けば、今年は冷夏かもしれない。
日の光が強くないというのはミアにとってはありがたいことかもしれないが、雨だって吸血鬼にとっては日光と同じくらいに不快なものらしい。
難儀なものだな、と考えながら、自動車が八台も停まれば一杯になるであろう小さな駐車場に入り、停めていたバイクに歩み寄る。
「!」
危険な気配と、重いエンジン音に、振り向いた。
見覚えのあるピックアップ4WDが、向かいの路肩からこの駐車場へと侵入してくるところだった。
ぎゅわっ! という激しい音と、ゴムの焦げる匂いを撒き散らしながら、4WDが、車体を半回転させて急停車した。
俺のバイクの、すぐ向こう。
そこに停まったごつい車体から、のっそりと、巨大な影が姿を現した。
「師匠!」
俺の叫びに、隣に立つミアが、その小さな体を緊張させる。
葛城修三。
身長二メートルを超す巨体に、太い胴体と四肢。ぼろぼろのジーンズとモスグリーンのTシャツは、内側にある筋肉の圧力ではちきれそうに見える。
そんな師匠と、バイクを挟んで対峙した。
「探したぜ……」
師匠が、その岩を削ったような顔に笑みを浮かべ、言った。
が、その小さな目は、笑っていない。
「くどくど小難しい話ァ、抜きにするぜ」
言いながら、師匠は、右手で、俺のバイクのハンドルを握った。
まるで、俺の逃走を阻むように。
いや、今の師匠は、確かに、敵を前にした時と同じ緊張感を、その体から漂わせている。
師匠の目が、俺と、そして、いつも通りの黒い服をまとったミアの間を、往復した。
「そいつは、“カインの花嫁”だな?」
「……!」
俺もミアも、何も言わなかった。
ただ、一瞬、僅かに身じろぎしたに過ぎない。
しかし、それだけで、師匠にとっては充分だった。
ぶん!
うなりをあげて、巨大な影が、俺の体をかすめた。
一瞬、師匠が、バイクを飛び越えて襲いかかってきたのかと思ったが、そうではなかった。
師匠が、俺のバイクを放り投げたのだ。
さすがに反作用があるので、師匠の次の踏み込みは普段より数瞬遅れたが、それでも、今の投擲は、俺とミアの連携を崩すのに充分だった。
バイクの車体をかわして左右に跳ぶ、俺とミア。
そのうち、師匠は、ミアに向かって跳躍していた。
まさに、兎に飛びかかる虎か何かを思わせる、その圧倒的な動き。
がぎゃん! という激しい音が、他の全ての音をかき消す。
師匠が投げた俺のバイクが、駐車してあった他の乗用車の上に落ちた音だ。
「ミアっ!」
叫んで、俺が身を翻した時には、ミアと師匠の体が衝突していた。
ミアは――まるで、弾かれたように後方に吹っ飛んでいた。
右目を押さえた右手の指の透き間から、鮮やかな赤い血が飛び散っている。
師匠の、血に濡れた右手の指を見るまでもない。鉤状に曲げられた人差し指と中指が、ミアの右目をえぐったのだ。
「師匠っ!」
自分でも驚くほど大きな声をあげながら、俺は、ミアに追いすがろうとする師匠に飛び蹴りを放っていた。
人を殺すだけの力を乗せた右の爪先を、師匠の延髄に――
「ぬっ!」
インパクトの一瞬前に師匠は振り返り、俺の蹴りを額で受け止めた。
ごっ!
かつて経験したことのないような重いショックとともに、俺は、先程のミアと同じように後方に飛ばされていた。
師匠は、蹴りの衝撃を全てその太い首で吸収した上、さらにそれを頭突きで弾き返したのだ。
辛うじて両足で着地しながら、俺は、戦慄していた。
「驚いたな。お前が、ンな声出すなんてよ」
そう言う師匠の額が割れ、血が顔を伝う。
こんな出血、師匠にとっては、ダメージでも何でもないだろう。事実、師匠の口調は普段と全く変わらない。
一方ミアは、地面にうずくまり、右手で右目を押さえたままだ。
苦痛で動けないのでなく、眼球が再生するまで、余計な動きをするまいと考えているのだろう。目の前の人間が、片目のままで対抗できるような相手ではないと見切ったのだ。
「どうして、お前、吸血鬼なんかとつるんでんだ?」
「……」
師匠の問いに、俺は答えない。
ミアの右目の視力が回復するまで、時間を稼がなくては……。
が、師匠には、俺の思惑なんてお見通しなのだろう。それを承知で、ミアが戦線に復帰するまで、俺と話をするつもりなのだ。
「どうしてもこうしてもねぇか。あんなかわいこちゃんじゃな」
「……」
「ま、俺だって、馬に蹴られるのは御免だし、本当はそっとしといてやりたい気持ちもあるンだけどよ……」
すっ、と師匠の目が、細まった。
背骨がそのまま氷柱になったような感覚が、俺を硬直させる。
今、師匠が動いたら――俺は、何もできない。
紙で作られた人形よりたやすく、俺は完膚なきまでに破壊されてしまうだろう。
だが、真に恐怖と呼ぶべきものは、その次に来た。
「夕子ちゃんは、どこに行ったんだ?」
気力が、瞬時に、萎えた。
ぐらりと、視界が揺れる。
俺は――今、何をしてるんだ?
「夕子ちゃんは――お前達の件に巻き込まれたんじゃないのか?」
師匠の顔が、見えない。
急速に暗くなる視界の中、師匠の顔が、真っ黒な穴のようになる。
そして、俺は、鮮烈に死を意識した。
俺は、ここで殺されるのか――?
どうっ!
不意に、凄まじい音が、響く。
ぎゅわわわわわわっ!
「うおっ?」
師匠が、驚きの声をあげて飛びのいた。
師匠の4WDが、俺と師匠の間に強引に割って入る。
運転席には――誰もいない。
「鷹斗! 早く乗って!」
ドアを開け、俺にそう叫んだのは、ミアだった。座高が低過ぎて外からは見えなかったのだ。
その顔は未だ鮮血に濡れているが、右目は元に戻っている。
俺は、運転席に座るミアの上を這うような格好で、助手席に頭を突っ込んだ。
俺の足がまだ膝に乗ってる状態で、ミアは、ドアを閉めて4WDを発進させた。
どうにか、きちんと助手席に座ると、師匠がサイドミラーに写っていた。
何をするでもなく、じっとこちらを見ている。
その顔に浮かぶ表情は、やはり判然としない。
だが、そんな師匠の姿も、加速する背景の中、すぐに見えなくなった。
「もう、ぜんぜん前が見えないわ」
ミアが、大きな運転席にだらしなく寝そべるような格好で、言った。こうしないとアクセルに足が届かないのだ。
全く前が見えてない状態で、それでもミアは、外の気配を察することだけで4WDを動かしている。
「運転、代わる」
「お願い」
路肩に数秒だけ停車し、席を入れ替わった。
アクセルを踏み込み、発車する。
「キー、差しっぱなしだったのか?」
「ううん。あの人とぶつかった時に、ちょっと拝借したの」
懐から白いレースのハンカチを取り出し、顔の血を拭いながら、ミアが俺の問いに答えた。
おそらく、例の銀の糸で絡め捕ったのだろう。師匠としても、いきなりポケットの中のキーを掏り取られるなんて思わなかったに違いない。
「……あれが、鷹斗の先生なわけ?」
「ああ……」
我ながら危なっかしい手つきで運転をしながら、俺は答えた。
「すごい人ね」
「ああ」
俺は、短い返事を返すことしかできない。
体が小刻みに震えている。
「……夕子さんのこと、言ってたけど」
「……」
「鷹斗が、罪を意識したりすることじゃないわ。それに、鷹斗は、充分すぎるほど苦しんだじゃない」
「ああ……」
それは、そうなのかもしれない。
だが、現に今、俺は師匠から逃げている。
俺は――
「俺は、夕子の両親に、きちんと告げるべきだったのかな……」
フロントガラスの向こうの、曇り空の下の街を見つめながら、俺は言った。
「それは……」
ミアが、何か言いかけて、黙る。
沈黙の中、獣の唸り声のようなエンジン音だけが、しばし響いた。
「あたしの立場だと、ちょっと答えにくいかな」
「そうだな。悪い」
そう。これは、俺の問題だ。
夕子の最期について、俺は、誰にどれだけのことを言うべきだったのか……。
多くのことを説明すればするほど、俺も、ミアも、そして説明を受けた人間も、高いリスクを背負うことになる。
吸血鬼について知り過ぎた人間は、吸血鬼たちに狙われることになるからだ。
そういう意味では、夕子の両親や友人たちに、詳しい話はできない。
中途半端な説明をするのは、その分だけ自分の罪の意識を軽くしようというだけのことで、それ以上の行為ではないかもしれないのだ。
それでも――夕子の両親や、笹宮や、他の友人や、そして師匠には、夕子の最期について、知る権利があるような気がする。
師匠は、夕子の母方の叔父だし、あいつのことを小さいころから可愛がっていたから――
「鷹斗」
赤信号に車を止めた俺に、ミアが話しかけた。
「どうすればよかったのか、なんてことは、今考えるのはやめましょうよ」
「……ああ」
「大事なのは、これからどうするか、でしょう?」
「そうだな」
俺は、頷いた。
「これから、どこに行くの?」
「――萌木氏に、相談しようかと思う」
「そうね。彼、相談相手としては頼りないけど……でも、何か新しい情報が入るかもしれないし」
「ああ」
そう返事をして、俺は、青信号に車を発進させた。
「けど、大丈夫かしらね? 彼が、あたし達を鷹斗のお師匠さんに売ろうとしたら、どうするの?」
ミアの声に、いささか意地悪な響きが混じる。
「そうするつもりだったら、とっくにそうしてたろう?」
「分からないわよ。状況が変わったのかもしれないじゃない」
「……」
「今回の件だって、裏には萌木緑郎がいるのかもしれないわよ」
俺は、しばし考えてから、口を開いた。
「だとしても……いや、だったら余計に、萌木氏には会わなくちゃならないだろう?」
「そうね」
ミアは、あっさり引き下がった。
「まあ、正直なところ、あたしは、さっきのことに彼が絡んでるとは思ってないけどね」
「どうしてだ?」
「だって、ちょっとやり方が雑すぎるもの」
ミアの遠慮の無い言い方に、俺は、ようやく、顔を緩ませることができた。
もちろん、苦笑いするなんて芸当、俺には無理な話だが。
そんな俺の変化を敏感に覚ってくれたのか、ミアが、俺の代わりのように、くすっと声をあげて笑う。
俺は、震えの止まった手でハンドルを握り直し、アクセルを強く踏み込んだ。
葛城修三は、待ち合わせの場所で、腕を組んで待ち続けていた。
小雨の降る中、傘を差そうともせず、たたずんでいる。
駅前の雑踏の中、その巨体は、一際、通行人たちの目を引いていた。
そんな修三に、やはり大きな灰色の影が、音も無く近付く。
修三よりはかすかに背が低いが、その肥満した体には、同程度の肉の量がある。
にもかかわらず、薄手のコートに包んだその男は、奇妙なほど見る者の意識に残らなかった。
「葛城さん」
「遅いぜ、男爵」
「申し訳ありません」
不機嫌そうな声を出す修三に、“男爵”と呼ばれたその男が、丁寧な物腰で頭を下げる。
第八機密機関の執行者、クルスニクのフォン・ヴァルヴァゾル。それが、男の名前だ。
「これでも、必死になって走って来たのですが」
「そうかい」
修三が、その小さな目を、フォン・ヴァルヴァゾルの顔に向ける。
長く伸びた濃褐色の髪と髭に覆われたその顔から、表情を窺い知ることは難しい。
「“花嫁”と接触したそうですね」
「ああ、噂どおり、可愛い面ァしてたぜ」
「しかし、彼女は吸血鬼です。それも最も危険な」
フォン・ヴァルヴァゾルが、修三の軽口を封じるように言う。
「分かってるよ、ンなこたァ」
「……で、どうでした?」
「片目と引き換えに、車を盗られた」
「それは、何かの比喩ですか? 日本の諺とか」
フォン・ヴァルヴァゾルが、笑いもせずに、言った。
「言った通りの意味さ。見かけによらず、手癖の悪い嬢ちゃんだぜ」
「それは、ご愁傷様です」
フォン・ヴァルヴァゾルは、慇懃な態度を崩さない。
「けど……攻略は、噂ほど難しかねェかもな」
初めて、修三の口元に、笑みが浮かんだ。
虎のような、羆のような笑み。
発達した犬歯が、唇の端からのぞいている。
「と、言いますと?」
「普通、吸血鬼を相手にする奴は、出来る奴であればあるほど、真っ直ぐに心臓を狙う」
「はい」
「普通の吸血鬼を相手なら、それでいいんだ。奴等を相手に持久戦を仕掛けるくらい、バカな話はねェからな」
「はい」
フォン・ヴァルヴァゾルの態度は、先達の研究成果を聞く学者のように、物静かな関心に満ちている。
「けどよ、“花嫁”相手にそれは逆効果だ。あの小っこい体には、何百年分の戦闘データがぎっしり詰まってる」
「その通りです。その意味では、“花嫁”の動きは、最強と呼ぶにふさわしいものかもしれません」
「しかし、だ、洗練され、完成されているほど、バランスが崩れた時の影響は致命的になる」
修三の目に、普段は滅多に人に見せない光が浮かんだ。
老獪な策士の目だ。
それを、フォン・ヴァルヴァゾルの針のような視線が見つめている。
「確かに、普通の吸血鬼であれば、視覚を奪われた程度では、戦闘能力に大きな差は生じませんね」
「ああ。だが、あいつの場合は、片目を潰しただけで、一気に動きが悪くなった。目を逸らしても不安が無いくらいにな」
「なるほど」
「まあ、油断し過ぎたら、車を盗まれるくらいじゃ済まねえかもしれないが……」
再び、修三は、顔をしかめた。
「理想は、脳だな。脳さえ殺せば、あいつは並の吸血鬼と大して変わらなくなるだろうよ」
「それだって、脅威であることには変わらないと思いますが」
「お前さんがそれを言うのかよ」
「……」
修三の言葉に、しかし、フォン・ヴァルヴァゾルは何も答えない。
「で、どうなんだ? 俺はテストに合格したのか?」
修三が、口調を改め、言った。
「テスト?」
「ああ。俺が、共に戦うに足る人間なのかどうか、試したかったんじゃないのか?」
「それは、大変な誤解です。私達の方こそ、葛城さんの助力を切に願っているのですから」
感情のこもっていないフォン・ヴァルヴァゾルの言葉に、修三は、ふん、と太い鼻息を吹いた。
「ま、いいさ。お互い、無条件に人を信用するほど、初心じゃねェよなあ」
「……」
フォン・ヴァルヴァゾルは、やはり、何も答えない。
そして二人の巨漢は、小雨の中を、並んで歩きだした。