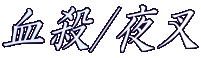
第一章
![]()
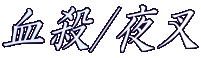
第一章
珍しく晴れた初夏の夜。
高いビルの谷間で、俺とミアは、そいつと対峙した。
ヴァンピール――英語読みではヴァンパイアだ。
それは、スーツを着た、長身の中年男の姿をしていた。
両目が、濁った赤い色に光っている。牙のはみ出た口は野獣のようだ。
「――吸血衝動に屈しきっているわ」
俺の隣に立つミアが、ほんのわずかに同情めいた響きを、その言葉ににじませる。
ヴァンピールは、こちらを威嚇するように、かっと赤い口を開いた。
その目には、狂おしいまでの餓えがある。
体の腐敗が進行していないというだけで、本質的には、“なりそこない”であるモロイと同じだ。
典型的な、“なりたて”のヴァンピールである。
あのアパートを出て、そしてこの一年あまり、俺とミアが斃してきた手合いだ。
ノインテーター。
それが、この連中の支配者らしい。
ミアの話だと、強力な力を備えた吸血鬼だという。
そいつが、自ら生み育てた吸血鬼を使い、ミアを狙っているのだ。
すでに十人以上のヴァンピールと、それ以上の数のモロイを、俺は、ミアとともに滅ぼしてきた。
そして、目の前のこいつも、最後ではないだろう。
銀の篭手を嵌めた右手を肩の高さに構え、人差し指と中指を突き出して鉤状に曲げる。
ミアも、隣で、銀の糸を繰り出す腕輪の安全装置を解除しているはずだ。
「ぎあッ!」
奇妙な声をあげ、ヴァンピールが地を蹴った。
ミアより半歩前に出ている俺に、一直線に疾走する。
凄まじい勢いだが、あまりにも直線的だ。
相手の両の鉤爪をかわすべく、軽く身をひねって踏み込む。
正拳突きの要領で心臓を狙った俺の一撃を、ヴァンピールは、真上に跳躍してかわした。
無駄の多い動きではあるが、その身体能力は侮れない。
ひゅん、と頭上で何かが風を切る音がした。
「げッ!」
空中で銀の糸に絡み取られ、ヴァンピールが無様にのたうつ。
そいつは、大きくバランスを崩し、右肩から地面に落下し、ごろごろと転がった。
無表情に、ミアが糸を手繰る。
ぎいいぃっ、と糸が一瞬唸り、転がるヴァンピールの右腕と右脚が千切れ飛んだ。
溢れる血の匂いに、無意識に眉を寄せながら、動きの止まったそいつに迫る。
その時――
「上!」
俺は、気配を感じ、反射的に叫んでいた。
頭上のビルの窓を突き破り、新たに二つの影が、俺達に襲いかかってきたのだ。
一度に三体は初めてだ。
「くっ……!」
ミアが、血にまみれた糸を腕輪に収納し、跳びすさった。
一瞬前までミアのいた場所に、ニ体のヴァンピールが着地する。
そいつらは、狙いを、ミア一人に絞っていた。
距離が、あまりに詰まっている。十歩前後の距離から糸を繰り出すミアにとっては、不利な間合いだ。
禍々しく伸びた鉤爪が、ミアの小さな体を引き裂こうと迫る。
俺は、手負いのヴァンピールをひとまず無視し、手近な新手に後ろから襲いかかった。
俺の意図を察したミアが、もう一人のヴァンピールに向き直る。
これで、一対一。
俺は、やはりスーツをまとったそのヴァンピールの襟首を、後ろから右手で掴んだ。
が、ヴァンピールに力で対抗するのは難しい。
俺は、そいつの力を誘導するべく、思いきり押した。
もう片方のヴァンピールに飛び掛ったミアをかすめるようにしながら、そいつを、ひたすらに押す。
そして、左手で相手の左肩の後ろを引くようにして、奴が想定していたであろう軌道を、わずかに左方向に逸らした。
奴が、俺の意図に気付いた時には、手遅れだ。
がつッ!
奴の顔面を、ビルの壁面に叩きつけた。
頭蓋に、亀裂くらいは入ったはずだ。
それが致命傷にならなくとも、動きは鈍る。
「げはぁッ!」
口から赤い血を撒き散らしながら、俺の相手が、バックハンドの要領で右の拳を繰り出す。
俺は、膝を曲げ、頭を沈めてそれを避けた。
頭上を奴の拳が通過した次の瞬間、たわめていた体を元に戻す。
そのまま、籠手を嵌めた右の掌底で奴の顎を打ち上げた。
堅い手ごたえ。
奴の顔が、真上を向く。
脳への震動と、頚椎への負担で、奴の反応速度はさらに鈍っているはずだ。
不意を打つか、動きを止めなければ、ヴァンピールの唯一の弱点を攻めることは難しい。
すなわち、心臓を――
「しッ!」
無意識に呼気を吐きながら、俺は、奴の襟首を左手で掴み、引き寄せた。
そして、カウンターで右の貫手を放つ。
距離が足りない分、体をひねるように回転させ、右手に力を乗せた。
ぞぶっ!
どうしても慣れることのできない、その感触。
それを振り切るように右手を捻り、さらに深く、銀の篭手に包まれた指先をねじり込む。
「げ――はあああああああああぁ!」
奴は、口から大量の血を吐き出した。
胸元で、それを受け止める。
ぞっとするような、腐った鉄の匂い。
最後の力を振り絞り、奴が、俺の右手を、両手で自らの体から引き抜こうとする。
俺は、右手を力一杯に握り締め、奴の心臓を潰した。
「――!」
最期のそれは、もはや言葉にならなかった。
奴の体が、熱の無い炎に包まれる。
右手にまとわりつく嫌な感触が、嘘のように消え失せた。
奴が、灰となったのだ。
「ミア!」
振り向くと、ミアが、ちょうど相手を銀の糸で寸断しているところだった。
肉片が、次々と炎に包まれ、灰となる。
一対一なら、並のヴァンピールなど、ミアの敵ではない。
ミアが、繰り出していた銀の糸を、腕輪に収納する。
「しゃああああああッ!」
奇怪な叫びが、夜気を切り裂いた。
右腕と右脚を切断された最初のヴァンピールが、残った脚でミア目掛け跳躍したのだ。
「くっ――!」
俺は、そいつ目掛け走った。
ミアは、動かない。
そして――ヴァンピールの体が、胸のところで上下二つに割れた。
「があッ……!」
二つに分かれた奴の体と、そして、地面に転がっていた右腕と右脚が、炎に包まれる。
「……大丈夫よ。きちんと仕掛けは残しておいたわ」
ミアが、灰に還っていくヴァンピールから俺に視線を移し、言った。
左右五本ずつ、計十本ある糸のうち一本を、気付かれないように奴に絡めていたということだろう。
うかつに動けばその勢いで自らを殺す――あまりにも単純な死の罠だ。
暗い灰色の風景の底で、静寂が、戻る。
「鷹斗、怪我は?」
「無い」
「よかった」
ミアが、息をつく。
「……一度に三人だったんで、戸惑ったけどな」
「でも、あたし達の敵ではなかったわ」
どこか哀しげに、ミアが言った。
すでに、灰は夜風に吹かれ、舞い散っている。
奴らの血を含め、何の痕跡も、この路地裏には残っていない。
「萌木緑郎に、連絡しなきゃね」
「ああ」
ミアの言葉に、俺は短く返事をした。
ミアが言うのは、情報屋である萌木氏に、今回襲撃してきた吸血鬼のことを教える、ということだ。
場合によっては、萌木氏が用意した顔写真から、ヴァンピールだった連中を特定する。
そのことで、萌木氏は、俺達にかなりの金額を支払ってくれるのだ。
出所不明の金だ。吸血鬼を倒したことに対し、どこからか報酬が出ているらしい。
その報酬を求めて、吸血鬼を退治することを生業とする者がいるということを、すでに俺は知っていた。
それこそが、吸血鬼ハンターと呼ばれる連中である。
「……不満そうね」
からかうような響きをその幼い声に含ませて、ミアが言った。
「そういうわけじゃないけど……やっぱり、釈然としないな」
「どうして?」
「俺は、ハンターじゃないからな。もらう謂れの無い金だ」
俺とミアのしてることは、正当防衛だ。賞金目当てのハンティングなどではない。
そもそも、ミアからして、狩られる立場の吸血鬼なのだ。
それに――
「でも、鷹斗がご飯を食べていくためには、お金が必要よ」
「金なら、まだ貯金が残ってる」
「それだって、いつまでももつものじゃないでしょう? それに、鷹斗ってば、あたしが暗示を使おうとすると、ひどく嫌がるじゃない」
「……」
俺は、二の句が継げない。まさしくミアの言う通りなのだ。
「さ、行きましょう」
「ああ」
素直に返事をして、ミアとともにこの路地裏から出て行く。
淀んだ夜気の中、頭上の月が、朧に滲んでいるように見えた。
「多いなあ……」
ミアと鷹斗からの第一報を受け取った萌木緑郎は、雑然とした事務所の中で、受話器を置きながら、言った。
「三人ってのは、ちょっと多すぎだよね。吸血鬼の人達って、そんなふうに群れたりしないもんじゃないの?」
緑郎のほかに事務所にいるのは、冬条綺羅だけだ。ラフなTシャツに細身のジーンズという姿で、何をするでもなく、パイプ椅子に座っている。
「第八の皆さんもおおわらわだよね。男爵さんなんか、寝る暇も無いんじゃないかな」
「男爵?」
綺羅が、短く聞き返す。
「オスカー・フォン・ヴァルヴァゾル。通称“男爵”。第八機密機関が誇るクルスニク。生粋の吸血鬼ハンターだよん」
年代物のメモ帳を片手に、緑郎が答える。
「機関の中じゃあナンバースリーってことになってるけど、今年の日本は吸血鬼の当たり年だから、極東担当の彼は、もうすぐレコードを塗り替えちゃうかもしんない」
「……その人が、ミアさんや鷹斗君の敵になるんですか?」
「鉢合わせしないように、気を使ってるつもりなんだけどねー」
緑郎は、ふわ〜、と大きなあくびをした。
「ミアちゃん争奪戦がおさまんない限り、心配の種は尽きないよね。何しろあの二人が台風の目ん玉だし」
「あたしも、こう世間が騒がしいとやりにくいですよ」
綺羅は、小さくため息をついた。
「舞台から引っ込むには、ちょっとミアちゃんの件、深入りし過ぎちゃった感じですしねー」
「隠居を考えるような年じゃないでしょ」
「……女に不用意に年齢の話をする人は、嫌われますよ」
綺羅が、鈍い赤色の瞳で、緑郎をにらむ。
「……綺羅ちゃんさあ」
しばらくの沈黙の後、普段の軽薄そうな顔のまま、緑郎が言った。
「ウチの人になんない?」
「あたしを、お妾さんにしようっていうつもりですか?」
「男の夢はハーレムエンド。これ世界の常識」
にんまりと、緑郎が笑う。
「まったく……いくら彼女さんにいいつけても、緑郎さんを喜ばせるだけなんだもんなあ」
そう言いながら、綺羅は、しなやかな動作で立ち上がった。
「で、どなの?」
「あたしは、吸血鬼探偵なんて俗っぽいものになるつもりはないし、緑郎さんの二号さんになるつもりもありません」
「“二号さん”って、いつの言葉よ」
緑郎が、呆れたように言う。
「それに、自分の身の振り方を考える時間は、幸いたっぷりありますから」
「……でも、今は、落ち着いて考えられる状況じゃないでしょ?」
緑郎が、机に上半身を突っ伏すような姿勢になって、綺羅の方を見た。雑然とした机の上で、書類の山が崩れかかる。
「“破壊屋”の葛城さんと連絡が取れなくて、まいってるんでしょう」
綺羅が、緑郎に向き直り、言った。
「いやー、あの人は、連絡が取れてもオレなんかの言うこと、半分も聞いてくんないし」
「あたしだったら、手駒にはちょうどいいって思ってるんですか?」
「そこまで自惚れてないよ。ただ、綺羅ちゃんとは利害が一致しやすいかなー、と思ってるだけ」
「ふうん……」
綺羅が、緑郎を値踏みするような目で見る。
「で、緑郎さんは、あたしをどっちにけしかけたいんです? 第八機密機関の方ですか? それとも、ノインテーター?」
「……」
緑郎は、しばし黙ってから、言った。
「ノインテーターの動きの方が、ヤバい」
「……」
「直接アタマを狙われちゃってる。正直、大ピンチ」
「で、緑郎さんは、あたしに助けてほしいんですね?」
にっこりと微笑みながら、綺羅が言う。
「……うん」
緑郎は、まるで子供のように素直な調子で、頷いた。
「報酬は? 冷凍血液一年分なんてのはナシですよ」
「オレが、全身全霊を傾けて綺羅ちゃんを守るってのは、どう? もちろん前払いで」
「……いいですね、それ」
綺羅が、意外なほど穏やかな声で、言う。
「けどですねえ、あたしは、別なのがいいです」
「あら、やっぱり?」
「はい。えっと……これからもずっと、あたしのお友達でいてください、ってのはどうですか?」
「……」
緑郎の顔から、一瞬、表情が消える。
そして、緑郎は、いつもの軽薄な笑顔を取り戻し、言った。
「おっけーだよん。もちろん前払いでね」
「契約成立ですね」
綺羅は、再びパイプ椅子に座った。
「じゃあ、緑郎さんが集めたあいつに関する情報、ありったけ見せてください」
「ほいほい」
返事をして、緑郎は、机の上の発掘作業を開始した。
赤い血を目にした夜は、ミアが、いつも以上に高ぶるということに、俺は気付いていた。
もちろん、俺も、ミアも、そのことにはあえて触れない。
その夜――と言うよりも、明け方。
ビジネスホテルの一室で、俺とミアは、全裸の体を絡ませあっていた。
いつも以上に冷たく感じられる肌に、指を這わせる。
「あっ……はぁっ……」
ミアが、冷たい唇から、熱い吐息を漏らす。
それは、すでに情欲に濡れていた。
ミアの高ぶりが、俺にもすぐに伝染し、股間のものを熱くたぎらせる。
俺は、その部分をミアの小さなヒップに押し付けるように、立ったまま、後ろから彼女の細い体を抱き締めていた。
俺の肩よりもなお低い位置にある、ミアの頭。
少し癖のある艶やかなその黒髪は、甘く、蠱惑的な香りがした。
その香りにさらに肉棒を疼かせながら、ミアの体をまさぐる。
瑞々しい弾力のある、白い肌。
膨らみかけたまま成長を止めた乳房を、優しく撫でさする。
「はぁっ……鷹斗……きもちいい……」
うっとりとした声で、ミアが快感を訴える。
俺は、小さな貝殻を思わせるミアの耳を甘く噛みながら、白い乳房の頂点にある桃色の突起をつまんだ。
「きゃっ……!」
指を細かく震わせ、その可愛らしい器官に振動を送り込む。
小粒な乳首が、ぷっくりと勃起していく。
「あぁ……だめ……だめよ……あぁっ……」
幼い声が、艶っぽい喘ぎを紡ぐ。
そのギャップに、俺は、自然と息が荒くなってしまうほどに興奮していた。
年端のいかない少女の体を、性の衝動の赴くままに嬲り、玩んでいるという罪悪感が、さらに俺の血をたぎらせる。
ミアとの関係は――ねっとりと暗い愉悦に満ちていた。
「お、おねがい……それ以上は、だめ……あうっ……!」
尖った乳首を引っ張るようにして刺激すると、ミアは、その体からかくっと力を抜いてしまった。
飾り気のない壁紙の張られた壁面に両手を突き、はぁはぁと喘ぐ。
「だめよ、これ以上は……感じ過ぎちゃう……」
額を壁に押し付けるような格好でそう言うミアの体を、俺は、なおも執拗に愛撫した。
腋から脇腹にかけてや、肩甲骨の下のあたり、ヒップのささやかな膨らみ、太腿の内側……そのいたいけな体に隠された性感帯を、指先で刺激していく。
「だめっ……! だめって言ってるのに……あっ……きゃんっ……!」
ミアのしなやかな体がうねり、もだえる。
俺は、横からミアの体を抱えるような形で、左手で乳房を揉み、そして、後ろから彼女の足の間に右手を差し込んだ。
くちゅ……っ。
「ああっ……!」
愛液で充分すぎるほどに潤んだ靡肉は、指先が火傷するのではないかと思うほどに、熱かった。
愛しげに絡み付いてくる秘裂に指を深く食い込ませ、さらに奥をまさぐる。
「ひっ! あうっ……! だめっ……! だめよ! だめぇ!」
ひくひくと背中を震わせながら、ミアが高い声で言う。
「あああっ……もう、限界……い、いく……いっちゃうわ……!」
絶頂を目前にして、ミアは、その官能の奔流に歯を食いしばって耐えている。
俺は、むきになったように両手を動かし、左右の乳房を揉みしだき、熱い秘肉をかき回した。
「いやっ……指じゃ……指じゃいや……! 指なんかでいきたくない……っ! 鷹斗の……鷹斗のオチンチンがいいのっ!」
その言葉に、俺は、手を動かすのをやめた。
「ひうっ……」
イキそこねたのか、ミアが、奇妙な声を漏らす。
そして、恨みっぽい流し目で、俺の顔をにらんだ。
「ひどいわ、鷹斗……あたしに、いやらしい事を言わせて楽しんでるんでしょう……?」
赤く染まった瞳をきらきらと濡れ光らせながら、ミアが言った。
「いいわよ……あたし、そういう女だもの……」
拗ねるような、ミアの口調。
「いや、その……」
「ね、お願い。このまま……このまま後ろからして……」
ミアが、壁に両手をついたまま、さらに腰を後ろに突き出す。
俺は、つまらない言い訳をするのをやめ、ミアの後ろに回り、その細いウェストを両手で抱えた。
いきりたった肉棒で、熱くぬかるんだ幼いクレヴァスに狙いを定める。
「ああ……早く……早く入れて……」
ぬるりとした、粘膜の感覚。
それを、亀頭から陰茎の根元まで、ペニス全体で味わうように、挿入する。
「あああああああああああああああああっ!」
ミアの白い背中が、弓なりに反った。
「あっ……あうっ……ああぁ……」
ひくん、ひくん、とミアの体が震える。
どうやら、軽い絶頂に達してしまったらしい。
そのまま崩れそうになるその小さな体を、腰に回した両手で支え、大きく、腰を動かす。
「ああっ……あうっ……あうん……ああん……」
俺の抽送に合わせ、ミアが、甘い声で鳴く。
ミアの体を出入りする陰茎は愛液で濡れ光り、てらてらと照明を反射した。
次第に抽送のリズムを速めながら、ミアの膣内の甘美な感触を味わう。
「あっ、あんっ、あう、あん、あん、あん、あんっ……!」
ミアが、俺の動きに合わせてせわしなく喘ぐ。
その声は、性感の高ぶりに比例するように、徐々にトーンが高くなっていった。
脳に、股間に、そして全身に熱い血液が巡るのを感じながら、腰を前後させ、時に回すように動かす。
「ひあうっ! す、すごい……!」
ミアは、俺の動き一つ一つに、敏感に反応した。
「すごいの……鷹斗のが、あたしの中で、暴れて……あああああっ!」
きゅうううん、とミアの膣肉が、収縮した。
「だめっ……! また、イっちゃう……!」
ぞわぞわぞわっ、と膣内粘膜がざわめき、俺のペニスをさらに奥へと誘い込むように動く。
俺は、その刺激に早くも精を漏らしそうになりながら、抽送を続けた。
「ああっ! そんな……またっ! またイクっ! あう……ああんっ!」
さらに膨張した俺のペニスが、ミアの一番奥を小突いている。
ミアは、壁に爪を立てるようにして身悶えた。
その可愛らしい口元から、白い犬歯がのぞいているように見える。
「ああん! イクわっ! イクっ! こ、こんなに……ああんっ! あああああ!」
俺が腰を一突きするごとに、ミアは、絶頂を味わっているようだ。
連続する快感の小爆発を、その幼い体に似合わない貪欲さで受け止めながら、さらに次の絶頂を誘い込むように、体をうねらせ、ヒップをくねらせる。
俺は、いつしか歯を食いしばりながら、腰を動かし続けていた。
「あああっ! すごい……! ああん……! す、すてき……あうっ! ひああん! またっ! またイっちゃうっ! イクっ! イクっ! イクうっ!」
ミアが絶頂を訴えるたびに、膣が締まる。
何度も何度も断続的に繰り返される強烈な締め付けは、俺のペニスを食い千切らんばかりだ。
血が煮えたぎるような熱い愉悦と、神経が削られるような冴え冴えとした性感。
それらが混じり合った圧倒的な快楽が、俺を一気に限界以上に追い詰める。
その限界をはるかに超えた刺激に、体がきちんと反応できなかった数秒の間、俺は、呼吸を忘れるほどの快感を味わい続けた。
そして――
「くっ……!」
俺は、痛いくらいに高まった性感に思わず声を上げた。
次の瞬間、まるで、膣肉に搾り取られるように、凄まじい勢いで射精する。
びゅううううううううううううううー……っ!
「きゃうううううううううううううううううう!」
ミアが、一際高い絶頂の声を上げる。
その声を聞きながら、ミアのいたいけな体の中に、精を注ぎ込み続ける。
脳を灼く白い閃光のような快感。
そのあまりの凄まじさに茫然となりながら、俺は、ミアの声とは違う、何かが裂けるような音を、聞いた。
快感一色に染められていた五感が、次第に戻ってきた。
体から弾き飛ばされ、遊離していた意識が、再び肉体に帰ってきたような感覚。
「は……あああぁっ」
忘れていた呼吸を思い出し、大きく息をつく。
ミアは、両足と共に両手まで床について、はぁはぁと息を整えていた。
壁を、見る。
ホテルの壁には、深い傷が、縦に何条も刻まれていた。
ミアの爪の跡だ。
ミアがこの体位で俺を求めた意味を、ぼんやりと理解する。
背筋に走る、戦慄。
が、その感触は、なぜかひどく甘く、そして危険なほどに心地よく感じられた。