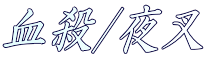
序章
![]()
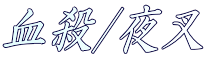
序章
高校に入学してすぐ、両親が死んだ。
交通事故だった。乗用車に乗っている時に、大きなトラックと正面衝突して、二人とも即死だったという。
葬式は、死んだ父親にとっては従兄弟にあたる夕子の親父さんが取りしきった。
茫然としている間に納骨が終わり、数少ない親類達は、俺のことを気遣いながら、それぞれの家に帰っていった。
その夜のことだ。
師匠が、俺を公園に連れて行った。
数年間、葛城流柔拳術を習った、その公園だ。
丸い月が、師匠の頭上で輝いていたことを、今もはっきり憶えている。
「鷹斗」
事故の報せを受け取ってからも、ずっと渇いたままだった俺の目を見ながら、師匠は言った。
「いい機会だから、言うぜ」
ただでさえ暗い公園の中、月明かりが逆光になって、師匠の表情は判然としなかった。
「人は、いつか死ぬ」
重く響く声に、俺は、しばらくしてから肯いた。
「俺も、お前も、いつかは死ぬ。いつかっていうのは、この次の瞬間かもしれねえ」
「……はい」
「例えば、俺がその気になれば……今、ここで、お前を殺すことだってできる」
「はい」
そんなことを言う師匠の意図は分からなかったが、ともあれ、事実だったので、俺は肯いた。
「お前は、どんなふうに死にたい?」
「……」
俺は、しばらく考え込んだ。
晩春の夜気が、頬を撫でる。
「分かりません」
「分からない?」
師匠が聞き返す。
「まだ、死にたくありません」
俺は、言い方を変えた。
質問とは直接関係のない答えになってしまったが、それでも、正直な気持ちだった。
ざわざわと、夜の風が葉桜の枝を揺すっていたと思う。
師匠は――どんな顔をしていたのか、分からない。
鮮明なはずの記憶の中、師匠の顔だけが、切り取られたように真っ暗だ。
「人はいつか死ぬ。だが、死にたくない」
師匠が、言った。
「そうだよなァ」
ふっ、と師匠の声が、柔らかくなった。
「それで、充分なのかもしれねェよなァ」
一人、納得したような口振りで、師匠は言った。
俺は、どう答えていいか分からなかったんだと思う。
じっと、師匠と向かい合って、黙っていた。
月の光が、意外なほどくっきりと、地面に師匠の影を落としていた。
「ただよォ……それだけじゃあ、ちっとばかし寂しいような気もするわな」
「寂しい?」
師匠の口から、そんな言葉が出たのが意外で、俺は思わず聞き返してしまった。
「ああ」
「……」
「あのなあ、鷹斗」
「はい」
「お前さんの親御さんはな、お前さんのこと、すごく気にかけていたンだぜ」
さらに意外な言葉を、師匠が言った。
その時、自分の胸に、何か熱くて濡れたカタマリがあることに、不意に気付いたのだ。
ずっとずっと、俺の気管を圧し、塞いでいた何か。
俺は、何かに耐えた。
耐えきれないほどの何かに、必死に抗った。
それが何なのか、最近になるまで分からなかったが。
そして、本当はその時、耐えることも、抗う必要もなかったことを、最近になって俺は知った。
それから、師匠が――その時、かつてないほど優しい目で俺を見ていたことを、今、俺は思い出している。