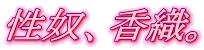
第六章
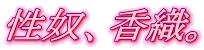
第六章
皆さん、ペニスとザーメンをなしではいられない体の、香織です。私の淫らな告白で、いっとき楽しんでいただければ、幸いです。
私は、あの満員電車の中での体験以来、ますますふしだらな女になってしまいました。
三日と間をおかずにいらっしゃる壬生田様のお相手を務めるだけでなく、壬生田様がお連れになる他のお客様にも体を開き、同時に何本もの肉棒に、全身を使って奉仕するようになったのです。
かつて、羽黒さんの奴隷として娼婦をしていた時にも、一度に二、三人のお相手をすることはありました。ですが、最近では、少なくとも五人、多い時には十人以上の方の相手を、一晩でしています。
そして、私は、穴という穴に熱く脈打つペニスを迎え入れ、煮えたぎった精液を流し込まれるたびに、歓喜の悲鳴を上げながら絶頂を極めるのです。
私は、もはや完全に男の方のための公衆精液便器でした。
濃厚なザーメンを体奥に注いでいただくためだけに生きている、卑しい淫乱肉奴隷です。
そんな私を、壬生田様は、これまで以上に可愛がってくださいました。
壬生田様は、私が他の殿方に抱かれるのを見るたびに興奮し、私への欲望を新たにするのだそうです。
もはや、私は、そんな壬生田様なしには――壬生田様の逞しいペニスなしには生きていけない女に成り果てていました。
壬生田様のペニスは他の誰のものよりも太く、男らしく、そして疲れを知らないのです。
たくさんの方々にさんざんに犯していただいた後、さらに朝まで壬生田様に抱いていただくと、気がおかしくなるほどにイキ続けてしまいます。
いえ、もう私は、とっくに狂っているのかもしれません。
そんな、常軌を逸した日々を送る私の心に、小さな刺のように刺さっているのが――夫である、宮倉皓一のことでした。
「壬生田様……お早うございます……」
私は、夫婦のダブルベッドで目を覚まされた壬生田様にそう言い、隆々と朝立ちをなさっているそのペニスに、うやうやしくキスをしました。
すでに、日は高く昇っています。
昨夜も、東の空が白むまで、繰り返し犯していただきました。私は、少し眠った後、心地よいけだるさの残る体で、壬生田様に朝一番の奉仕をするのです。
「はむ、んむむ、ちゅぶ、ちゅぷっ……んむむ、ちゅぶ、ちゅぶぶぶっ……」
他のお客様がいる時はなかなかできないような濃厚なフェラチオで、壬生田様のペニスを唾液まみれにします。
「ふうぅ……ああ、いいよ、香織クン……くうぅ、昨夜あんなに出したのに、もう出したくなるねぇ」
そう言いながら、壬生田様は、仰向けの姿勢のまま、私の髪を撫でてくださいました。
「ちゅむ、ちゅばばっ……どうぞ、ご遠慮なく、お好きな場所にお出しください……んちゅっ、んちゅちゅっ……はぁはぁ……」
私は、カーテンの隙間から漏れる日の光をヌラヌラと反射させる逞しい肉棒に、頬擦りしました。
「んはぁ……私の口マンコも、お尻マンコも……もちろんオマンコも……壬生田様のザーメンを飲み込みたくて、ウズウズしてるんです……ちゅっ、ちゅぶっ、ちゅぶぶっ……れろろろろっ」
「おっ、おっ、なんて舌使いだ……ふぅふぅ……ますますフェラテクに磨きがかかってるな?」
「れろれろ……んふっ、壬生田様に喜んでほしくて……んちゅっ、ちゅぶ、ちゅずずずずっ……ただそれだけです……ちゅぶ、ちゅぶっ、じゅぶぶ……」
私は、褒められて頬が熱くなるのを感じながら、口唇奉仕に没頭しました。
「ムフ、ムフフ……香織クンは本当に可愛いメス奴隷だよ……よし、今朝は、オマンコに中出ししてやろう」
「あぁ、嬉しい……香織のいやらしいオマンコに、壬生田様の朝一番の新鮮なミルクを注いでください……」
「よしよし……さあ、自分でワタシの腰にまたがるんだ」
「はい……!」
私は、声を弾ませながら、いそいそと壬生田様の腰をまたぎました。
金色のピアスに飾られたラビアは、壬生田様のペニスにキスをしたときから、すでに愛液に濡れています。
「し、失礼いたします……うくっ、んっ、くはあああっ……お、大きい……!」
私は、喜びに全身を震わせながら、熱く疼く膣壷に肉棒を根元まで迎え入れました。
粘膜と粘膜が、私の中でぴったりと重なります。
「あっ、あはあっ、気持ちイイ、気持ちイイですぅ〜」
私は、我慢できずに、そのまま腰を使い始めました。
「むうぅ……吸盤のように吸い付いてくるぞ……相変わらずの極上マンコだ……!」
「あ、あぁ〜ん、ありがとうございますぅ……んっ、んんっ、壬生田様の男らしいチンポにオマンコでご奉仕できて、香織は幸せですぅ……あううっ」
「ふうふう……くっ、ただセックスをするだけでこんなにいいとはな……」
壬生田様が、そうおっしゃいながら、さらにペニスを膨らませてくださいます。
私の女性器は、男性を喜ばせるための機能を増すために、すでに幾度となく手術を施されました。膣内を肉厚にして締まりを良くしたり、肉襞や柔突起を増やすための手術などを、です。
さらには、定期的に、色素の沈着を防いだり、愛液の分泌を促すようなお注射もしていただいています。
刺青も増えました。髑髏や女郎蜘蛛などの不気味な絵柄が、私が快楽に悶えるたびに、肌の上で蠢くようになっています。
処女膜の再生手術をしていただいたこともあります。新たになった処女膜を壬生田様のペニスに貫いていただいた時は、激痛と感動とが入り混じった快感に、そのまま失神してしまいました。
「あっ、あぁっ、すごいぃ……壬生田様のおちんぽ、子宮にガンガン当たってますぅ……うああっ、あひ、あひぃ……あン、あンあンあンあンっ! あはあぁ〜っ!」
私は、快楽に脳を痺れさせ、そのまま壬生田様の体の上に突っ伏してしまいました。
「んっ、んちゅっ、ちゅぶぶ……チュッ、チュッ……はぁはぁ……ああぁ……あひ、あひいぃ……んちゅっ、ぶちゅぅ〜っ」
私達は、どちらからともなく唇を求め合い、舌を絡ませ合いました。
その間も、私のお尻は、まるで別の生き物のように前後左右に動き、壬生田様のペニスを貪るのです。
「あっ、ああぁン、すごい、すごいですぅ……ハァハァ……オマンコっ、オマンコ感じちゃいます……ドスケベマンコ感じるぅ〜!」
「うううっ、な、何て締め付けだ……く、食いちぎられそうだ!」
壬生田様が、そう声を上げながら、下から腰を使ってくださいます。
「ひううっ! うぐっ、うあああっ! イイですっ、イイですぅ〜! あーっ! あーっ! オマンコいっぱいっ! オチンポでイッパイですぅ〜! あぁ〜! イイぃ〜!」
「ムフ、ムフッ、も、もう出るっ! ううっ、ザーメン出してやるっ!」
「あああ、出して! チンポミルク出してください! ザーメンミルクで、香織の子宮をイかせてくださいっ! あン、あぁン、あンあン! あひぃ〜ン!」
「うおおおっ、し、搾り取られる……ぐおおおおっ!」
壬生田様が、ひときわ大きくペニスを突き上げ、そのまま射精してくださいました。
「あぁーっ! イク、イク! チンポザーメンでイクうっ! ああああっ! オマンコいぐううううううぅ〜!」
びゆっ! びゅっ! という激しい迸りを膣奥に感じながら、私は、絶頂を極めました。
肉壷が、残った精液を吸い取ろうとするかのように、ペニスにぴったりと吸い付いたまま、ヒクッ、ヒクッ、と痙攣します。
「お、おおおっ……たまらん……香織クンのここは、最初から最後まで、最高だよ……」
「あぁ……嬉しいです、壬生田様ぁ……」
私は、感謝の言葉を口にしながら、チュッ、チュッ、と壬生田様の顔にキスをしました。
「ムフフフフ……しかし、こうしてベッドの上で普通にセックスしていると、まるで夫婦にでもなったみたいだな」
「そ、そんな……壬生田様の奥様だなんて……私……」
私は、壬生田様の言葉にはにかみながらも、ちくりと小さく心が痛むのを感じました。
「おやおや……まだ、旦那サンのことが忘れられないのかな?」
そう言いながら、壬生田様が、まるで嬲るように、私の頬を分厚い手で撫でます。
「あ、あの……も……申し訳ありません……私は、身も心も壬生田様の奴隷です……でも……」
「それ以前に、旦那サンの妻だというのか。ムフフ、香織クンは、そうでないとねぇ」
そう言いながら、壬生田様が、私の胸に手を移し、乳首に嵌まったピアスを、指先でいじくります。
「あっ、あふぅ……んっ……あうぅ……」
「香織クン……旦那サンに会いたいかね?」
「はぁはぁ……ハ、ハイ……んううっ……許してください……私、こんなに可愛がっていただいているのに……ま、まだ、夫に未練が……あううぅっ……」
このままの生活を続けていれば、いずれ、本当にセックスのことしか考えられない色情狂になってしまう――それは、予感というより、訪れることの確実な、未来の事実でした。
それならば、少しでも理性の残っている間に、一目なりとも夫に会い、できることなら謝罪の言葉を告げたい――
それは、快楽によって糖蜜浸けのようになった私の心の中の、唯一の人間らしい希望でした。
「ムフフ……会わせてあげてもいいんだよ」
「――えっ?」
私は、一瞬、自らの耳を疑いました。
「ま、まさか……壬生田様、夫の行方を知っているのですか?」
「知っているもなにも……実は、宮倉クンは、今、私のところで働いてくれているんだよ」
そう言いながら、壬生田様が、上体を起こしました。
「そ、そんな……」
私は、反射的にベッドから降り、床の上に土下座しました。
「お願いです、お願いです! どうか……どうか夫に会わせてください!」
自分でも思いもしなかったような悲痛な声が、私の喉から迸りました。
「ムフフ……宮倉クンは、ずいぶんと想われているんだねぇ」
そう言いながら、壬生田様が、ベッドの橋に腰掛け、私を見下ろします。
「どうか……どうか、香織の我が儘を聞いてください! その後で、どのような目にあわされても構いません! どうか一目だけでも……」
私は、壬生田様の足にすがりつきながら、懇願しました。
もし、このまま蹴りとばされたとしても、私は訴えをやめなかったでしょう。
ですが、壬生田様はそんなことはなさらず……代わりに、私の髪をそっと撫でました。
「香織クンの気持ちは分かったよ。なに、実は、宮倉クンの方で、キミに会うのをためらっていてねぇ……」
「あぁ……そ……そんな……」
私の目から、熱い涙が溢れ、頬を濡らしました。
でも、無理は無いのです。私がどんな女かを知れば、どんなに夫が優しくとも、再会を渋るでしょう。
それに、壬生田様は、私が今どのような状態なのかも、全て夫に話しているのに違いありません。
ですが、そのことで壬生田様を恨むのは筋違いです。全ては私のせい――私の自業自得なのですから。
「まあ、ワタシが説得すれば、宮倉クンも考えを変えてくれるかもしれんがねぇ……」
「あぁ……お願いします……お願いしますっ……! どうか……ううっ、どうか夫を……」
「ただ、説得をする前に、ひとつ香織クンの気持ちを確かめておきたくてね」
壬生田様が、私の顔を起こし、顔を寄せました。
「旦那サンに会うためなら、どんなことでもするかね?」
「は、はい……! はい! いたします! どんなことでもお申し付けください……!」
私は、夫に会いたい一心でそう言い、壬生田様の足に何度も口付けしました。
「ようし……香織クンの覚悟を確かめてさせてもらおう」
壬生田様は、そうおっしゃいながら、口元を歪めて笑いました。
それは、距離にすれば、大したものではありませんでした。
壬生田様のリムジンを降り、ホテルの駐車場から、エレベーターに乗り、ラウンジや廊下を横切り、そして、目的地のホールの控え室まで……。
その距離を、私は、四つん這いで歩いたのです。
私の首には、大きめの真っ赤な首輪が嵌められています。そして、それに繋がった引き綱を握るのは、壬生田様でした。
私が身につけているのは、首輪だけであありません。
私は、純白のウェディングドレスを着せていただいているのです。
薄い布でできたベールと、フリルとレースで飾り付けられた、花嫁衣装――ですが、胸の部分には布が無く、私のみっともないほどに大きな胸は剥き出しです。
スカートも、たっぷりとしたボリュームがありながら、丈が極端に短く、少し捲り上げればお尻が剥き出しになってしまうほどです。そうでなければ、とても四つん這いでは歩けなかったでしょう。
フリルがあしらわれた白いガーターベルトと、やはり白いストッキングを身につけてはいますが、ブラジャーも、ショーツも、付けていません。
そんな、結婚という神聖な儀式を冒涜するような衣装で、私は、足を踏み入れたことも無いような高級ホテルの中を、犬のように歩いたのです。
時間が真夜中だったので、人の姿はほとんど無かったのですが、一度だけ、無関係な宿泊客の男性とすれ違いました。
その男性は、ぎょっとしたような顔で、浅ましい姿をした私を見つめていましたが、壬生田様に従う黒服の部下の方の強面を見て、何も言わずに去っていきました。
そんな男性の視線にさらされ、徹底的にマゾ性を開発された私の女陰は、おびただしい量の愛液を溢れさせてしまいました。
太腿の内側まで愛液に濡らし、ストッキングに恥ずかしい染みを作りながら、私は、控え室で犬の“お座り”の格好になり、息をつきました。
これから始まる私の“結婚式”に対する不安に、私の心臓は早鐘のように鳴っています。
「おや、だいぶ緊張しているようだねぇ」
壬生田様が、そう言いながら、私の頬をピタピタと叩きました。
「どうするね? 今ならまだ間に合うよ」
「い、いえ……私……あの方のお嫁さんになります……」
「ムフフ、いい覚悟だ……でも、そうしたら、キミは正真正銘の牝犬だよ」
「…………」
壬生田様の言葉に、きゅん、と心臓が縮み上がり――なぜか、子宮がカッと熱くなります。
「か、構いません……香織の本性は、淫らな牝犬ですから……」
「しかし、今のキミの姿を見たら、旦那サンは本気で愛想を尽かすかもしれないぞ」
そう言って、壬生田様は、意味ありげに部下のお一人の方をチラリと見ました。
その部下の方は、私がこのウェディングドレスに着替えた時から、ビデオカメラを構え、私をずっと撮影しているのです。
「そ、それで、結構です……私は、一目でも夫に会えれば……」
「いいだろう……今のキミの顔は、最高にセクシーだよ」
そう言いながら、壬生田様が、自らの言葉を証明するように、ズボンの膨らんだ部分を突き出します。
私は、自らの不安を静めようと、目を閉じて、その部分に頬擦りをしました。かすかなペニスの匂いが、布の奥から私の鼻孔に届きます。
「――そろそろ時間です」
控え室に入ってきた進行係の方が、そう告げました。
私は、一度深呼吸をして、再び四つん這いになりました。
壬生田様の握る引き綱に導かれ、私は、会場へと向かいました。
「さあ、花嫁の入場です!」
暗い会場に入ると、司会の方の声が響き、次に、結婚行進曲が鳴りだしました。
スポットライトが、会場の扉をくぐる私を照らします。
「あぁ……」
たくさんの方の視線を全身に感じ、私は、我知らず吐息をつきました。
そのまま、父親に導かれる花嫁のように、赤いじゅうたんの上を通り、会場を横切ります。
会場にいる方々は、全て、私を抱いてくださったお客様でした。私に数々の刺青を彫ってくださった“先生”や、懐かしい宇治木様の姿もあります。宇治木様の隣で幾人目か分からない赤ちゃんをお腹に宿して微笑んでいるのは、琴音さんです。
私は、会場の上座に設けられた、大きな円形の舞台に上がりました。
そこには、私の花婿が、ハァハァとせわしない息をつきながら待っていました。
「うっ……」
獣臭いその体臭に、思わず、息を詰まらせてしまいます。
それは、上半身に特別製の白いモーニングを着せられた、一頭の大形犬でした。
褐色の毛並みと、黒く短い鼻面――犬の種類には詳しくありませんが、血統書付きのボクサー犬なのだそうです。その犬種としては並外れて大きく、そして、人間の女の“相手”をする訓練をみっちりと受けているとのことでした。何でも、未だに犬のメスとは交尾をしたことがなく、人間とのセックスの経験のみを重ねてきたということです。名前は、ジョンということでした。
これが――いえ、この方が、私の花婿なのです。
私は、舞台の上で、ジョンと並びました。
「あっ……!」
ジョンが、体の位置を変え、その鼻面を私の股間に押し当て、フンフンと匂いを嗅ぎました。
まるで、その鋭敏な嗅覚で、私の秘部が発情しているのを嗅ぎ当てたかのようです。
そのまま私にのしかかろうとするジョンを、調教師の方が、慌てて押さえ付けます。
「おやおや、花婿は、もう辛抱たまらない様子です」
司会の方がおどけた口調で言い、会場に笑い声が響きました。
私は、惨めさに目尻を涙で濡らしながら、ますます股間を濡らしてしまいます。
「では、花婿が限界を迎える前に、誓いの言葉をいただきましょう」
そんな司会の方の言葉とともに、聖書を携えた初老の男性が私達の前に現れました。この方は、本職の神父だと聞いています。
「宮倉香織」
神父様が、私の名を呼びました。
「あなたは、病める時も、健やかなる時も、富める時も、貧しい時も、この牡犬に終生妻として奉仕し、隷従することを誓いますか?」
「あ、あぁ……」
喉に何かがつかえたようになり、なかなか声が出せません。
そんな私の姿を、何台ものビデオカメラが撮影しているに違いありません。
私もかつては、今と同じようにウェディングドレスをまとい、夫とごく普通の結婚式を行った身です。
もちろん、その時は、自分がこのような惨めな性奴隷になるなどと、思ってもいませんでした。
それが――そもそもの間違いだったのでしょう。なぜなら、私は、夫と結婚するずっと前に、羽黒さんに調教され、淫らな奴隷にされていたのですから……。
ですから――私の今の立場も必然――私は、牡犬の花嫁になるのがお似合いな、正真正銘の淫らな牝なのです。
「……はい……誓い、ます……」
私は、心の中で何度も夫に詫びながら、震える声で、ようやく神父様にそう返事をしました。
「ジョン――あなたは、病める時も、健やかなる時も、富める時も、貧しい時も、この牝犬に終生夫としての愛情と精液を注ぐことを誓いますか?」
調教師の方に体を押さえられたジョンが、焦れたように吠え声を上げます。
それは、もちろん神父様の言葉を理解してのことではなく、ただ目の前にいる牝と早く交尾をさせてくれと訴えているだけように思えました。
「では、誓いの交合を――」
神父様のその言葉とともにジョンの調教師が手を放しました。
ジョンが、私の短いスカートの中に頭を突っ込み、グリグリとその鼻面を秘苑に押し付けます。
「あ、あうっ、うく……は、はあぁ、ああぁっ……」
生温かい息と、濡れた鼻面の感触のおぞましさに、私は、声をあげてしまいました。
やっぱりこんなことはやめてください、と、傍らの壬生田様に、情けない叫び声をあげてしまいそうになります。
その時、ジョンのザラザラした舌が、蜜にまみれた私の女陰をベロリと舐め上げました。
「あひいっ!」
鋭い快感に、私は、満場のお客様の前で、喉を反らしました。
そのまま、ジョンが、ピチャピチャと音をたてながら私の無毛の股間を舐め回します。
「あ、あううっ、あひ、あひっ……う、うぐぐ……うっ、うああっ、あひいっ……!」
愛液とともに、人間としてのプライドを長い舌で舐め取られながら、私は、断続的に声を上げてしまいました。
犬に、いいように感じさせられている、という事実が、私の被虐心を否応無く煽り立てます。
「はっ、はああっ、あっ、あううっ……あああぁぁ……あうっ、あひン、ひいぃン……ハァ、ハァ、アァ、ハァ……」
いつしか私は、牝犬そのもの喘ぎを漏らしてしまいました。
頃やよしと見て取ったかのように、ジョンが、私のお尻にのしかかります。
短いスカートがジョンの胴によって捲られ、剥き出しのお尻に、熱く堅い感触を感じました。
「あ、あああっ……!」
思わず視線を後ろにやると、真っ赤なペニスがジョンの股間から突き出ているのが見えました。
ジョンがカクカクと腰を動かすたびに、まさに肉の凶器といった外観のペニスの先端が、私のお尻を叩きます。
私は、無意識のうちに自らのお尻が逃げそうになるのを、必死にこらえました。
ワウッ、ワウッ、と声を上げながら、ジョンが、私の入り口を探ります。
「ううぅ……」
私は、この恥辱の儀式を早く終わらせたい一心で、ジョンのペニスに手を添えながら、大きくお尻を掲げました。
「おお、どうやら花嫁も、花婿の愛の挿入を待ち切れないようです」
司会の方の言葉が、私の心をずたずたに引き裂きます。
それでも、私は、ジョンのペニスを、受け入れるべく、その先端を自らの秘唇に導きました。
ジョンが、大きく腰を突き出し――呆気ないほどスムーズに、私の中に入り込みました。
「あうううううううっ……!」
人間のそれとは全く違う乱暴な挿入感に、私は、喉の奥から声を振り絞りました。
ジョンが、満足げな唸り声を上げながら、さらに腰を進め、膣内の奥地へとペニスを繰り出していきます。
「う、うあうっ、うぐぐ……あ、ああっ……あひ、あひい……あぁ、い、いやぁ……あっ、ああっ、あううううっ……!」
ジョンの、あまりにも自分勝手な腰使いが、犬に犯されている、という実感を際立たせます。
そして、ジョンは、私の背中に前足を置いて、カクカクと高速でペニスを抽送させました。
「ひああああっ! あっ、あっ、あっ、あぁーっ! う、うそっ、こんな……あひいいいいぃ〜!」
熱く逞しいペニスで膣壷を撹拌され、私は、甘い悲鳴をあげてしまいました。
「おお、花婿はなかなかテクニシャンのようです。花嫁の顔に、歓びの表情が浮かんでいます!」
「う、うっ……あぁっ、あん、あぁ〜っ! うあ、うああ、うっ……あひ、あひン、あひひっ……ひうっ、うううう……うあああああああっ!」
嘘です! という叫びが、恥ずかしい嬌声に埋没し、意味をなさない喘ぎと化していきます。
その瞬間、熱い迸りが、私の膣内の一杯に広がりました。
「あ……あああああああああああっ!」
犬に膣内射精された――その思いが、私を、最初の絶頂へと強制的に押し上げました。
「あああっ、うっ、あううっ、ひぐううううぅ〜! あぁ〜っ、イク、イク、イクうぅ〜っ!」
羽黒さんに、そして壬生田様に躾けられた通り、私は、自らがアクメに達したことを告げました。
変態的なウェディングドレスに包まれた体をヒクヒクとおののかせながら――私は、この屈辱の儀式がようやく終わることに安堵していました。
ですが、それは、あまりにも愚かな誤りでした。
「あ、あうううっ……え、えっ? 何? 何っ!?」
膣の入り口に強い圧力を感じ、私は、うろたえた叫び声を上げました。
「ご覧ください、皆様――ジョンが、花園に亀頭球を押し込み、花嫁を完全に自らのものにしようとしております」
司会の方の言葉どおり、ジョンは、ペニスの根元の膨らんだ部分まで、私の膣内に押し込もうとしているのです。
「うああっ! ダメ、ダメっ! あああっ、やめて、やめてぇ〜! ああああっ、イヤああぁ〜っ!」
私は、恥も外聞もなく叫びながら、舞台の上のじゅうたんを掻き毟りました。
しかし、絶頂の余韻に震える体は、思うように動いてくれません。
「ご存じの方もおられるかもしれませんが、犬は、交尾にあたって、そのペニスの根元の瘤で、パートナーの膣を塞ごうとします。そうやって、自らの精液が外に漏れないように蓋をしてから、本格的な射精に移るのです」
「ひぃーっ! ひいぃーっ! やめて、やめてやめてやめてっ! あああっ、誰か、誰か助けてぇ〜ッ!」
私の叫びを聞きながら、お客様も、司会の方も、ジョンの調教師も、神父様も、ニヤニヤと笑みを浮かべています。
そして、壬生田様も、興奮に目を血走らせながら、口元を歪めているのです。
そんな中、ジョンが、とうとうペニスの瘤を私の中にねじ込みました。
「うはっ!」
限界まで膣口を押し広げられ、私は、呆気なくまた屈辱の絶頂を極めてしまいました。
ジョンが、勝利の咆哮を上げながら、私の膣内に、大量にザーメンを注ぎ込みます。
「おあああああああ! 出てるっ! 犬のザーメン出てるっ! ああっ、あっあっあっあっあっ! に、に、妊娠しちゃうぅ〜ッ!」
その精液の量のあまりの多さに、私は、ありえないことを絶叫してしまいました。
「ひあーっ! ひっ、ひいっ、ひいいぃ……ひぐっ、ひぐうっ、うああああ! イ、イ、イ、イクうぅーッ!」
子宮に熱い生命の奔流を感じ、私は、さらなる高みに達してしまいました。
その時、私は、まさに身も心も牝犬にまで堕ちてしまったのだと思います。
「あうっ、あっ、あおおおおっ! イ、イク、イク、イクぅーっ! おおおおおおっ! おひーっ! おひぃいいいいぃ〜! イ、イ、イっちゃうっ! あああっ、牝犬マンコいきますうっ! あっあっあっあっ、い、いぐうううううう!」
熱い精液を体内に浴びながらイキ続ける私の背中の上で、ジョンが、歓びの声を上げています。
それは、まるで、私という存在を完全に自らのペニスによって征服したことを宣言しているようでした。
「あ、あうううっ、うはあぁぁぁぁぁ……いひぃ、いひいいぃぃぃ……あっ、ああっ……もう、もうダメぇ……あああ、イ、イク、イク、イクうぅ……!」
ビクビクと痙攣を続ける私の上から、ジョンが、ゆっくりと体をどかしました。
ですが、根元の肉瘤まで深々と突き刺さったペニスはそのままです。
「ぐひいいいッ!」
膣内でグルリとジョンの肉棒をねじられ、私は、後頭部を殴られたようなショックとともに、一瞬、意識を失いました。
「あ、あはぁ、あああぁぁ……ひっ、ひいいいいぃ……ひあああああ……イクぅ……イクぅ……」
半ば失心しながらも、私の肉体は、なおも変態的なアクメを貪りました。
私とジョンは、いま、お尻を突き付けあったような格好で、つながっています。
ゆっくりと回復する視界の中で、壬生田様が、その逞しい肉棒を剥き出しにして扱いています。
「ムフフ、香織クン、本当に幸福な顔をしているよぉ」
「あ、ああぁ……ハ、ハイぃ……香織はシアワセですぅ……んあああっ……こ、こんな立派なぁ……お、お、お婿さんを、世話してくださってぇ……あ、あ、ありがとうございましたぁ…はへええぇぇぇ……」
「ようし、じゃあ、幸せのおすそ分けをいただこうか」
壬生田様が、そう言って、涎をダラダラと垂れ流す私の口元に、赤黒い亀頭を突き付けます。
私は、ジョンとの交尾を続けたまま、壬生田様の太いペニスにむしゃぶりつきました。
「んむっ、むぐぐっ、ちゅぶちゅぶちゅぶ……んふっ、んふぅ〜っ……んぐ、んぐぐっ、ちゅぶぶっ……!」
胎内に、ジョンの精液がさらに溜まっていくのを感じながら、壬生田様にご奉仕します。
その頃には、お客様が舞台の周りに集まり、私の痴態を見つめながら、シコシコと手淫を初めていました。
「うっ、うん、うぅんっ……ちゅぶっ、ちゅぶぶぶっ……じゅぼぼ、じゅぼぼっ……うふぅ、うふぅ……うんっ、ううぅんっ……ちゅぶぶぶぶ、じゅるるるるるっ!」
私は、壬生田様のペニスを吸引しながら、自らのお尻をクネクネと動かし、ジョンのペニスを肉壷で味わいました。
少し腰を動かすだけで、圧倒的な容積を誇るジョンの肉瘤が、膣の入り口の一番感じる部分を刺激してくれます。
私は、ジョンとの交尾に夢中になりながら、壬生田様の肉竿に舌を絡め、喉奥まで駆使してフェラチオ奉仕を務めました。
「お、おうっ、出るっ!」
ビュッ! ビュッ! ビュッ! と、私の口内に、壬生田様が射精されます。
「んっ! んぐっ! んぐぐっ! うぶ、おぶぶっ……んふぅ、んふぅ……ごきゅ、ごきゅ、ごきゅっ……!」
私は、それを、祝福の美酒であるかのように飲み干しました。
「ふうふう……次は、お客様にご挨拶するんだ」
「ぷはあぁっ……あぁ、分かりました……ハァハァ……ど、どうか、皆様……この、卑しい牝犬花嫁の口マンコを使って楽しんでください……」
私は、そう言って、壬生田様と位置を交替したお客様のペニスを口に含みました。
どれくらい、時間が経ったのでしょう……。
私は、次々とお客様のペニスに口で奉仕し、喉奥や顔面で、祝福の精液を受け止めました。
順番を待ち切れなかったお客様の中には、手淫だけで果ててしまい、私のドレスに精液をかけてくださった方もいました。
私の体に付着した精液が乾いて異様な臭気を放ち、その上に、さらに精液が降りかかります。
そんな男性の匂いに包まれながら、私は、なおもジョンとの交尾を続けていました。
犬の交尾は、1時間にも及ぶことがあるという話ですが、ジョンは、そんな犬の中でも並外れた持続力を誇っているようでした。
私は、そんな逞しい“牡”の花嫁に選ばれたことを、心から嬉しく思ってしまいました。
そして、また、新たな肉棒が、目の前に突き付けられます。
それは、これまで目にしたどんなペニスよりも大きく、太く、そしてグロテスクでした。
亀頭部分は大きくエラを張り、肉竿の皮の下には真珠でも埋め込まれているのか、幾つもの突起があるのです。
思わずウットリとなりながら、大きく口を開けてそれを口内に迎え入れようとした時――その声が、私の耳に届きました。
「香織……君は……」
かつて毎日聞いていた、懐かしい声――
私は、ほとんど失いかけていた理性を取り戻し、視線を上に向けて、このペニスの持ち主の顔を見ようとしました。
ですが、ベールにベットリと精液が付着し、きちんと視線が遮られているのです。
「この……この、淫売がっ!」
その、懐かしい声が、聞いたこともなかったような口調で叫び――私は、無理やり肉棒を口にねじ込まれました。
「おっ、おぐぐっ! うぶっ! ンおおおおおっ!」
くぐもった悲鳴を上げる私の口腔を、その逞しいペニスが凌辱し、蹂躙します。
私は、その激しい抽送に、思考と感情をグチャグチャに掻き回されながら――凄まじいまでの快楽を感じてしまいました。
「このっ、このっ! どうだ! このおっ!」
「おううっ! うぶ、うぶぶ……! おぐっ、うぐうっ……おっ、おおおっ、おううっ、ぢゅぶ、ぢゅぶぶぶぶ!」
嘔吐感を伴った被虐の愉悦に全身を支配されながら、私は、口内を犯し続けるペニスに奉仕しました。
肉竿の突起が口内の粘膜を擦り、その刺激だけで私を絶頂に導きます。
「うっ――おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおッ!」
咆哮とともに、口内に、大量の精液が迸りました。
甘美な電流が、未だ犬のペニスを体奥に咥え込んだままの淫らな肉体を打ちのめします。
そして、私は、そのまま意識を失ってしまったのでした。